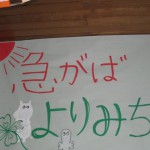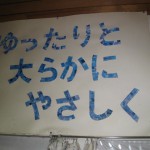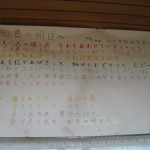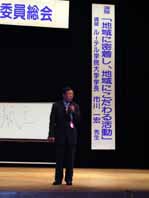社会福祉関連
夏の真っ盛りの7月、空は青く広がる札幌。札幌コンベンションセンターに1,200〜300人の民生委員・児童委員の方々が集まってこられる。
各年代層におよぶ参加者に、女性民生・児童委員の方々も多くなってきている。そして事例をお伺いして、各地域における生活課題に取り組む各委員の意欲が感じ取られる。まさに、社会福祉法下の新しい社会福祉の枠組みの中で、新たな役割を認識しようとする方々の意欲を感じる。確かに、地域福祉を推進してきた委員の実績は誇るべきものである。しかし、虐待、孤立等の問題が増加し、かつ地域自体もその姿をかえてきた。住民意識は多様化し、住民相互の関係も、以前と比べて明らかに希薄化した。民生委員・児童委員自身が、「何がしたいか、何ができるか、何が求められているか」を問われている。そもそも民生委員活動は、市民の視点が強調された市民活動である。したがって、民生委員は、市民活動としての一定の責任をもつものの、その活動範囲がいたずらに広げられてはいけない。そこで、私は、以下の留意点をお伝えした。
基本的留意点
1.地域の福祉を見守り、つくりあげる→→→地域を築く、創り出す。忘れてはならない地域性
2.主体は相手(秘密保持の原則)
信頼の絆は、必要な人以外には他言しないこと。
3.活動においていつも仲間の話し合いを→→→仲間同士の連携を、全部一人で背負わないこと。
4.各ボランティア団体、ボランティア、民生児童委員等、地域に関わる 人々同士が連携する場を→→→閉鎖性の打破、協力
5.活動が孤立しないように→→→機関(=社協)や既存のサービスとの連携を
6.開発性、先駆性と柔軟性を忘れずに
7.幅広い住民への対応
8.生活を支える総合的な生活援助と連携
*守ろう、育てよう、育もう、地域を! 住民とともに自分自身のために!
すなわち、地域を支える民生児童委員の役割は、共感、共歩、協働である。
-

-
札幌市民生委員大会1
-

-
民生委員大会2
-

-
民生委員大会3
投稿日 10年08月26日[木] 11:31 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2010年2月6日、大利根町第23回社会福祉大会の講演をさせていただいた。昨年に引き続き、2年目であったが、本年は特別の意味がある大会でした。
当日、朝8時30分に三鷹駅から中央線で新宿に向かい、乗り換えて10時頃にJR湘南新宿ライン栗橋駅に着きました。当日は、晴天でしたが、赤城山より冷たく、強い風が吹きつけ、体だけでなく、心も凍えそうになりました。
大利根町のホームページには、以下のように説明されていました。「埼玉県北東部の首都50km圏内に位置し、北部は利根川をはさんで北川辺町と茨城県古河市、東部は栗橋町、西部および南部は加須市に接し、町の総面積は24.47km2で、東西に約6.2km、南北に約5.6kmの広がりをもっています。北部を利根川が流れ、関東平野のほぼ中央で、海抜13mの平坦な地形をしています。
産業の中心は農業で、こしひかり、いちごなどを生産する県内でも有数の穀倉地帯です。また、黒米を使った加工品をはじめとした特産品や農産物は、農業創生センターで販売され、町の観光拠点となっています。」
また、大利根町は、「童謡のふる里づくり宣言」をしました。大利根町は、「たなばたさま」「野菊」など数々の童謡を作曲し、またたくさんの校歌を作曲なさった下總皖一先生の生誕の地です。そのことを誇りに、「誰もが生き生きと、夢を持って生活できるような豊かな地域社会を創出していくためには、童謡の持つやさしさをまちづくりの基本とし、みんなで手を携えて、まちづくりを進めていくことが重要」として、以下のことを宣言しました。
- 私たちは、下總皖一先生をふる里の誇りとし、いつまでもその素晴らしさを多くの人々に伝えます。
- 私たちは、童謡の持つやさしさをまちづくりに生かし、みんなが夢を持てるようなまちをつくります。
- 私たちは、童謡のふる里にふさわしい、人や自然にやさしい豊かなまちをつくります。
- 私たちは、童謡を始めふる里の伝統・文化を生かし、活力ある新しいまちをつくります。
- 私たちは、一人一人が主役であり、「全国に誇れる童謡のふる里おおとね」を目指し、みんなで努力します。
第23回社会福祉大会では、大利根町社会福祉協議会から「地域福祉は毛細血管のように~一人ひとりの暮らしを支えあう地域づくり~」というテーマをいただきました。実は、大利根町は2010年の3月に、近隣市町と合併し、加須市と名前を変えることになっています。大利根町という地名を使うことがなくなるのです。その事実の約1ヶ月前に、皆さんは、例年通り社会福祉大会を開催されたのです。
手のシワと手のシワを合わせて、「幸せ」を願う。そのシワは、まさに申し上げた文化と伝統であり、同士の絆、地域との繋がりであり、そこに生きた住民一人ひとりの人生だと思います。合併は、それぞれの市町村という手が、シワを合わせ、幸せを目指した取り組みであることを期待しています。そのことを町民の皆さんは、確認なさったのだと思っています。
私は、講演のまとめとして、以下の4点を申し上げました。
- 孤立等の地域の生活問題の早期発見・早期連絡(アンテナ)は、地域の福祉力。
- 共に支え合うまちづくり=理解や協力の基盤づくり
そもそも、コミュニティとは?
- コミュニティに所属する者同士の相互の関わり
- 関わりに対するアイデンティティ、愛着
- それらを実現しやすい地理的な空間
- 互いを認め合うコンセンサスと一定の規範
- コミュニティを支える宗教や祭り等の文化の形成
- 人材や活動等、一定の地域資源の存在
- 血の通った活動は、生活の潤滑油
地域密着型サービスの本来の意味
- 眠っている資源を掘り起こす(大利根町の底力)
「人」 問題解決に取り組む当事者、医師、保健師、社会福祉士・ケアワーカー・ケアマネジメント等の専門職、住民、ボランティアといった保健医療福祉等に関わる広い人材 「もの」保健・医療・福祉・教育・公民館等の施設、空き家・空き店舗、サービス・活動、物品はもちろん、住民関係、地域関係、またボランティア協議会、医療保健福祉等の専門職ネットワーク等のネットワーク 「金」 補助金・委託金、寄付金、収益、研究補助金
「とき」就業時間、ボランティアが活動する時間。課題を共有化し、合意して取り組むチャンス
「知らせ」資源情報、サービス利用者情報、相談窓口における情報等のニーズ情報、計画策定に必要な統計等の管理情報
大利根の地名はなくなっても、その地域はなくなるものではないし、住民がいつものように生活しているという事実から出発するのが、地域福祉の本来の姿なのです。
栗橋の駅をおり、再び会場に着き、皆様方の顔を見て、私はある歌を思い出しました。いずみたく作曲の歌です。
「ぼくらは みんな 生きている
生きているから 歌うんだ
ぼくらは みんな 生きている
生きているから 悲しいんだ
手のひらを太陽に 透かして見れば
真っ赤に流れる ぼくの血潮 ・・・・・」
それぞれの手を、明日という太陽に向け、流れる血潮という、文化と伝統、同士の絆、地域との繋がり、住民一人ひとりの人生、一人ひとりの顔を確かめていくことは、合併の趣旨に反するのではなく、まさに合併による幸せを実現するのです。豊かな自然の実り、温かい人と人の絆がいつまでの守られ、大利根町が目指した明日が、実現できますことを心より願っています。
投稿日 10年02月06日[土] 12:00 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
時:9:30〜11:00 民生委員の方々への講演
「地域福祉と民生委員の役割」
11:00〜12:20
地域福祉計画・地域福祉活動計画についてのヒアリング
13:10〜14:00 川又地区いきいきサロン
熊本で3日間開催されたるうてる法人会連合総会、ルーテル諸学校代表者会を終え、午後3時のバスで宮崎北部の山間地に向かう。空は、雨で覆われ、阿蘇は嵐の中。黒川温泉に行く時もそうだった。また空から見る阿蘇は、時々荒れていた。だからこそ、阿蘇は雄壮なのかもしれない。
翌日、日之影町を訪問する機会を与えられた。あくまで、私自身のお願いであり、すべて自前でするつもりだったが、日之影町は、民生委員の方々にお話をする機会をつくってくださり、また町を案内してくださった。
宮崎県内の中山間地の過疎問題への取り組みを進める委員会の委員長を仰せつかっており、今回はほんとうに大切なアイデアを得ることができた。 以下、私の意見をお渡しした。
1.民生委員研修
非常に誠実、かつ実直な方々で、隣人愛に根ざした使命感をお持ちのように思えた。これは、町の大きな資源。このネットワークをいかに小地域活動に結びつけるか、また活動の効果を高めるために、行政、社協、町の保健医療福祉専門職がどのようなバックアップシステムをとることができるか、個別検討を含めて、問われていくことになると思います。
2.人口の減少が続いている現在、非常に難しいことかもしれませんが、安心して生活できる、どのような町をつくっていくのかという展望が見せられないでしょうか。人生の定年は、生命を失う時。それまで、以下の豊かに生きていくか、それを支えるこの5年の目標を立てる必要があります。
そのために必要なことは、予防、自己啓発、近隣の助け合い、サービスの内容や運営方法の相違工夫です。これが総合的な日常生活支援となります。そのために、行政や社協の役割があり、こだわりがあると思います。
3.実施主体、運営方法をより明確にしていただくことが大切です。両計画を一体でたてることは十分考えられるのですが、実際に責任が不明確になる危険性が十分あり、結果として機能しない計画になってしまいます。
住民も含めて、それぞれが何をするのかということの合意をすすめてください。
4.優先的に進めるものを明確にしてください。また、既存の活動、サービスを実施する、強化する、再編する、新たに活動やサービスを生み出す、運営方法で効果を高める等のことがわかると、住民の理解を得ることができます。
5.専門職の役割と配置を明確にすること。特に、コーディネートする役割を持つ専門職がいませんと、限られた資源を有効に活用、開拓することができません。
6.資源の活用で事業化できるもの、たとえば現在使われていない住居等を活用した地域密着型施設、介護予防等の明確化が望まれます。
7.あえて、生活の質を基軸にした計画を作成してはどうでしょうか。すばらしい水と空気(親好)、おいしい食物と生命の質(健康)、豊かな近隣関係(親交)、生きる姿を大切にする宗教(信仰)、大人歌舞伎等の伝統と豊かさ(光)、働く機会と自己実現(振興)を軸に、予防、支え合い、地域振興とまちづくりを組み立てられないか?
8.資源の吟味を進めること
現在のネットワークは重要です。福祉でまちづくりの視点は不可欠でしょう。広範囲に、かつ小規模集落が点在しているという地域特性から見ると、それぞれの集落にある「水」、整備され、網羅された「道」、きれいな「自然」も重要な資源でしょうか。結ぶという視点で何かプランはできませんか。また、自分の田畑以外の田畑を耕す活動もあるとするなら、その主体を増やしていくことも可能でしょう。それも産業化につながりますか。オーナー制も考えられますか。とにかく、ある資源を活用し、町を維持していく、そして、生活しておられる方々が誇りと安心感をもって生き続けられるため、地域福祉計画がまちづくりとなることを願っていますし、応援しています。
日之影町は、かっていくつもの村が合併してできた町で、広範囲の地域に、比較的小規模な集落が点在している。すばらしい自然があり、水がでる場所に集落ができ、おいしい米と収穫物は地域力である。確かに、高齢化が進み、過疎が進行してきていることも事実。だが、そこに住み続けられる人々がおり、生活を支える文化や伝統が残されている。その事実から、将来を見据えた改革をすべきではないでしょうか。
昭和30年代後半から始まる高度経済成長は、物質的豊かさをもたらした。「パイの理論」が主張され、パイ自体が大きくなれば分配するパイも大きくなると言われてきたが、ふくらんだのは、パイの殻だけだったのではないだろうか。人々の心の空洞化が始まり、バスに乗り遅れたたくさんの人々が生まれた。引きこもり、家族崩壊、社会的孤立、自殺者3万人、依存症等々。
今また、目の前から、生活が、文化が壊れていくように思える。日之影町で私が学んだことは、生活の豊かさとは何か。生活の溶け込んだ文化があり、人々は自然に向かって祈りを捧げること。それは、第1に生かされていることの感謝、第2に日々の生活への愛着、第3に生きていくことの誇りであり、文化となってそれぞれの生活に根ざしている。
それらは、いずれも現代に生きていく人々が取り戻さなければならいこと。
翌日には、宮崎県社協において、「中山間地域・過疎地域等の人口減地域における地域福祉サービス・活動研究委員会」が開催された。委員会には、社会福祉の行政、社協関係者とともに、農協、商工会の代表にも委員として入っていただき、検討している。
過疎問題に取り組む際には、以下の基本的視点が大切である。1.マイナス・危機は取り組み課題、プラス・可能性は資源として積極的に活用していくこと、2.日常的な関係等のソーシャルキャピタルを、一つの地域の可能性として維持・発展させていくこと、3.課題の共有化と合意、そしてそのプロセスを大切にすること、4.地域の資源とは、ひと、もの、かね、とき、知らせと広範囲であり、丁寧な地域診断が不可欠であること、5.地域の再生や活性化を含むまちづくりの視点を必ず加えること等である。
本研究の目標として、事務局である宮崎県社会福祉協議会の山崎地域福祉課長らが考えている、ア.生まれ育ったところで暮らし続けることを支える仕組みづくり、イ.住民や多様な団体・機関の参加と協働のための仕組みづくり、ウ.地域再生・活性化のためのまちづくりの3つが組み合わされてはじめて、本研究会の目標が提示されるのである。
これらの取り組みは、決してたやすいことではない。しかし、実際にそれを実現してきている市町村も少なくない。「なぜ、そうなったか」の理由を考えるだけでなく、「なぜ、そうならなかったのか」という視点も大切にしたい。
投稿日 05年08月25日[木] 12:50 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
「人にやさしい福祉のまちづくり学園」が宮崎県で行われた。実践講座を含め、6回講座の最初の講演を担当させていただいた。企画運営は、恵佼会(代表者土居雅郎氏)が中心となっていた。私の講演テーマは「福祉のまちづくりと実例」であり、物理的バリアフリー、制度的バリアフリー、文化・意識のバリアフリー、情報面のバリアフリーをめざしたまちづくりの意味を、1.地域性の尊重、2.当事者性の確保、3.連携、4.生活者の視点、5.多様性・柔軟性・総合性という特徴を具体的な実例を通して説明していった。
風が非常に強い大型台風16号が南から近いづいてきており、前日まで、講座そのものの開催が危ぶまれていた。その強さをいっこうに衰えさせることなく、ゆっくりと、しかし着実に九州に近づいてくる台風の進路を見極めるため、主催者は前日の午後1時に、開催するとの最終な決断をした。私は数日帰れないことを覚悟しながら、依頼された講演の責任を最後まで全うできることを目指した。長い間、十分討議しながら準備を重ねてきた企画である。自分のできることは、精一杯したい。
前日の最終で宮崎に入ったが、九州に近づくにしたがって、飛行機の揺れが激しくなり、横風を受けながらの着陸となった。そして一晩中、風がうねり、きしむ音が鳴り続いていた。また予約していた午後4時台以降、台風が通り過ぎるまで飛行機は運休することが予想されてたため、伊丹経由羽田行き12時台の飛行機に変更し、講演後すぐに、待たせていたタクシーに飛び乗り空港に向かった。
飛行機の到着が遅れたため、伊丹では走って乗り継ぐことになった。伊丹行きは、横5席、縦30席程度の飛行機であったため、離着陸時の揺れは、なかなかスリリングであった。窓から見える地上は、いつもの通り平穏であり、たくさんの車が走っている。飛行機の中からその景色を見ていると、心が落ち着いてくる。 「あともう少しの辛抱だ」というサインに思えるから不思議である。寸前まで雲で覆われていたら、精神的不安は大きい。
約3時間かけて羽田に到着し、電話をかけた。宮崎発の飛行機の運航はむずかしい様子。しかし、午後の車椅子体験は、天候の崩れも限界値を超えることなく、無事済んだとのことであった。「雨の天気でも、障害者は出かける。そのことを経験してください」という主催者の思いが通じたのか。

嵐の前の宮崎空港

雲の間に挟まれて飛ぶ飛行機

講座参加者
投稿日 05年04月07日[木] 12:06 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
嫌煙権が認められ、喫煙場所が限定されることは、当然である。公共の場では、室内全面禁煙、または分煙が実施され、特定の場所に喫煙所が設けられている。例えば、喫煙室には換気扇が付けられ、煙害を防ぐ様々なシステムが作動する。しかも、ほとんどの喫煙室はガラス張りで、外から見る姿は、煙の談合。
横浜市戸塚区の公共施設の喫煙室の周囲には、一定の空間があった。そこでは、ブロック創作等の様々なプログラムが用意されている。母親教室なのだろうか。すぐそばで子供と若い親が一生懸命に創作作業に取り組んでいる姿を見て、喫煙室から煙がもれていないか心配する喫煙者。また子供に喫煙するところを見られて、将来、子供の生活習慣に悪影響を与えないか心配する喫煙者。
ここは、もっともタバコを吸いにくい場所。
投稿日 12:06 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
湯河原駅近辺で児童養護施設城山学園までの道を聞くと、必ず「歩いて行かれるのですか」との問いかけがある。なぜなら、湯河原駅から東京方面にむかい、線路沿いを歩き、すぐのガードをくぐると、そこからはひたすら坂道を登り続けることになる。城山の中腹にある学園までの勾配は、想像以上に急であった。
2004年の12月、宇留田貞子さんから、一通のクリスマスカードが届く。私自身はお会いしたことがなかったが、父が生存中に、たいへんお世話になった方。年の暮れである失礼をお許しいただいて、日本キリスト教団湯河原教会でお会いするお約束をした。お礼を申し上げたかったからである。
お話の中で、私が尊敬する大村勇先生、阿部志郎先生、山崎美貴子先生、飯田進先生等々のお名前が出され、宇留田さんの歴史が語られた。まさに神と人に仕えた84年の証であった。語られた歩みの中に、児童養護施設城山学園との長年の関わりをお聞きし、「是非訪問させていただけないでしょうか」とお尋ねすると、「多分、子どもや職員が少ない時期ですが、大丈夫だと思います。聞いてみましょう」とお返事をいただいた。
宇留田さんと、長男、私が乗ったタクシーは、ギアをロウにしたまま、坂道を学園に着くまでかけ登る。湯河原駅からは一区間ではあったが、私にとって、ほんとうに長い道のりの思えた。学園の玄関前で、たくさんの子どもたちが遊ぶ。例年より多くの子どもたちが、学園で正月を過ごすとのこと。
さまざまな理由で、両親と暮らせないたくさんの子どもが、自分の生活をここで生きる。そして、子どもたちには、それぞれの思いがある。それぞれの生き方があるし、それは自分にとっての人生。その事実に真向かった人々がいた。子どもたちの笑顔と、子どもたちの幸せと寄りそって、人生を自分らしく生きてきた宇留田さん、全国のたくさんの教会やYMCA等の関係者が、子どもたちのために物置をつくり、土手をつくり、庭をつくり、部屋をつくった。正月に帰れない子どもを実家に連れて行く職員。子どもたちの正月を心配する人たち。今、子どもたちと一緒に生き、また子どもたちを見守る人々がいる。
城山学園には、たくさんの人々の思いが埋まっている。学園は、求められる声に応じて、その役割を広げてきた。当初は1階の建物であったとお聞きしたが、必要に応じて、2階へ、そして3階へと、生活の場を積み上げてきた。学童保育、個別の勉強指導、ユニット化、地域での生活をすすめるぐるーぷほーむ指路(松島賞受賞)の建築などの取り組みは、日本における児童養護の歴史の縮図でもある。城山の傾斜に建てられた学園のその敷地で子どもたちが遊ぶ。時には、城山の庭で遊び、また急な階段を登り、笑い声をあげる子どもたち。彼らは、城山のすべてを遊び場にかえる。
城山学園から階段を登り、大分急な斜面を登ったところに墓地があるとお聞きした。そこには、病気でなくなって引き取る人がない子どもたち、不慮の事故でなくなった卒園生、担当牧師の遺骨が安置されているとのこと。城山学園は、そこで育った子どもたちの一生に寄りそう。そして同じ場所に、一生をかけて子どもたちと歩んだ方の遺骨が並ぶ。
毎日、子どもたちはその坂を登る。しかし、日本社会は、その登り方と頂上を、経済効率と経済的繁栄で意味づけた。そして「バスに乗り遅れるな」という合い言葉で、高度経済成長が進められたが、他方、たくさんの人々が、切り捨てられ、自分らしく生きていきたいと思いを捨てざるをえなかった事実がある。だからこそ、今、それぞれが、幸せを求めて歩む姿を大切にしようとする「オーダーメイドの社会づくり」が進められてきている。「Only one」という言葉に素直に共感する人も増えてきた。「老いの坂をのぼりゆき、かしらの雪つもるとも、かわらぬわが愛におり、やすけくあれ、わが民よ」(賛美歌第284番4節)という歌詞を私は好きだ。一生は、その人なりに頂上への坂を登りゆくことである。子どもたちも、明日への希望に導かれ、親族や職員に手を借りて、一歩づつ坂を登る。今、その事実を大切にしてきたかと、私たち一人ひとりが問われている。
城山学園から見る海がとてもきれいだった。大島、神津島等々が、いつもより透きとっていると言われる空が、海と島の美しさをうかびあがらせる。
子どもたちが、その目で、城山から見下ろす自然の豊かさと美しさと恵みを大切する社会にしたい。子どもたちの心を受けとめる社会にしたい。子どもたちが、将来への希望をもって、育っていける社会にしたい。この坂を、毎日、いろいろな思いをもって登る子どもたちの生きる姿を見守りつづけることが、今、私たちに求められている。
投稿日 05年01月04日[火] 11:50 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
長野県の民生委員・児童委員の働きは、地域に根ざしたものであり、その実績は高く評価されている。前日、栃木県から上田に出て、バスで鹿教湯温泉に泊まり、丸子町に戻った時の気温は、30度を軽く超えていた。町役場でバスをおり、そこから荷物を引き、丸子町文化会館の到着した時には、広い長野県内の市町村からたくさんの民生委員・児童委員の方々が来られていた。講演とシンポジウムの間、その熱い情熱と、一言ものがさず聞こうとなさる姿勢に感銘を受けた。
テーマは、「地域に密着し、地域にこだわる活動」である。かって、小金井市のケアマネジメント研究会の責任者を3年にわたり担わせていただいた時、最後の会議で、参加しておられたボランティアの方から本をいただいた。その方は、佐久の病院長を長く続けられ、疾病率の高かった長野が健康推進県となる原動力となった若月先生の娘さんで、いただいた本は、若月先生の論文を集めたものであった。何かと長野とは縁がある。
<概要>
- 直面する地域福祉問題
- 介護・養育→(家族・地域関係の喪失と無理解)→虐待
- 孤立→問題の潜在化と深刻化→老化の進行や疾病の急激な悪化
- 家族負担→世間体・誤った介護者の意識・介護されるものの自立意識のなさ→介護地獄
- 学校・家庭以外の止まり木がない→出会いの場の限定と孤独感→非行・不満・閉じこもり
- 社会福祉における小地域福祉活動=住民が取り組む地域福祉活動とは何か
- 地域福祉活動の担い手=民生児童委員・福祉推進員に期待される役割
- 地域を耕すための連携
投稿日 11:50 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2004年10月7日、三重県社会福祉大会の講演をさせていただいた。テーマは、「今日の社会福祉の目指すもの~地域福祉型福祉サービスの展開~」である。とくに日常生活の拠点である地域で、生活を支え、支え合うシステムをつくる試みを軸に事例を通してお話しした。
大会の数日前、台風により、洪水がおき、三重県南部の地域は、甚大な被害を受けた。また三重県内のいくつかの市町村では合併が進められ、その調整に大きな時間を要していた。しかし、そのような状態にあっても、各地から600~700名の方々が来られ、身が引き締まる思いがした。
私にとって、三重県は友人の多い県の一つであり、今まで県内のいくつかの市町村を訪問させていただいた。県社協がある津市には、毎年来させていただいているが、その他、四日市、伊勢、上野、菰野、鳥羽等々に行った。なかでも、三重県のもっとも南部の郡に日帰りでの講演は、私にとってとても印象深い。自宅から東京駅まで約1時間、東京駅から名古屋駅まで2時間、さらに名古屋駅から現地まで特急で3時間、片道6時間を往復した経験がある。確かに限定された空間ではあるが、実体験に基づいて地域を考えることは、大切である。そして友人の若手医師が、故郷であるその地でいずれは開業しようと考えており、その意味でも親しみ深い。車窓から見える景色や生活の場は多様であり、美しいが、利便性としては必ずしも都市型のようには行かない。しかし、年に欠落している地域への愛着性、住民間や職場との関係性においては、住みやすい場所である。地域福祉とは、各地域の固有性、地域的特性や地域の文化を大切にすることから始めるのであり、「金太郎飴」のようにどこを切っても同じ姿というものではない。各地域の強さと弱点を理解し、課題を共有化して臨むことからはじまる。したがって。強みは活用課題、弱点に対応課題である。
生活基盤を基点においた地域福祉活動が求められているのであり、合併をしても決してその活動の意味は変わらない。
- 小地域福祉活動=住民が取り組む地域福祉活動とは何か
小地域ごとに地区社会福祉協議会またはそれに代わる基盤組織を設置する。 - ふれあい・いきいきサロンの広がり
- 見守り・友愛活動等の住民活動・生活環境の改善(雪下ろし含む)と市民型ボランティア活動
- 住民参加型在宅福祉サービス供給組織の変化
- 小規模多機能施設の拡大
以上は、地域密着型、まちづくり、多様な市民・住民参加等の共通の特徴をもっており、地域福祉型福祉サービスの典型的な例と言えよう。
投稿日 04年10月07日[木] 11:06 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
« 前のページ
次のページ »
 ①コミュニティに所属するもの同士の相互の関わり
①コミュニティに所属するもの同士の相互の関わり
 講演が終わり、社協会長や関係者の方としばしお話をし、再会を誓い、上越市社会福祉協議会が経営するやすづか学園に向かった。会場から、車で40分ほど行った、自然に満たされた地区にあった。畑があり、川があり、木々が生い茂り、途中の道の駅で売られていた自然の実りを見て、自然の恵みを感じた。確かに、人口の減少は否めない。しかし、そこにある、人々のぬくもりや思いやり、厳しくはあっても生命を生み出す自然は、子どもたちが育つ土壌であり、住民の思いやりは、子どもたちにとって肥料でもある。また管理されない自然は、猛威となって市街地をおそう。土石流は、上流の自然破壊を原因としている場合が多い。また、子どもたちが、将来、働く場を見いだせない社会は、希望のない社会。そのことをもっと国政は考えないと、国会議事堂という狭い地域にしか通用しない常識は、これを非常識と言うのではないだろうか。今、必要なことは、日本の未来を描くこと。失われる伝統、文化、自然、人間関係、農業・漁業・林業等の第一次産業が崩壊すると、その再建は不可能に近いし、また可能であっても何十倍も手間と時間がかかる。一刻の猶予もないはずである。
講演が終わり、社協会長や関係者の方としばしお話をし、再会を誓い、上越市社会福祉協議会が経営するやすづか学園に向かった。会場から、車で40分ほど行った、自然に満たされた地区にあった。畑があり、川があり、木々が生い茂り、途中の道の駅で売られていた自然の実りを見て、自然の恵みを感じた。確かに、人口の減少は否めない。しかし、そこにある、人々のぬくもりや思いやり、厳しくはあっても生命を生み出す自然は、子どもたちが育つ土壌であり、住民の思いやりは、子どもたちにとって肥料でもある。また管理されない自然は、猛威となって市街地をおそう。土石流は、上流の自然破壊を原因としている場合が多い。また、子どもたちが、将来、働く場を見いだせない社会は、希望のない社会。そのことをもっと国政は考えないと、国会議事堂という狭い地域にしか通用しない常識は、これを非常識と言うのではないだろうか。今、必要なことは、日本の未来を描くこと。失われる伝統、文化、自然、人間関係、農業・漁業・林業等の第一次産業が崩壊すると、その再建は不可能に近いし、また可能であっても何十倍も手間と時間がかかる。一刻の猶予もないはずである。 菱沼地区の小高い丘に、学園はあった。今は統合された小学校を学園として活用し、近くにある寮から通う小学校高学年から中学校生の10数名の生徒がここで学んでいた。この学園の特徴は、地域が子どもの育ちを支えていることである。やすづか学園菱里地域支援委員会が設置されている。菱沼、おぎの、須川、船倉の町会長、11の集落の自治会長、農家組合長、そして老友会等の各会の代表者が加わる地域支援委員会を設け、さらに家庭交流部会(子どもとの交流、手打ちそば作り体験、焼肉大会)、地域活動交流部会(収穫感謝祭、塞の神作り)、農村文化技術部会(田畑の管理、動物の飼育、農作物体験、技術指導)、農産物部会(給食用農作物の提供)、環境美化部会(学園関係施設の環境美化協力、羊、鶏の小屋づくり)が実際の活動にあたる。
菱沼地区の小高い丘に、学園はあった。今は統合された小学校を学園として活用し、近くにある寮から通う小学校高学年から中学校生の10数名の生徒がここで学んでいた。この学園の特徴は、地域が子どもの育ちを支えていることである。やすづか学園菱里地域支援委員会が設置されている。菱沼、おぎの、須川、船倉の町会長、11の集落の自治会長、農家組合長、そして老友会等の各会の代表者が加わる地域支援委員会を設け、さらに家庭交流部会(子どもとの交流、手打ちそば作り体験、焼肉大会)、地域活動交流部会(収穫感謝祭、塞の神作り)、農村文化技術部会(田畑の管理、動物の飼育、農作物体験、技術指導)、農産物部会(給食用農作物の提供)、環境美化部会(学園関係施設の環境美化協力、羊、鶏の小屋づくり)が実際の活動にあたる。 夕方近くになり、次第に暗くなっていく時間に、私は学園に到着した。学園に入ると、歓迎の看板に恐縮し、靴を脱いで校舎に入った。いたるところで子どもたちの声が聞こえる。案内いただいた食堂から調理を手伝う子どもたちが見える。後でお聞きしたが、私の友人の知り合いのお母さんが調理を手伝われており、子どもが家に泊まることもあるとのこと。また、教職員の方々といつも一緒にいる子どもが、お茶を入れてくれた。先生が子どもたちに、私を歓迎するため演奏を依頼したところ、彼らは快く引き受けてくれた。
夕方近くになり、次第に暗くなっていく時間に、私は学園に到着した。学園に入ると、歓迎の看板に恐縮し、靴を脱いで校舎に入った。いたるところで子どもたちの声が聞こえる。案内いただいた食堂から調理を手伝う子どもたちが見える。後でお聞きしたが、私の友人の知り合いのお母さんが調理を手伝われており、子どもが家に泊まることもあるとのこと。また、教職員の方々といつも一緒にいる子どもが、お茶を入れてくれた。先生が子どもたちに、私を歓迎するため演奏を依頼したところ、彼らは快く引き受けてくれた。