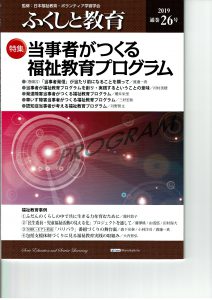学会
皆様
新たな年度を迎え、お忙しいことと存じます。
私も、ルーテル学院大学43年目を迎え、地域福祉論の授業を担当することに感謝しています。学生諸君が満足してくれる授業を目指します。
また、4区市の介護保険事業計画・高齢者総合計画の作成に関わらせていただきますが、今回は、制度自体の基盤が揺れており、またニーズも深刻化している現状にどのように取り組むか、非常に難しい舵取りを迫られます。委員の方々とご相談するとともに、課題をまとめて、厚労省の担当部局に問い合わせをさせて頂くことも考えています。ご助言頂ければ幸いです。そして、本年は、民生委員児童委員の改選期。当然、地域包括ケアシステムにおいて重要な方々です。介護保険でも、話されるべきことと考えます。関係する私の意見書を再送します。
お元気で。
ルーテル学院大学
名誉教授 市川一宏
1.全社協メールニュースを送らせて頂きます。
地域福祉・ボランティア情報ネットワーク メールニュース(社協版)
2025(令和7)年度/第1号(通算1045号) 2025.4.1
https://www.zcwvc.net/ E-mail:c-news@shakyo.or.jp
このメールニュースは、「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」のサービスとして、社会福祉協議会関係者に向けて地域福祉、ボランティア・市民活動関係の情報をいち早くお伝えするサービスです。
■ 全社協からのお知らせ等
◆令和7年度「社会福祉法人会計実務講座」のご案内(全社協 中央福祉学院)
社会福祉法人の会計担当者の主な役割は、日々の実務を適切に遂行しつつ決算書を作成することにあります。法人の経営を分析し、経営戦略を考える際、会計担当者が作成する会計・財務資料が重要な役割を果たします。本講座は、会計実務の基礎から財務管理まで段階的に学び、会計の知識を幅広く習得することができる講座です。「社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を理解し、学んだ知識および技術を各社会福祉法人の適切な運営と発展に資することを目的として開講します。なお、本講座では、会計区分の設定の仕方など社協特有の会計処理を学ぶことができる「中級社協コース」を設けています。【受講期間】2025年8月1日~2026年1月31日(6か月間) ※うちスクーリング(集合研修:ロフォス湘南(神奈川県葉山町))に3日間出席。
【受講対象】「社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を行う社会福祉協議会・社会福祉施設・事業所等の役職員
【受 講 料】入門コース/26,400円(税込) 初級コース・中級(社協、施設)コース・上級コース/47,300円(税込) ※通信授業テキスト・教材費、添削指導料、スクーリング参加料を含む。
※スクーリング(集合研修)に係る旅費・宿泊費等は別途負担。
【申込締切】2025年5月16日(金)※先着順
【詳細・申込】下記URLをご参照ください。
【問合せ先】全社協 中央福祉学院 社会福祉法人会計実務講座係
TEL:046-858-1355 FAX:046-858-1356
◆全国で「福祉の就職総合フェア」を行います(4月分)(全社協 中央福祉人材センター)
都道府県福祉人材センターおよび福祉人材バンクにおいて、福祉のお仕事に関する就職総合フェアを行います。各都道府県内の求人事業所がブースを出し、福祉の職場や仕事内容の説明をしたり求職者の質問に直接お答えします。その他、福祉の仕事や就職活動の理解を深めるセミナーや事業所職員によるトークセッション、介護ロボット展示、転職時の資金の貸付事業(介護分野就職支援金貸付事業等)の案内等、さまざまなプログラムが行われています(開催都道府県により内容は異なります)。下記URLより詳細が確認できますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。ご不明な点は、各センター・バンクにお問合せください。
【掲載内容】2025年4月分 【詳 細】下記URLをご覧ください。
https://www.fukushi-work.jp/news/detail_67.html
■ 他団体からのお知らせ等
◆日本地域福祉学会第39回大会(兵庫大会)のお知らせ
地域福祉における「住民自治」のあり方を問う~地域福祉の政策化の時代における「住民自治」の意義と実践の可能性を探る~ (日本地域福祉学会、日本地域福祉学会第39回大会(兵庫大会)実行委員会)
本大会では、地域福祉(「地域における社会福祉」)が政策的にも推進されるという今日的な動向をふまえて、2日間のプログラムを通して、地域福祉(地域による福祉)における「住民自治」の意義と実践の可能性について、理論的な検討を通じて争点を明確にしたいと考えています。あわせて主として近畿圏での地域福祉に関する実践やまちづくりの取り組みを検証することで、地域福祉における「住民自治」の意義と可能性について議論を深めます。
【日 程】2025年6月28日(土)~29日(日)
【会 場】武庫川女子大学 中央キャンパス 公江記念講堂ほか(兵庫県西宮市池開町6-46)
【参加対象】どなたでも参加できます。
【参 加 費】会員事前申込み(団体会員を含む)/8,000円 会員当日申込み・非会員/10,000円 大学院生/4,000円、学部学生/1,000円 要旨集/2,000円
【団体会員について】地域福祉学会では、2022年に団体会員制度を創設し、社協や社会福祉法人、NPO法人などが会員として活動しています。団体会員は、団体として大会で研究発表ができるほか、学会誌「地域福祉実践研究」のなかで「団体活動実践報告」として投稿できます。ぜひこの機会に加入をご検討ください。
【締 切 日】2025年5月22日(木)24:00 ※事前申込締切
【主なプログラム】<1日目>○基調鼎談:地域福祉における「住民自治」をめぐる論点整理―地域福祉の理論と実践の分析・検討を通して―
○大会企画シンポジウム:地域福祉におけるコミュニティの主体性と「住民自治」を問う ―地域福祉とまちづくりの接点にフォーカスして―
<2日目>○大会企画課題別シンポジウム:これからの社協のあり方を問い直す~社協実践を切り口にして~
○大会企画シンポジウム:「地域福祉と包括的支援体制」時代の地域福祉の課題と展望
○開催校企画シンポジウム:地域福祉の推進と多文化共生の取り組み
○優秀実践賞受賞式・報告
○日韓学術交流企画:両国に共通する地域福祉に関するテーマを取り上げ、両国からの報告をもとに、議論を深めていきます。
【詳細・申込】下記URLをご覧ください。
https://www.mwt-mice.com/events/chiikifukushihyogo2025-1
【問合せ先】
○大会運営について 兵庫大会実行委員会事務局(武庫川女子大学) E-mail:jracd2025inhyougo@gmail.com
○大会参加申込等について 名鉄観光サービス株式会社神戸支店(担当/西村、二宮、礒野)
TEL:078-321-5005(平日10:00~17:00) FAX:078-321-5019
E-mail:chiikifukushihyogo@mwt.co.jp
◆令和7年度社協のための「広報のチカラ」講座 ~全国社協広報紙コンクール2024同時開催~
(元社協職員で構成する「全国社協広報紙コンクール実行委員会」)
昨年度に引き続き、社協広報に特化した「令和7年度社協のための『広報のチカラ』講座(全8回)」を開催します。第1回および第2回講座の開催日が決まりましたのでご案内いたします。引き続き申込受付しています。※全国社協広報紙コンクール2024のエントリー受付は終了いたしました。
【名 称】令和7年度社協のための「広報のチカラ」講座
【参加対象】広報担当者等すべての社協職員
【参 加 費】1アカウント6,600円(1アカウント追加4,400円)
※1アカウントで複数名閲覧することはできません
【令和7年度講座開催予定日・内容】いずれも13:30~15:30
第1回 「伝わる」ための広報講座(新任広報担当者に聞いて欲しい内容)(2025年4月24日(木))〔講師〕窄口 真吾氏(株式会社エスフェクト 代表取締役社長)
第2回 受賞広報紙から学ぶレイアウト講座(2025年5月28日(水))〔講師〕窄口 真吾氏(株式会社エスフェクト 代表取締役社長)
第3回 受賞広報紙から学ぶ写真講座(2025年6月予定)
第4回 広報×○○講座(2025年7月予定)
第5回 ホームページ・SNS活用講座(2025年8月予定)
第6回 最優秀賞社協から学ぶ広報紙講座(2025年9月予定)
第7回 優秀賞社協から学ぶ広報紙講座(2025年10月予定)
第8回 TTPT講座(質疑応答中心)(2025年11月予定)
※開催時期・時間は予定です。また、テーマは前後する可能性があります。グループワークも行います。
【開催方法】オンライン(Zoom)※申込者限定でYouTubeにて後日配信します。
【締 切 日】2025年4月10日(木)
【参加申込】専用ホームページより申込みください。
【問合せ先】事務局:Printコーディネーター窄口(さこぐち)
E-mail:shakyokoho@print-for.com TEL:050-3569-0511
◆「地域福祉マンガ大賞」作品集発行のお知らせ(新潟市西区社会福祉協議会)
新潟市西区社会福祉協議会では、マンガで福祉にふれていただくことを目的に、ボランティア、自分らしさ、食をテーマにしたマンガ作品を令和6年7月から10月まで公募しました。全国から63作品の応募があり、下記選考委員による審査の結果、11作品の受賞が決定。このたび、新潟県社協の「県民たすけあい基金助成」を受け、作品集を発行しました。
【掲載作品】○大賞「蒼太と過ごした夏」 作:かくら みのり(熊本県)○ボランティア部門賞「Wonderful days」作:hako(沖縄県)○自分らしさ部門賞「あかりがともるとき」作:グレうさぎ(新潟県)○食部門賞「ひーばあちゃんのご飯」作:千葉 むねむら(茨城県)○特別賞(7作品)「福祉は愛」作:まふぁーる、「キラッッ!! 楽しいのめぐり」作:くと、「焚き火」作:加原 ゆうま、「ホーム」作:OMI、「エリートエンピツ」作:箍為 飛勇、「発達障害のススメ」作:もへこ、「動けばマルく」作:うつろー
【選考委員】石川 兼司氏(日本アニメ・マンガ専門学校 講師)、渡辺 仁介氏(日本アニメ・マンガ専門学校 講師)、 村山 賢氏(NPO法人新潟ねっと 代表)、支え愛戦士アワセロン氏(NPO法人身寄りなし問題研究会 代表)、大学生ボランティア、新潟県社協職員、新潟市社協職員など4名 /計8名
【体 裁】A5判 192ページ【配付について】郵送料をご負担いただければ、全国へお送りいたします。(先着700部)
【詳 細】下記URLをご覧ください。
◆ニッセイ財団「高齢社会を共に生きる-つなげる・支え合う居場所づくりと地域共生社会-」
第37回シンポジウム・第31回ワークショップ記録集無料配布のご案内(公益財団法人日本生命財団(ニッセイ財団))
ニッセイ財団では、活動助成・研究助成の成果を社会に還元する観点から、シンポジウム・ワークショップを毎年開催しております。このたび昨年12月開催分の記録集が完成しました。希望者先着500名様に無料で配布いたします。
【記録集概要】A4版117ページ おひとり3冊まで
送料:申込者負担(1冊284円、 2~3冊344円)
※着払い(日本郵便「ゆうパケット」にて郵送)
【記録集目次(抜粋)】
<第37回シンポジウム「高齢社会を共に生きる」>
○第1部:基調講演
・こども食堂と私たちの地域・社会
〔講師〕湯浅 誠氏(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長)
○第2部:実践報告(地域福祉チャレンジ活動助成成果報告)
・高齢者の社会参加への場づくり:子どもたちと触れ合う地域の再生
穂坂 光彦氏(認定NPO法人パルシック 共同代表理事)
吉浦 諒子氏(認定NPO法人パルシックみんかふぇ 代表)
〔講評〕市川 一宏氏(ルーテル学院大学 名誉教授)
・町民の孤まり事を減らしたい!共生型居場所から始まる重層的支援
大谷 真氏(函南町社会福祉協議会 係長)
〔講評〕宮城 孝氏(法政大学 教授)
・人生の見取りまで含む生活支援「東郷ささえ愛家族」
織田 英嗣氏(NPO法人ノーマCafe 理事長)
〔講評〕大塚 眞理子氏(長野県看護大学 学長・教授)
○第3部:総合討論
・つなげる・支え合う居場所づくりと地域共生社会
〔コーディネーター〕上野谷 加代子氏(同志社大学 名誉教授/日本医療
大学教授)
〔コメンテーター〕白澤 政和氏(国際医療福祉大学大学院 教授)
〔アドバイザー〕湯浅 誠氏
〔シンポジスト〕穂坂 光彦氏、大谷 真氏、織田 英嗣氏
<第31回ワークショップ「高齢社会実践的研究助成成果報告」>
○第1部:若手実践的課題研究助成
・僻地に住む独居高齢者に対する社会的交流促進のアウトリーチ支援
高田 大輔氏(文京学院大学保健医療技術学部 准教授)
・高齢者の孤独感を軽減するVirtual Reality(VR)プログラムの開発
今井 鮎氏(京都府立医科大学大学院医学研究科 精神機能病態学博士課程)
・認知症高齢者の就労支援に関する実践的研究
郭 芳氏(同志社大学社会学部 准教授)
・介護職員の危険予知能力評価尺度の開発と安全管理研修への応用
山鹿 隆義氏(名古屋女子大学医療科学部 准教授)
・太極拳を活用した高齢者の健康増進:科学的検証とプログラム開発
陳 岑氏(九州大学大学院 人間環境学府博士課程)
○第2部:実践的課題研究助成
・DXを用いた高齢者を支える家族関係重視型Advance Care Planning(ACP)
プログラムの開発
鈴木 みずえ氏(浜松医科大学臨床看護学講座 教授)
・「地域共生社会」の実現に向けた社会関係資本の実証的研究
塚本 利幸氏(福井県立大学看護福祉学部 教授)
【記録集申込方法】下記URLより申込方法をご確認ください。
https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/03.html
◆ICTリテラシー向上にかかる教材の積極的な活用について(総務省)
総務省では、これからのデジタル社会において求められるリテラシーを向上するため、公式サイトにおいて各種教材を公開しています。積極的にご活用ください。
1. 5つの分野のICTリテラシーを学ぼう
~つくろう!守ろう!安心できる情報社会~
青少年、保護者、シニアの皆さまを対象に、これからのデジタル社会において必要となるICTリテラシーを身につけるための教材です。本教材では、デジタル空間の特性を理解し、新たな課題にも対処できるよう、最新の事例も用いながら学習することが可能です。
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/Ictliteracy_for_yps/
2. インターネットとの向き合い方
~ニセ・誤情報にだまされないために~第2版
ニセ・誤情報に関する留意点や対策についてまとめた教材です。本教材では、災害時に広まるニセ・誤情報など最新事例や生成AIの影響、民主主義への影響等を踏まえて、ニセ・誤情報について学ぶことが可能です。併せて公表している講師用ガイドラインは、資料に従って講座を進めることで、どなたでも気軽に講座の実施が可能です。
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/
3. 官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」
総務省では、令和7年1月にプラットフォーム事業者等を含む19の事業者・団体と連携して、意識啓発のためのプロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」を立ち上げました。企業・団体のステークホルダーとともに官民で連携した取り組みを進め、さらなるICTリテラシーを向上する取り組みを推進しています。
https://www.soumu.go.jp/dpa/
●「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」トップページ
http://www.zcwvc.net/
●メールニュースのバックナンバーはこちらで見ることができます
https://www.zcwvc.net/member/mailnews/
●メールアドレスの変更、メールニュースの配信停止はこちらへ
https://www.zcwvc.net/member/mailnews/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター
TEL:03-3581-4655/4656
メールニュース(社協版)専用:c-news@shakyo.or.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
次回は2025(令和7)年4月8日(火)に発行予定です。
2. 東京都地域公益活動推進協議会からのニュースです。
本会事業、東京都地域公益活動推進協議会のホームページが、4月1日をもってリニューアルオープンいたしました!
https://clk.nxlk.jp/m/S9yuap7oF
①地域公益活動の事例検索が簡単になりました!
新たにタグ検索機能を追加!これまで以上に情報を探しやすいウェブサイトになりました!
②デザインを一新しました!
たくさんの方に見ていただけれるサイトを目指し、明るくポップなデザインに仕上げています。マスコットキャラクターつつまるも新しいサイトで皆さんを出迎えます!
③実践事例の寄稿が簡単にできるようになりました!
各社会福祉法人の実践事例がホームページ上で投稿が可能に!メールでのやり取りが不要になり、スムーズにご寄稿ができます!
新しくパワーアップしたウェブサイトへ、ぜひアクセスして下さい!
※一部リニューアル作業中のページがございます。予めご了承ください。
=====================
<東京都地域公益活動推進協議会 事務局>
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
福祉部 経営支援担当(阿部)
3. 全国社会福祉協議会 地域福祉部 全国ボランティア・市民活動振興センターより
3月4日に開催いたしました「市区町村社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターの機能強化に係るオンラインサロン~KICK・OFF~」につきましては、ご要望も多かったことから、オンラインサロンのアーカイブ配信を行うことに致しましたので、当日ご覧いただけなかった方や、ご関心のある方が周囲にいらっしゃいましたら、
下記サイトをご案内くださいませ。
投稿日 25年04月05日[土] 11:16 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,学会,災害支援,社会福祉関連
皆さん、おはようございます/こんにちは/こんばんは。お元気ですか。
さて、2月22日に、ハイブリッドで開催されます21世紀キリスト教社会福祉実践会議大会のご案内をさせて頂きます。
大会では、「誰が隣人になったと思うか?」〜ともに生きる関わりを求めて~をテーマに、以下のプログラムが予定されています。
開会礼拝:上田憲明氏(日本聖公会東京教区司祭)
基調講演1:幸田和生氏(カトリック東京教区名誉補佐司教、一般社団法人カリタス南相馬代表理事、カトリック原町教会司祭)、現在も進行中の原発被害に直面する住民と共に歩む「カリタス南相馬の働き」から学びます。
基調講演2:向谷地生良氏(社会福祉法人浦河べてるの家理事長、北海道医療大学名誉教授)、「他者の苦しみへの責任と連帯」を目指し、精神的障がいをもつ方々と共にある浦河べてるの働きから学びます。
シンポジウム
・稲松義人氏(社会福祉法人小羊学園理事長)「重度の障害をもつ人と歩む」、意思を判断すること自体が難しい重度の知的障がいをもつ方と共に生きていく日々の実践を学びます。
・下条裕章氏(聖公会神田キリスト教会司祭、きぼうのいえ施設長・理事長)「独居の高齢者の生活を支えるために」、高齢化が進む山谷において、「生」を全うするための宿屋を提供する実践から学びます。
・長縄良樹氏(日本児童育成園統括施設長)「一人ひとりの子どもの成長と可能性を支えて」、
子どもの成長を支援して多様なケアを展開する育成園の実践から学びます。
司会者である石川一由紀氏(救世軍本営社会福祉部長)のコメント
「それぞれ切り口は違うが、「歩み寄る」「支える」という実践の中で「隣人」になろうとしてきたことを掘り下げたい」
閉会礼拝 小勝奈保子氏(日本福音ルーテル聖パウロ教会牧師)
閉会の挨拶 大橋愛子氏(さかえ保育園園長)
なお、実践会議は「神は苦しむ人間の姿を見て、見逃さず駆け寄り、寄り添い、その痛みを背負って下さる方であることから、強い共感が生まれる。神と同じように人々の苦しむ姿に共感して駆け寄るならば、神を信じる、信じないにかかわらず、意識するとしないとに関わらず、神と結ばれた共に歩む隣人である」(カトリック司教森一弘先生)という基本的考え方を大切にしてきており、施設職員の研修の場にもなってきました。
是非、ご参加くださいますよう、お願いいたします。
2025年1月21日
21世紀キリスト教社会福祉実践会議代表
ルーテル学院大学 名誉教授 市川一宏
参加の申し込みは、以下のパンフレットをご参照ください。
https://www.dropbox.com/scl/fi/vyhs4knc918qgsirvqcwh/12-202410.10.pdf?rlkey=r2k87ip9600ozn1r8503dxl33&dl=0
投稿日 25年01月23日[木] 12:01 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,教会関連,災害支援,社会福祉関連
全社協の元事務局長であり、地域福祉学会の元副会長として全国の地域福祉の推進に大きく貢献され、またルーテル学院大学の現名誉教授として教育等に大きな働きをされた和田先生の本が出版されました。
出版に際しては、大橋謙策先生を中心に、越智和子(琴平社協元常務理事・事務局長)さんと日下直和(香川県社会福祉協議会事務局長)さんのご努力があったことは言うまでもありません。感謝申し上げます。
皆様も、どうぞ手に取って、貴重な地域福祉、社会福祉協議会の歩みをお読み下さい。
投稿日 24年04月04日[木] 10:07 AM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,教会関連,社会福祉関連
市川一宏(いちかわかずひろ) 2023年10月現在
市川一宏
1. 現在 ルーテル学院大学名誉教授
2.学歴
早稲田大学法学部、日本社会事業学校研究科、東洋大学大学院社会学研究科社会福祉専攻博士前期課程・後期課程、ロンドン大学ロンドン・スクール オブ エコノミックス(LSE)特別研究員2002~2004年
3.専門分野:社会福祉政策・地域福祉・高齢者福祉
4.研究テーマ:全国・都道府県・市区町村の行政、社協、民間団体における計画の策定、実施、評価および調査研究、人材養成・研修等に多数関わる。
全国各地の実践から、様々な「地域の福祉力」を学び、各地域に合った地域福祉実践を研究テーマとしてきた。特に近年、地域の福祉力を高め、孤立を防ぎ、「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる一人ひとりの人生が守られる、希望あるまちづくり、共生型社会づくりに挑戦している。
5.学会の活動
日本地域福祉学会監事・元理事、日本社会福祉学会前監事・元理事、キリスト教社会福祉学会前会長
6.最近の主な学外活動
・三鷹市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会委員長・作業委員会委員長・副会長(現在に至る)
・三鷹市介護保険事業計画検討委員会市民会議会長(現在に至る)
・小金井市介護保険運営協議会会長(現在に至る)
・武蔵野市健康福祉総合計画推進会議会長・地域福祉計画策定委員会委員長(2023年3月まで)
・調布市高齢者福祉推進協議会顧問(現在に至る)
・世田谷区共同募金配分委員会委員長、評議員専任・解任委員会委員長(現在に至る)
・練馬区介護保険運営協議会会長(現在に至る)
・東京都社会福祉協議会総合企画委員会委員長、法人評議員(現在に至る)
・東京都つながり創生財団評議員(現在に至る)
・全国社会福祉協議会
全国ボランティア市民活動振興センター運営委員長(現在に至る)
「これからの民生委員・児童委員制度や活動のあり方に関する検討委員会」委員(2018年4月まで)
評議員専任・解任委員会委員長(現在に至る)
民生委員・児童委員研修体系検討委員長(2014年3月まで)
「単位民児協運営ハンドブック(令和4年3月版)」編集委員会委員長
・ニッセイ財団高齢社会助成審査委員(現在に至る)
・厚生労働省寄り添い型相談支援事業等選定・評価委員会委員(現在に至る)
・『日本の都市総合力評価(JPCI)有識者委員会(Expert Committee)』 委員<社会福祉担当>(森記念財団)(現在に至る)
・東京神学大学監事(現在に至る)
・医療法人財団慈生会野村病院監事(現在に至る)
7.近年の主たる編著書・論文・執筆等
・2014年6月『「おめでとう」で始まり 「ありがとう」で終わる人生 福祉とキリスト教』教文館
・2009年5月『知の福祉力』人間と歴史社 等
・2019 年1 月この人に聞く「ソーシャルワーカーは、専門職である前に一人の人間であれ」聞き手松本すみ子先生、『ふくしと教育』(日本福祉教育・ボランティア学学会機関誌)2019 通巻26 号、p.38〜p.41
・2019 年5 月「はじめに」「第1 章 三鷹市における地域包括ケアシステム構築の現状と課題」「清成忠男先生インタビュー:地域ケアの過去、現在、将来」編集代表・共著『人生100 年時代の地域ケアシステム―三鷹市の地域ケア実践の検証をとおして―』
・2020年3月「解説 民児協運営のポイントと会長としての心構え」p.6・7『VIEW No.214』全国社会福祉協議会民生部
・2020年4月「ボランティアコーディネーターの皆さんへ〜皆さんへのエールと今の私たちにできること」『ボランティア情報』全国社会福祉協議会全国ボランティア・市民活動センター
・2021年4月「コロナ禍における地域ケアを考える」p.4『SAI-4月号』埼玉県社会福祉協議会
・2021年10月「リーダーに求められる役割」p.10〜13、『View221』全国民生委員児童委員連合会
・2021年12月「リーダーに求められる役割(第2回)対談:吉川郁夫氏(大阪市民児協会長)」p.10〜13、『View222』
・2022年2月「全国民生委員大会シンポジウム:地域共生社会の実現と民生委員・児童委員活動〜新型コロナウイルス禍を踏まえて考える〜シンポジウムコーディネーター」p.12〜p.17、『ひろば』全国民生委員児童委員連合会、DVD配布
・2022年3月「はじめに」ⅲ〜ⅷ『単位民児協運営の手引き[令和4年3月版』全国民生委員児童委員連合会
・2023年3月「新体制を迎えた単位民児協の運営について」『View227』全国社会福祉協議会民生部
・2023年2月「市川一宏の足跡~ 50 年の歩みをふりかえって~ 退職記念随筆」ルーテル学院研究紀要『テオロギア・ディアコニア』 ルーテル学院大学・日本ルーテル神学校紀要
・2023年3月「新体制を迎えた単位民児協の運営について」『View227』p.2〜7,全国社会福祉協議会民生部
・2023年3月「はじめに」三鷹市地域福祉活動計画Ⅶ(2023〜2026年)
・2023年5月「福祉職が語る:ソーシャルワーカーは、新たな絆をつくり、未来の社会を切り開く」東京都社会福祉協議会『福祉情報』
・2023年6月「巻頭言 信州の実践者・開拓者の思いを紡ぐ」『実践者・開拓者であれ!信州の地域福祉の歩み』長野県社会福祉協議会・信州の地域福祉研究会
・2023年6月NHK ハートネットTV「フクチッチ」「社会福祉協議会」(HPで記事になりました。
https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/849/ <https://www.nhk.or.jp/heart-net/article/849/>
投稿日 23年10月16日[月] 3:42 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,共助社会づくり,大学関連,学会,社会福祉関連
日本キリスト教社会福祉学会第60回大会(2019年6月28日、聖隷クリストファー大学)で、シンポジウムのシンポジストのご依頼を頂きました。テーマは、「神と隣人に仕えるー地域共生社会形成におけるキリスト教社会福祉の役割」です。シンポジストは、村上恵理也氏(日本キリスト教団松戸教会牧師)、野原健治氏(興望館館長)、市川、コーディネーターは柴田謙治氏(金城学院大学教授)でした。すでに1ヶ月を過ぎましたが、私がお伝えしたかったことをまとめました。
私は、50年近く、キリスト教社会福祉の実践から多くを学んできました。それは、私自身の生き方に影響を与えていました。特に、私は先人の実践から信仰の意味を学び、今を生きる使命としてきました。しかし、この数年、いくつもの経験を通して、私のキリスト教社会福祉の実践に対する考えが変化していることに気がつきました。
1.「隣人に仕える」キリスト教社会福祉の取り組み
⑴共感から生まれる活動
「あなたがたの中に、百匹の羊を持っている人がいて、その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を野原に残して、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らないだろうか。そして、見つけたら、喜んでその羊を担(かつ)いで、家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、『見失った羊を見つけたので、一緒に喜んで下さい』と言うであろう。言っておくが、このように、悔い改める一人の罪人については、悔い改める必要のない九十九人の正しい人についてよりも大きな喜びが天にある」(ルカによる福音書第15章第4節から7節)
キリスト教社会福祉を切り開いた先人の方々の思想、信念から、私は神の御言葉を学び、共感しました。また先人が目指した明日に向かって、たくさんの方々が足並みを合わせ、歩んでこられたことを知っています。その証が、現在まで引き継がれてきた実践そのものです。
私は、一匹を救う取り組みが、私の使命であると考えてきました。そう考えるもう一つの根拠は、「わたしの兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、わたしにしてくれたことなのである。」(マタイによる福音書25章40節)との聖句です。私が訪問した多くのキリスト教主義施設には、この聖句が掲げられていました。
しかし、自分に予想していなかった病いが発見され、少し辛い治療を始め、「生きるために食事をする」等を体験してから、私自身が「一匹の羊」「いと小さき者」であることを実感しています。そして、私の生きることへのこだわりは、隣人が自分らしく生きてほしいという気持ちを強めています。相手に対する畏敬や共感は、自分自身を知ることから始まりました。
また、2011年3月の発災後から続けている東日本大震災の被害がもっとも大きかった石巻市の支援を通して、一人の人間の非力さを痛感しながらも、多くの人たちが絆を形成し希望を生み出している現実を見て、共に生きる意味を知りました。震災以来、今も石巻に通わせて頂いています。
そして、そもそも、今日の家族の扶養機能・養育機能、地域の相互扶助機能、企業内扶助機能の脆弱化により、誰もが閉じこもり、孤立死の危険があります。また引きこもりの推計が数十万となっている状況で、私たち自身が一匹の羊であると思います。だから、一人の人間としての共感が自然に湧き上がってくるのだと思っています。
その事実を理解できたことを思いますと、この間の経験は、神様からの贈り物だと確信しています。
⑵隣人愛の実践
隣人愛という言葉は、クリスチャンに限らず、今の社会にとって、かけがえのないミッションであると思います。
例えば、民生委員信条には、「わたくしたちは、隣人愛をもって、社会福祉の増進に努めます」と書かれています。また、手話では、ボランティアを、「苦労を献げる」という意味ではなく、両手の人差し指を合わせ、人差し指と中指で歩く表現します。すなわち、「共に歩む」と意味を表します。 そして、生活困窮者自立支援制度は、援助の原則として、「生活困窮者が社会とのつながりを実感しなければ主体的な参加に向かうことは難しい。『支える、支えられる』という一方的な関係ではなく、『相互に支え合う』地域を構築します。これらは、奉仕の概念の変化ではないでしょうか。
また、私が委員長をさせて頂いている東京都共助社会検討委員会では、共助の原則の一つをdiversity(多様性)とinclusion(共生)にしました。ずなわち、それぞれの生活文化、生き方、思想、信条、信仰等の多様性を認め合い、そして互いに支え合いながら生きていくことの大切さを掲げました。隣人愛に立つ歩みを求めた神を信じるか、信じないかに関わらず、神を知っているか知らないかは関係なく、倒れている人を助けようとする人は、キリストにある隣人だと考えています。
2.キリスト教社会福祉としての地域社会との関わり
⑴住民との関わりによる成長
社会福祉法第4条には、「地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者(以下「地域住民等」という。)は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。」と規定されています。命を与えられてから、人生の最後に至るまで、一人の人間として生きていくことを支援する実践が地域福祉であると示しています。
ふりかえって、キリスト教社会福祉を実践してきた団体は、その置かれた場で希望の光を灯しました。地域住民は、その光を見ながら、生きておられたと思っています。そして、今、同団体は、地域という場所で、当事者、住民と共に生きていくこと、互いに補い合っていくことが求められていると思います。そして、それは互いに学び合うことでもあります。
⑵「我がごと、丸ごと」を目指した地域共生社会の展開をどのように考えるか
「我がごと」とは、地域住民等も地域の生活課題を自分のことと認識し、協働してその問題の解決に取り組みこと。「丸ごと」とは、障害者、児童、高齢者と分かれていた施策を束ねて、地域問題に対応するサービス供給組織に再編しようとすることです。
この考え方は、すでに施策のいたるところで実施されています。私は、介護保険における介護予防・総合事業、社会的養護における地域支援、生活困窮支援制度における地域社会づくり等の施策の動向から、インフォーマルケアである見守りやサロン等の住民活動、当事者活動が、施策に位置づけられ、自助、共助、公助を合わせた地域ケア体制が求められていると考えています。すなわち、地域福祉の制度化です。
確かに、国の責任を放棄しているとの指摘もあります。しかし、各自治体、地域状況は多様です。そしてそれぞれの地域で、孤立や虐待が顕在化している現実がある。地域の問題を行政だけでは対応できない。地域共生社会づくりは、身近な住民やボランティア、社会福祉法人、NPO法人等の幅広い資源が最大限協働して、「問題が発生する地域を予防、解決の場とする」従来のコミュニティケアの実現と共通しています。但し、従来の施策と違う視点は、それらの活動を支援する自治体の役割が強化されたことです。
⑶原点に戻る
ちなみに、社会福祉法人改革の現状分析は首肯できませんが、組織の透明性等の強化、公益事業の義務化に関しては、一つの機会ととらえています。また、地域ケア会議等の連携の中で、各キリスト教社会福祉を実践する団体はどのような姿勢をとるか。または地域社会における役割を明確にしていく必要があります。
すなわち、隣人愛に基づいて創設され、今日も至る団体のミッションが、組織を構成する関係者にどのように共有化され、日々の仕事にどのように活かされているのか、本物のキリスト教社会福祉実践なのかどうかが問われていると思います。
3.キリスト教・教会とキリスト教社会福祉実践との関わり
⑴基本的考え方
教会から発せられる言葉である隣人愛の実践が、キリスト教社会福祉実践であり、教会の地域への玄関が、幼稚園・保育園を含む社会福祉施設、地域活動であるとも考えています。ですので、以下に述べるキリスト教と社会福祉実践を結び合わせる5つのCの座標軸が大切だと考えています。すなわち、共感(Compassion)、連帯(Collaboration)、当事者の様々な能力の向上(Capacity building)を横軸に、キリストの教え(Christ)を縦軸にする十字の座標軸です。
悲しみや痛みを感じ、喜びや感動する心を抱き、自分らしく生きたいと葛藤し、人間としての誇りを生きる糧とし、安心する心の拠り所を求めさまよう、そうした人生を一歩一歩積み重ねて生き抜いてきた利用者の「生きる」姿に共感すること。これは、同じように生きてきた自分自身を理解することから始まります。
「隣人」とは、生きる意味を共に考えてくれる同伴者です。日本聖公会神学院校長関正勝先生は、「弱さを担うことが真実の人間の強さだ」と言われました。すなわち、叫びをあげている人々から求められることに、ひたすら応え続け、同伴者として歩むこと。それは、利用者の存在を支える働きであり、互いが生きる意味を教えあい、共に考える空間であり、意味のある人生を互いに築いていく過程ではないでしょうか。そこには、明らかに、生きる意味を共に考えていく「隣人」としての関わりが生まれています。
例えば、地域ケア会議等の連携の中で、各キリスト教社会福祉を実践する団体はどのような役割を果たすのか、地域社会における使命は何か、明確にしていく必要があります。隣人愛は、キリスト教社会福祉団体の専売特許ではありません。
また、当事者本人と連帯し、その人の存在を認めているか、それぞれの方の生きる姿を受けとめているのか、隣人愛の実践がなされているのかという問いを実際の仕事で確認していくことが大切だと思っています。
- 当事者の様々な能力の向上(Capacity building)
「孤児の父」と言われた石井十次は、明治後期に密室主義(個人的な話し合いによる教育)、旅行主義(見聞を広めるように努力すること)、米洗主義(米をとぐようにそれぞれの特質を現させる)等の岡山孤児院12則を明らかにしました。また知的障害児の父と言われた糸賀一雄氏は、昭和20年代から療育を通して、発達保障というミッションを掲げました。当事者の生きようとする力、他者を理解しようとする力、潜在的な自立能力を一緒に発見し、維持し、強化のための挑戦をすることが求められています。
- 運営方針の明確化と組織強化(Check and evaluation)
ちなみに、社会福祉法人改革の現状分析は首肯できませんが、組織の透明性等の強化、公益事業の義務化に関しては、一つの機会ととらえています。
組織内だけでしか通用しない常識は、それを非常識と言います。そして、キリスト教社会福祉を実践する団体が、社会から求められている存在であるのかと確認し続けて頂きたい。
また、事業、活動等の具体的な支援が、手続、計画、内容において適正なものか、評価基準を明確にした上で、たえず見直していくことが求められています。これなくしては、地域からも信頼は得られません。
上記の①から④を横軸に、キリストの教え(Christ)すなわちキリストが私たちのために十字架につけられ、自らの命を捧げて下さったこと、そして復活なさり
キリストへの信仰を縦軸にする十字の座標軸がキリスト教社会福祉実践だと考えています。
⑵特に意識して頂きたいこと
今日の社会福祉の現場は、明らかに自立の概念、当事者主体、継続的支援の強化を図っています。
①自立の概念の変化
そもそも自立とは、能力に応じたものであり、障害には支援、能力は活用という基本的考え方が大切です。また、自立の目標は就労による経済的自立か、生活能力(ADL+生活機能障害(2001年ICF)への転換、生活のしづらさ、困難さの発見と支援の必要性)、経済的自立、地域生活における自立、社会関係的・人間関係的自立、文化的自立、身体的・健康問題と自立等、多様な自立が求められています。
②当事者主体
身体障害をもつ方、知的障害をもつ方の社会参加は課題がありつつも、一定の実績はありますが、近年は特に、精神障害をもつ方の社会参加、自己実現を目指す活動が注目されています。浦河べてるの向谷地氏は、当事者研究を示し、当事者自身の取り組みを前面に掲げています。初期の認知症を持っている方々が当事者として社会参加していく可能性を模索する実践もそうです。このような実践が、全国に広がっています。
③継続的支援の強調
さらに、継続的な支援を考えていかないと、多くの当事者は孤立するのではないでしょうか。例えば、一定の年齢になり、児童養護施設を卒園した青年が、突然社会での自立を求められることには無理があります。人生のそれぞれの歩みの過程で、一緒に歩む人、活動、組織があることは、不可欠です。限定されていたサービス、制度を結び合わせるシステムを創り出していくことが求められています。
さて、今日は、浜松駅から聖クリストファー大学まで、バスで来ました。その道すがら、案内の方が立っておられました。不案内の私にとって、本当に心強かったです。その案内に従い、今、私はここに居ます。私は、教会が、キリスト教社会福祉実践に携わる私たちが、迷う人、地域福祉活動の歩みの『道しるべ』、暗い夜空を吹き抜け、社会を照らす『光』になっていく夢の実現を目指したいと思っています。
投稿日 19年07月21日[日] 3:50 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,学会,教会関連,社会福祉関連
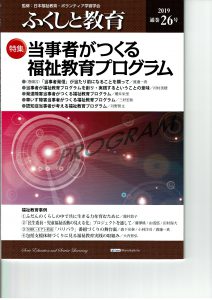
日本福祉教育・ボランティア学習学会機関誌である『ふくしと教育』2019通巻26号において、松本すみ子先生のインタビューを受け、「この人に聞く<ソーシャルワーカーは、専門職である前に一人の人間であれ>」として掲載された。
本書には、実践と研究の成果がまとめられており、様々な実践と施策の情報が良く理解できる。地域福祉、ボランティア活動支援、福祉教育の実践者には、是非、購読をお勧めする。
なお、松本すみ子先生にインタビューをして頂いたことは、光栄である。松本先生にはルーテル学院大学大学院博士後期課程で指導する機会が与えられ、私の考えや実践をよく理解して下さる方のお一人である。
これも、2019年度で教歴36年目を迎える私に与えて下さった、皆さんからのご褒美かもしれない。
この人に聞く⑴ この人に聞く⑵
投稿日 19年02月11日[月] 2:36 PM | カテゴリー: 共助社会づくり,学会
12月21日午前8時半より9時、28日午後6時半より7時(再放送)の『宗教の時間』で、「福祉と信仰の現場から」という私へのインタビュー番組が放送されました。聞き手は、上野重喜氏で、番組として、以下のように紹介して下さいました。
「知的障害児について「この子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」と説いた糸賀一雄に感動し、福祉と信仰の道に入った市川さん。個々を尊重する福祉への願いを説く」
その後、全国にいる私の友人、卒業生より、たくさんの励ましのメールが届き、また家族より、ラジオで話す際の厳しいアドバイスもあり、社会福祉の源流についてより深く学んでいく動機付けにもなりました。ありがとうございました。
投稿日 14年12月28日[日] 6:29 PM | カテゴリー: 大学関連,学会,教会関連,社会福祉関連
2014年6月
日本キリスト教社会福祉学会第55回大会・21世紀キリスト教社会福祉実践会議第9回大会 合同開催のご案内
21世紀キリスト教社会福祉実践会議 代表 幸田和生・日本キリスト教社会福祉学会 会長 市川一宏
日本キリスト教社会福祉学会と21世紀キリスト教社会福祉実践会議が、下記のとおり合同開催することとなりました。
東日本大震災から3年、震災で生じた複合的な問題は決して解決しておらず、本当の問題はこれからさらに顕在化すると思われます。被災された方たちの心の傷が癒えることは容易ではありません。しかし苦しみや傷を抱えながらも、日々を暮らし、一歩ずつ踏み出し始めている方たちの姿から学びたいと思います。また「震災について共に考える」とはどういうことなのか、被災された方々の苦しみの背景にはどのような日本社会の問題があるのかも、問い直したいと考えています。
◆日本キリスト教社会福祉学会第55回大会
「今日におけるキリスト教社会福祉の役割-希望の光が見える新たな社会づくり(3)-」
日時 2014年6月20日(金)10:00~20:00
会場 宮城学院女子大学
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1
TEL 022-279-1311(代表)
主催 日本キリスト教社会福祉学会
プログラム詳細
9:00~ 大会受付
総合司会:田中治和氏(東北福祉大学)
10:00~ 開会礼拝
司式・奨励 新免 貢牧師(宮城学院女子大学チャプレン)
10:40~ 開会挨拶
学会会長 市川一宏氏

松永俊文先生撮影
10:50~ 基調講演
テーマ「震災を生きる―人として医師として―」
石木幹人氏(岩手県立高田病院 前院長)
12:00~ 記念撮影(場所:講堂前)
12:15~ 昼食
13:00~ シンポジウム(会場:講堂)
テーマ
「被災地支援とキリスト教社会福祉」
シンポジスト
佐藤恵子氏(仙台いのちの電話 研修担当)
佐藤彰氏(福島第一聖書バプテスト教会 牧師)
深堀崇氏(カリタス大船渡ベース 事務局長)
コーディネーター
都築光一氏(東北福祉大学)
15:00~ コーヒーブレイク
15:30~ 研究発表・実践報告分科会
(1)歴史・思想
(2)高齢者・児童
(3)障がい者・マイノリティ
(4)実践報告(被災地支援等を含む)
17:15~ 総会
18:15~ 懇親会(会場:学生食堂ピエリス)
◆21世紀キリスト教社会福祉実践会議第9回大会
「震災によってあらわになった人間の苦悩に向き合う」
日時 2014年6月21日(土)10:00~16:00
会場 カトリック元寺小路教会
〒981-8557 宮城県仙台市青葉区本町1-2-12
TEL 022-222-5507
参加費 大会参加費:2,000円(学生 1,000円)
主催 21世紀キリスト教社会福祉実践会議
プログラム詳細
10:00~10:40 開会礼拝
カトリック仙台教区長・司教・平賀徹夫氏
10:40~11:00 開会挨拶
本会議代表・東京教区補佐司教・幸田和生氏
11:00~12:00 基調講演
同元代表・日本キリスト教社会福祉学会名誉会長・阿部志郎氏
13:00~15:00 パネルディスカッション
~震災によってあらわになった人間の苦悩に向き合う~
パネリスト
川谷保育園 園長 柴田彰氏
児童養護施設 青葉学園 園長 神戸信行氏
社会福祉法人カナンの園 法人事務局長 佐藤真名氏
コーディネーター
立教大学名誉教授・関正勝氏
15:00~15:40 分かち合い
カリタスジャパン秘書・宮永耕氏
15:40~16:00 閉会礼拝
救世軍医療部長・吉田眞氏


日本キリスト教社会福祉学会第55回大会
21世紀キリスト教社会福祉実践会議第9回大会
合同開催趣意書
2011年3月11日の東日本大震災から3年を迎え、東日本大震災について日本全体では関心が薄れつつあることが危惧される今、以下のような現実を忘れてはいけないと私たちは思っています。震災の直後には多くのボランティアが駆け付け、貴重な働きをしましたが、その後撤退もみられています。しかし、東日本大震災で生じた複合的な問題は決して解決しておらず、復興住宅に入れる人と入れない人の存在、中折れ現象、隠していた心の傷の現れ、要介護・要支援高齢者の増加、虐待問題の顕在化、将来を見通せない失望感など、本当の問題はこれからさらに顕在化すると思われます。
そこで、日本キリスト教社会福祉学会が主催する1日目(6月20日<金曜日>)は、被災された方々の心の痛みに耳を傾ける相談活動や、被災地の方々による自主的・主体的なつながりづくり、そして被災した教会の再建などの働きを知ることを通して、被災地におけるキリスト教社会福祉実践の労苦の現実を学び、そこでのソーシャルワークはどうあるべきか考えます。登壇者の中には、ご自身も被災され、被災者としての苦悩を抱えつつ、支援活動に従事された方もいらっしゃいます。本大会では、「被災者から学ぶ」という視点を大切にし、「被災者と支援者」という関係についても考えていきたいと思っています。
一方、21世紀キリスト教社会福祉実践会議では、今まで、福祉系学会・団体から、まちづくりや日常のケア、保健医療福祉等の連携についての提言がおこなわれていますが、人生を歩むうえで何かを失った人の絶望や孤独感、怒りなどに向かい合う実践も大切にしてきました。実践会議が主催する2日目(6月21日<土曜日>)には、キリスト教社会福祉のなかでも「キリスト教」の視点から、被災された方々の痛みや悩み、祈り、想いの理解に焦点を当て、それを起点とし、共に歩んでいくことを目指したいと思っています。
今回、学会と実践会議を仙台の地で連続・連携して開催できることは、キリスト教信仰を土台にした研究と実践が被災地で地道に行われてきたことの証しでもあり、とても意義深いことと考えています。
被災された方たちの心の傷が癒えることは容易ではありません。しかし苦しみや傷を抱えながらも、日々を暮らし、一歩ずつ踏み出し始めている方たちの姿から学びたいと思います。また「震災について共に考える」とはどういうことなのか、被災された方々の苦しみの背景にはどのような日本社会の問題があるのかも、問い直したいと考えています。
2013年12月24日
21世紀キリスト教社会福祉実践会議大会実行委員会
日本キリスト教社会福祉学会大会実行委員会
たくさんの方々のご支援とお働き、そして祈りによって、大会が盛況の中で終わることができましたこと、心より感謝します。今、新たな歩みが始められたと、確信しております。

カトリック新聞より
投稿日 14年07月10日[木] 4:00 PM | カテゴリー: 学会
市川一宏(いちかわかずひろ)
1.ルーテル学院大学・人間総合学部社会福祉学科・大学院人間福祉学研究科社会福祉学専攻
2.学事顧問・教授
3.略歴
早稲田大学法学部、日本社会事業学校研究科、東洋大学大学院社会学研究科社会福祉専攻博士前期課程・後期課程、ロンドン大学ロンドン・スクール オブ エコノミックス(LSE)特別研究員2002~2004年
4.専門分野:社会福祉制度政策・地域福祉・高齢者福祉
5.研究テーマ:地域の福祉力を高め、孤立を防ぎ、「おめでとう」で始まり、「ありがとう」で終わる一人ひとりの人生が守られる地域社会の創造をめざす。
全国・都道府県・市区町村の行政、社協、民間団体における計画の策定、実施、評価および調査研究、人材養成・研修等に多数関わる。
6.学会等の活動
日本キリスト教社会福祉学会会長、日本社会福祉士養成校協会相談役、日本精神保健福祉士養成校協会理事(2013年5月まで)、日本社会福祉学会役員(未定)、地域福祉学会理事、日本学術会議連携会員・社会学委員会福祉系大学院あり方委員会委員、福祉系大学経営者協議会監事、21世紀キリスト教社会福祉実践会議委員、認定社会福祉士認証・認定機構運営委員・研修認証委員会委員長、三鷹ネットワーク大学副理事長、
7.最近の主な学外活動
・家庭裁判所調査官補採用Ⅰ種試験第一次試験専門試験(記述式)問題作成者
・国際基督教大学非常勤講師「社会福祉学」
・石巻市社協地域福祉活動計画作業部会アドバイザー(2013年3月まで)『石巻市地域福祉活動計画』
・三鷹市健康福祉審議会副会長(2013年7月まで)、三鷹市社会福祉協議会副会長
・小金井市介護保険・高齢者保健福祉総合事業計画策定委員会委員長(2012年9月まで)
・小金井市社会福祉協議会地域福祉活動計画作成アドバイザー『小金井市地域福祉活動計画』
・武蔵野市健康福祉総合計画策定委員会委員長、地域福祉計画部会部会長
・西東京市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定委員会委員長
・調布市高齢者福祉推進協議会顧問
・ほほえみサポートちよだ:ちよだ福祉サービス利用援助センター運営委員会委員長
・世田谷区「地域支えあい活動助成事業」審査委員長(2012年10月まで)・世田谷区共同募金配分委員会委員長、世田谷区社会福祉協議会地域福祉活動計画策定アドバイザー
・練馬区地域福祉パワーアップカレッジ学長、介護保険事業計画策定委員長
・長野市社会福祉協議会地域福祉活動計画評価委員会委員長(2013年3月まで)
・長野県小地域における地域支え合い体制づくり研究委員会委員長(2013年3月まで)
・宮崎県社会福祉協議会第4次計画策定委員会アドバイザー『第4次宮崎県社会福祉協議会経営基盤強化推進計画』
・東京都社会福祉協議会総合企画委員会委員長、理事
・東京都高齢者保健福祉計画策定委員会委員長(2013年3月まで)
・神奈川県社会福祉審議会会長、地域福祉推進部会会長、高齢者保健福祉計画評価・推進等委員会委員長
・全国社会福祉協議会中央福祉学院運営委員長、民生委員・児童委員研修体系検討委員長(2013年5月)、
・横浜保護司選考会委員
・地域福祉社会構築研究会(清成忠男会長)委員
8.法人関係役員
・学校法人九州ルーテル学院理事
・学校法人浦和ルーテル学院評議員
・るうてる法人会連合人材養成委員会委員
・公益財団法人愛恵福祉支援財団評議員
・東京老人ホーム理事(2013年7月まで)
・日本聖書協会評議員選定委員会委員(2013年3月まで)
9.主な編著書(2013年度を中心に)
・(単著)2009年5月『知の福祉力』人間と歴史社
(書評:阿部志郎先生「ほんだな」『月刊福祉2009年8月号』全社協p.100、岡本榮一先生「書評」『キリスト教社会福祉学研究第42号』日本キリスト教社会福祉学会p.135—136、『社会福祉セミナー2010年4月〜7月号』NHK出版p.135、福祉新聞2009年)
・2013年3月日本学術会議社会学委員会社会福祉学分科会『災害に対する社会福祉の役割―東日本大震災への対応を含めて』(提言)分担執筆
・2013年4月1日「地域の福祉力」『NHKテキスト社会福祉セミナー(4月→7月)』p.32〜47、NHK出版
・2013年6月監修『信州流まめってぇ読本』長野県社会福祉協議会
・2013年6月『民生委員・児童委員研修のあり方に関する検討委員会報告書』<民生委員・児童委員研修教材>『民生委員・児童委員研修ワークブック』『民生委員・児童委員活動事例集1』
・2013年12月「認知症になっても暮らせるまちづくり」『認知症ケア事例ジャーナル』第6巻第3号、日本認知症ケア学会
・2014年3月第3章2節「市民型アソシエーションと地域型コミュニティ組織」p.73〜89、第5章4節「地域福祉サービスの経営」p.139〜144、終章「地域福祉の新たな地平」p.297〜311、(共編著)『地域福祉の理論と方法』(第2版)ミネルヴァ書房、
・原稿提出: 第9章「個別福祉計画の種類と特徴」、「あとがき」、(共編著)『福祉行財政と福祉計画』ミネルヴァ書房
・原稿提出:巻頭言「希望のある明日を築くスタートライン」、第11章「安定成長期・福祉改革期のキリスト教社会福祉」(高山直樹氏と共著)、第13章「日本におけるキリスト教社会福祉関係団体の歩み」(谷川修氏、山本誠氏と共著)、日本キリスト教社会福祉学会編『日本キリスト教社会福祉史』ミネルヴァ書房、
・原稿提出:「社会福祉教育団体と専門職養成」「日本学術会議等の資格制度の提言」、(共編著)『社会福祉事典』丸善
10.講演・新聞記事・講演記録等
・2013年4月12日『山梨新報』「明日の社会を築く〜地域の絆をつくるボランティア活動」(甲府市講演会)
・2013年5月唐津放送<特集番組>「みんなが地域の主役〜今、私たちができるボランティアとは?」(唐津市ボランティアの集い「講演」)
・2013年6月第54回キリスト教社会福祉学会全国大会シンポジウム「今日におけるキリスト教社会福祉の役割―希望の光が見える新たな社会づくり(2)―」シンポジスト 幸田和生氏(日本カトリック司教協議会・カリタスジャパン担当司教)・藤野興一氏(社会福祉法人鳥取こども学園 常務理事・園長、日本キリスト教児童福祉連盟 理事長)・司会市川一宏
・2013年7月(東京・福岡会場)社会福祉協議会活動全国会議「てい談 生活支援活動を通じて社会福祉協議会がめざすもの」『ノーマ』8月号・9月号、全社協地域福祉部
・2013年7月社協会長会議・事務局長会議「地域の生活支援と社協活動を考える」『ひょうごの福祉 NOW』9月号
・2013年10月(千葉)全国民生委員児童委員全国大会報告書(特別集会)「東日本大震災被災地における民生委員・児童委員活動〜被災地と全国との絆による被災地支援の強化に向けて〜」
・2013年11月(高知)第22回全国ボランティアフェスティバル報告書「ふれあい・いきいきサロン全国研究交流会基調講演・コーディネーター<明日へ繋げよう地域の絆〜輪・和・話>」
・2014年2月2日『三陸河北新報社』「支え合って地域再生 石巻で福祉フォーラム 具体的活動へヒント学ぶ」
聖望学園入学式挨拶、長野県民生委員・児童委員研修会、長野県介護支援専門員更新研修・中堅研修、特別区職員研修「高齢者福祉」、長野県地域福祉コーディネーター研修、家裁調査官授業「社会福祉」、全国市町村社会福祉協議会管理職研修基調講演、神奈川県地域福祉コーディネーター研修講義、鹿児島市民生児童委員大会講演、賛育会全体研修会講演、中四国都市社協研修会講演・シンポジウム、永信会創立40周年記念会講演、諏訪ブロック社協研修会講演、石川県社協トップセミナー講演、石川県社会福祉大会講演、民生委員リーダー研修講義、宮城学院大学研修会、自治大学校講義「地域福祉」、島根県地域福祉学会プレ大会講演、熊本県地域福祉フォーラム、広島市地区社協リーダー研修、浜松市社協、静岡市社協、島根県民生児童委員会長研修、浦和ルーテル学院コメスメント、栄光教会、掛川・菊川教会、挙母教会、牛久教会
2010年度は、以下の県で講演をさせていただきました。その場が被災地になったことに、深い悲しみを覚えます。私は、ご指導いただいた多くの方々の思いを心に灯し、今、命ある被災地の方々と末永く、一緒に歩むことであると思っています。
青森県三戸郡60周年記念大会「これからの地域福祉と社会福祉協議会の使命」、宮城県市町村社協会長・事務局長会議「市町村社会福祉協議会に求められる地域福祉活動について」、福島県生涯研修講師スキルアップ研修~福祉を取り巻く環境と福祉人材養成の意義~」、山形県市町村社協トップセミナー「市町村社会福祉協議会に求められる地域福祉活動について」、茨城県社会福祉法人指導的職員研修「福祉を担う人材とは?〜専門性・人材確保・育成等を考える〜」
11.今までの共編著
『社会福祉と聖書』(共編著)リトン、『社会福祉論』(共著)ミネルヴァ書房、『老人福祉論』(共著)ミネルヴァ書房、『地域福祉論』(共編著)ミネルヴァ書房、『社会福祉協議会論』(共編著)全国社会福祉協議会、『高齢者施設の個室ケアマニュアル』(共編著)中央法規、『地域福祉論』(共著)中央法規、『ボランティアコーディネータースキルアップシリーズ』(監修・共著)全国社会福祉協議会、『生きるー生きる<今>を支える医療と福祉』(共編著)人間と歴史社、るうてる法人会連合『共拓型社会の創造をめざしてー未来を愛する 希望を生きるー』人間と歴史社、『キリストの愛を伝え、共に成長するー未来を愛する 希望を生きるー』(共編著)リトン、『はじめて地域福祉の担当になった方のために』(共著)神奈川県
投稿日 14年03月30日[日] 12:09 PM | カテゴリー: 大学関連,学会,社会福祉関連
日本キリスト教社会福祉学会会長阿部志郎先生は、この3年間を、学会全体で、学びを蓄える時としてとらえ、「神学と社会福祉学からみるキリスト教社会福祉」研究の重要性を説かれた。阿部会長の方針に則り、関東地区、中部地区、近畿・中国地区、九州地区のブロックごとに研究会が立ち上げられ、個別の研究が進められた。
- 関東地区:
- 「福祉理解と教会理解」(森一弘先生)
- 「今日における人間理解と教会」(大宮溥先生)
- 公開シンポジウム 「キリスト教人間理解」*原稿
- 「ディアコニアの一つの視点」(江藤直純先生)
- 「人間の尊厳を発見・支える仕事ーディアコニア」(関正勝先生)
- 「ヘンリ・ナウエンの福祉思想ースピリチュアリティと<創造的弱さ>をめぐって」(木原活信先生)
- 「弱さの神学」(米田綾子先生)
- 「マタイ福音書の山上の説教ー平和へのメッセージとして」(森一弘先生)
- 中部地区:
- 「今まで私が行ってきたディアコニア研究の動向と課題」(坂本道子先生)
- 「NPOのマネジメント–<止揚学園>の事例から」(大沢先生)
- 近畿・中国地区:
- 「ディアコニアの現代的展開」(石居正己先生)
- 「外国籍住民と共に生きる社会」(M.メンセンディーク先生)
- 「ディアコニー関係ドイツ語圏文献解題」(畑祐喜先生)
- 「キリスト教社会福祉の意義とその使命」(シンポジウム)
- 「カトリック社会福祉の歴史的変遷」(田代菊雄先生)
- 九州地区:
- 「キリスト教社会福祉–ディアコニーの源流」(山城順先生)
- 「ディアコニアの思想の一考察」(門脇聖子先生)
また、それらの研究成果をとりまとめるべく、以下のシンポジウムが開催された。
- 「人間理解」2003年3月・ルーテル学院大学<研究会シンポジウム>
- 「いのち こころ 生活–キリスト教社会福祉実践に生きる」2004年3月・救世 軍本営<21世紀キリスト教社会福祉実践会議第4回大会>
- 「キリスト教社会福祉の存在意義とその使命」2003年11月・キリスト教ミード 宮原センター<学会2研究会共催シンポジウム>
- 「キリスト教社会福祉の使命–神学と社会福祉の対話」2004年7月・中部学院大 学<本学会全国大会>)
が開かれた。
研究会の基本的考え方を、私は以下のように考えている。
- Whom キリスト教人間理解(研究会)2003年3月公開シンポ
- Why 使命・目標・考え方(研究会)2003年7月、04年6月 学会シンポ
- When 歴史研究 2004年6月 学会自由報告(研究依頼)
- Who What Where 実践(21世紀キリスト教社会福祉実践会議)04年3月
*可能ならば、実践会議における討議内容も含め、出版を目指す
<第1回研究会において提示された今後の研究課題>
- 社会福祉に関する現状認識
- 社会福祉を取り巻く環境の変化
- 少子高齢化による高齢社会へ
- 家族機能の低下
- 介護や養育等のニーズの広範化
- 精神的不安・孤独、孤立への対応の必要性
- 虐待、精神障害、痴呆、自殺等の問題の顕在化
- ホームレスや在日外国人を排除する現状
- 社会福祉の質的転換
- 新しい公共性(行政・民間の限界と可能性→パートナーシップ)
- ソーシャルインクルージョン(共生の社会づくり)と社会福祉の普遍化=閉ざされた福祉を開く
- 行政依存から対等のパートナーシップ=防衛的福祉から開発的・先駆的福祉へ=ボランティアリズム
- サービス中心から利用者中心への変化=利用者の選択、満足度重視
- 福祉六法による縦割り福祉→市民・住民、地域という視点による再統合
- 新しい文化の創造=まとづくり、参加型社会づくり
- 地方分権と地域間格差、小地域における助け合いの重視
- キリスト教社会福祉を研究する視点
- 教会と社会福祉
- 福祉国家=生活保障=公共性→教会の働きとしての福祉事業からの撤退はなかったか?
- 1961年にニューデリーで開かれたWCCで登場した「ソーシャルディアコニア」の考え方が、政治に特化し、それ以降、社会福祉の働きが見逃されてきたことはなかったか?
- 社会福祉の一般化、社会化によって、敢えて宗教色すべてが薄められてきたことは、正しかったか?
またそのことをもって、社会福祉の働きが世俗化したと言うべきであろうか?
- 社会福祉事業を生み出し、支えたのは、教会自体か、一部の教会員か、宣教師個人か?
- 神の国の福音を述べ伝えることと、福祉事業・実践を神学的に整理する視点は?
- キリスト教社会福祉研究の過去と現在
- クリスチャンワーカーが取り組むべき使命を明確にしてきたか?
- ワーカーが拠るべき視点を明確にし、その働きに貢献してきたか?
- 社会福祉=国家概念にとどまり、神学的ビジョンを提示してきたか?
- そもそもキリスト教社会福祉学会の存在意義は何か?
- 今日の多様なニーズに対して、どのような理論構成をしているか?
- 働く者に対する社会的地位の向上に貢献してきたか?
- アジアという文化の中で、スピリチュアルの意味は?
- 神学がキリスト教社会福祉と関わる際の、信仰告白の意味をどのように位置付けるか?
- クリスチャンとノンクリスチャンの壁を高くすべきではない。その際の協働について、十分議論してきたか?
- 研究課題
- 人間理解「いと小さき者」=「人間の弱さ」
- 一人=ペルソナの重視
- 一人と一人の関係性の重視
- 連帯する個人=コルプス
- 働く人々の社会的地位
- 専門職の意味
- 市民として参加し、コミュニティを築いていくことの意味=ボランティアリズム
- エキュメニズムの理解
- 施設主義から在宅主義へ移行する中で、教会の役割
- 福祉文化の形成とキリスト教社会福祉の役割
- 今を確認し、将来を展望する視点の模索
- 各教派の社会福祉施設・機関に対する関わりの実証的検証
以上を検証することによって、「地の塩 世の光」としてのキリスト教社会福祉の本質に迫りたい。
ちなみに、2004年日本キリスト教社会福祉学会全国大会において、「キリスト教社会福祉の使命ー神学と社会福祉の対話」をテーマに、市川がコーディネーターの役割を与えられた。各シンポジストのレジメを紹介したい。
北村 次一氏(関西学院大学)
- 最初の社会福祉家イエスに聴く
「神学と社会福祉の対話」を具現しユダヤ世界に
投稿日 06年04月25日[火] 4:11 PM | カテゴリー: 学会
次のページ »