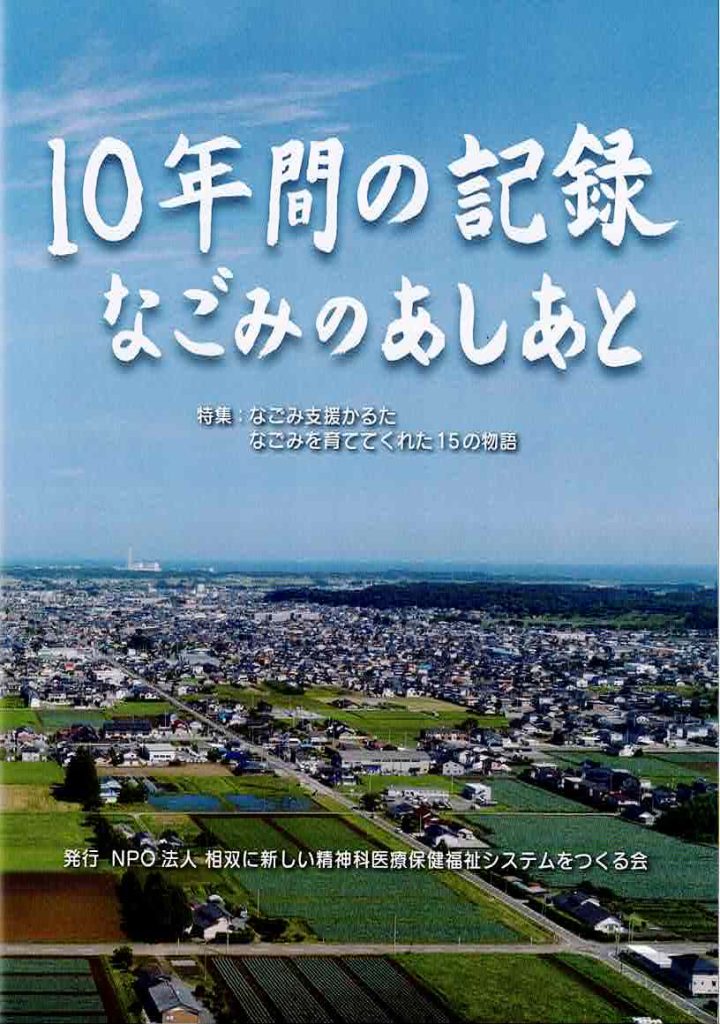災害支援
皆様
新たな年度を迎え、お忙しいことと存じます。
私も、ルーテル学院大学43年目を迎え、地域福祉論の授業を担当することに感謝しています。学生諸君が満足してくれる授業を目指します。
また、4区市の介護保険事業計画・高齢者総合計画の作成に関わらせていただきますが、今回は、制度自体の基盤が揺れており、またニーズも深刻化している現状にどのように取り組むか、非常に難しい舵取りを迫られます。委員の方々とご相談するとともに、課題をまとめて、厚労省の担当部局に問い合わせをさせて頂くことも考えています。ご助言頂ければ幸いです。そして、本年は、民生委員児童委員の改選期。当然、地域包括ケアシステムにおいて重要な方々です。介護保険でも、話されるべきことと考えます。関係する私の意見書を再送します。
お元気で。
ルーテル学院大学
名誉教授 市川一宏
1.全社協メールニュースを送らせて頂きます。
地域福祉・ボランティア情報ネットワーク メールニュース(社協版)
2025(令和7)年度/第1号(通算1045号) 2025.4.1
https://www.zcwvc.net/ E-mail:c-news@shakyo.or.jp
このメールニュースは、「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」のサービスとして、社会福祉協議会関係者に向けて地域福祉、ボランティア・市民活動関係の情報をいち早くお伝えするサービスです。
■ 全社協からのお知らせ等
◆令和7年度「社会福祉法人会計実務講座」のご案内(全社協 中央福祉学院)
社会福祉法人の会計担当者の主な役割は、日々の実務を適切に遂行しつつ決算書を作成することにあります。法人の経営を分析し、経営戦略を考える際、会計担当者が作成する会計・財務資料が重要な役割を果たします。本講座は、会計実務の基礎から財務管理まで段階的に学び、会計の知識を幅広く習得することができる講座です。「社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を理解し、学んだ知識および技術を各社会福祉法人の適切な運営と発展に資することを目的として開講します。なお、本講座では、会計区分の設定の仕方など社協特有の会計処理を学ぶことができる「中級社協コース」を設けています。【受講期間】2025年8月1日~2026年1月31日(6か月間) ※うちスクーリング(集合研修:ロフォス湘南(神奈川県葉山町))に3日間出席。
【受講対象】「社会福祉法人会計基準」に基づく会計実務を行う社会福祉協議会・社会福祉施設・事業所等の役職員
【受 講 料】入門コース/26,400円(税込) 初級コース・中級(社協、施設)コース・上級コース/47,300円(税込) ※通信授業テキスト・教材費、添削指導料、スクーリング参加料を含む。
※スクーリング(集合研修)に係る旅費・宿泊費等は別途負担。
【申込締切】2025年5月16日(金)※先着順
【詳細・申込】下記URLをご参照ください。
【問合せ先】全社協 中央福祉学院 社会福祉法人会計実務講座係
TEL:046-858-1355 FAX:046-858-1356
◆全国で「福祉の就職総合フェア」を行います(4月分)(全社協 中央福祉人材センター)
都道府県福祉人材センターおよび福祉人材バンクにおいて、福祉のお仕事に関する就職総合フェアを行います。各都道府県内の求人事業所がブースを出し、福祉の職場や仕事内容の説明をしたり求職者の質問に直接お答えします。その他、福祉の仕事や就職活動の理解を深めるセミナーや事業所職員によるトークセッション、介護ロボット展示、転職時の資金の貸付事業(介護分野就職支援金貸付事業等)の案内等、さまざまなプログラムが行われています(開催都道府県により内容は異なります)。下記URLより詳細が確認できますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。ご不明な点は、各センター・バンクにお問合せください。
【掲載内容】2025年4月分 【詳 細】下記URLをご覧ください。
https://www.fukushi-work.jp/news/detail_67.html
■ 他団体からのお知らせ等
◆日本地域福祉学会第39回大会(兵庫大会)のお知らせ
地域福祉における「住民自治」のあり方を問う~地域福祉の政策化の時代における「住民自治」の意義と実践の可能性を探る~ (日本地域福祉学会、日本地域福祉学会第39回大会(兵庫大会)実行委員会)
本大会では、地域福祉(「地域における社会福祉」)が政策的にも推進されるという今日的な動向をふまえて、2日間のプログラムを通して、地域福祉(地域による福祉)における「住民自治」の意義と実践の可能性について、理論的な検討を通じて争点を明確にしたいと考えています。あわせて主として近畿圏での地域福祉に関する実践やまちづくりの取り組みを検証することで、地域福祉における「住民自治」の意義と可能性について議論を深めます。
【日 程】2025年6月28日(土)~29日(日)
【会 場】武庫川女子大学 中央キャンパス 公江記念講堂ほか(兵庫県西宮市池開町6-46)
【参加対象】どなたでも参加できます。
【参 加 費】会員事前申込み(団体会員を含む)/8,000円 会員当日申込み・非会員/10,000円 大学院生/4,000円、学部学生/1,000円 要旨集/2,000円
【団体会員について】地域福祉学会では、2022年に団体会員制度を創設し、社協や社会福祉法人、NPO法人などが会員として活動しています。団体会員は、団体として大会で研究発表ができるほか、学会誌「地域福祉実践研究」のなかで「団体活動実践報告」として投稿できます。ぜひこの機会に加入をご検討ください。
【締 切 日】2025年5月22日(木)24:00 ※事前申込締切
【主なプログラム】<1日目>○基調鼎談:地域福祉における「住民自治」をめぐる論点整理―地域福祉の理論と実践の分析・検討を通して―
○大会企画シンポジウム:地域福祉におけるコミュニティの主体性と「住民自治」を問う ―地域福祉とまちづくりの接点にフォーカスして―
<2日目>○大会企画課題別シンポジウム:これからの社協のあり方を問い直す~社協実践を切り口にして~
○大会企画シンポジウム:「地域福祉と包括的支援体制」時代の地域福祉の課題と展望
○開催校企画シンポジウム:地域福祉の推進と多文化共生の取り組み
○優秀実践賞受賞式・報告
○日韓学術交流企画:両国に共通する地域福祉に関するテーマを取り上げ、両国からの報告をもとに、議論を深めていきます。
【詳細・申込】下記URLをご覧ください。
https://www.mwt-mice.com/events/chiikifukushihyogo2025-1
【問合せ先】
○大会運営について 兵庫大会実行委員会事務局(武庫川女子大学) E-mail:jracd2025inhyougo@gmail.com
○大会参加申込等について 名鉄観光サービス株式会社神戸支店(担当/西村、二宮、礒野)
TEL:078-321-5005(平日10:00~17:00) FAX:078-321-5019
E-mail:chiikifukushihyogo@mwt.co.jp
◆令和7年度社協のための「広報のチカラ」講座 ~全国社協広報紙コンクール2024同時開催~
(元社協職員で構成する「全国社協広報紙コンクール実行委員会」)
昨年度に引き続き、社協広報に特化した「令和7年度社協のための『広報のチカラ』講座(全8回)」を開催します。第1回および第2回講座の開催日が決まりましたのでご案内いたします。引き続き申込受付しています。※全国社協広報紙コンクール2024のエントリー受付は終了いたしました。
【名 称】令和7年度社協のための「広報のチカラ」講座
【参加対象】広報担当者等すべての社協職員
【参 加 費】1アカウント6,600円(1アカウント追加4,400円)
※1アカウントで複数名閲覧することはできません
【令和7年度講座開催予定日・内容】いずれも13:30~15:30
第1回 「伝わる」ための広報講座(新任広報担当者に聞いて欲しい内容)(2025年4月24日(木))〔講師〕窄口 真吾氏(株式会社エスフェクト 代表取締役社長)
第2回 受賞広報紙から学ぶレイアウト講座(2025年5月28日(水))〔講師〕窄口 真吾氏(株式会社エスフェクト 代表取締役社長)
第3回 受賞広報紙から学ぶ写真講座(2025年6月予定)
第4回 広報×○○講座(2025年7月予定)
第5回 ホームページ・SNS活用講座(2025年8月予定)
第6回 最優秀賞社協から学ぶ広報紙講座(2025年9月予定)
第7回 優秀賞社協から学ぶ広報紙講座(2025年10月予定)
第8回 TTPT講座(質疑応答中心)(2025年11月予定)
※開催時期・時間は予定です。また、テーマは前後する可能性があります。グループワークも行います。
【開催方法】オンライン(Zoom)※申込者限定でYouTubeにて後日配信します。
【締 切 日】2025年4月10日(木)
【参加申込】専用ホームページより申込みください。
【問合せ先】事務局:Printコーディネーター窄口(さこぐち)
E-mail:shakyokoho@print-for.com TEL:050-3569-0511
◆「地域福祉マンガ大賞」作品集発行のお知らせ(新潟市西区社会福祉協議会)
新潟市西区社会福祉協議会では、マンガで福祉にふれていただくことを目的に、ボランティア、自分らしさ、食をテーマにしたマンガ作品を令和6年7月から10月まで公募しました。全国から63作品の応募があり、下記選考委員による審査の結果、11作品の受賞が決定。このたび、新潟県社協の「県民たすけあい基金助成」を受け、作品集を発行しました。
【掲載作品】○大賞「蒼太と過ごした夏」 作:かくら みのり(熊本県)○ボランティア部門賞「Wonderful days」作:hako(沖縄県)○自分らしさ部門賞「あかりがともるとき」作:グレうさぎ(新潟県)○食部門賞「ひーばあちゃんのご飯」作:千葉 むねむら(茨城県)○特別賞(7作品)「福祉は愛」作:まふぁーる、「キラッッ!! 楽しいのめぐり」作:くと、「焚き火」作:加原 ゆうま、「ホーム」作:OMI、「エリートエンピツ」作:箍為 飛勇、「発達障害のススメ」作:もへこ、「動けばマルく」作:うつろー
【選考委員】石川 兼司氏(日本アニメ・マンガ専門学校 講師)、渡辺 仁介氏(日本アニメ・マンガ専門学校 講師)、 村山 賢氏(NPO法人新潟ねっと 代表)、支え愛戦士アワセロン氏(NPO法人身寄りなし問題研究会 代表)、大学生ボランティア、新潟県社協職員、新潟市社協職員など4名 /計8名
【体 裁】A5判 192ページ【配付について】郵送料をご負担いただければ、全国へお送りいたします。(先着700部)
【詳 細】下記URLをご覧ください。
◆ニッセイ財団「高齢社会を共に生きる-つなげる・支え合う居場所づくりと地域共生社会-」
第37回シンポジウム・第31回ワークショップ記録集無料配布のご案内(公益財団法人日本生命財団(ニッセイ財団))
ニッセイ財団では、活動助成・研究助成の成果を社会に還元する観点から、シンポジウム・ワークショップを毎年開催しております。このたび昨年12月開催分の記録集が完成しました。希望者先着500名様に無料で配布いたします。
【記録集概要】A4版117ページ おひとり3冊まで
送料:申込者負担(1冊284円、 2~3冊344円)
※着払い(日本郵便「ゆうパケット」にて郵送)
【記録集目次(抜粋)】
<第37回シンポジウム「高齢社会を共に生きる」>
○第1部:基調講演
・こども食堂と私たちの地域・社会
〔講師〕湯浅 誠氏(認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ理事長)
○第2部:実践報告(地域福祉チャレンジ活動助成成果報告)
・高齢者の社会参加への場づくり:子どもたちと触れ合う地域の再生
穂坂 光彦氏(認定NPO法人パルシック 共同代表理事)
吉浦 諒子氏(認定NPO法人パルシックみんかふぇ 代表)
〔講評〕市川 一宏氏(ルーテル学院大学 名誉教授)
・町民の孤まり事を減らしたい!共生型居場所から始まる重層的支援
大谷 真氏(函南町社会福祉協議会 係長)
〔講評〕宮城 孝氏(法政大学 教授)
・人生の見取りまで含む生活支援「東郷ささえ愛家族」
織田 英嗣氏(NPO法人ノーマCafe 理事長)
〔講評〕大塚 眞理子氏(長野県看護大学 学長・教授)
○第3部:総合討論
・つなげる・支え合う居場所づくりと地域共生社会
〔コーディネーター〕上野谷 加代子氏(同志社大学 名誉教授/日本医療
大学教授)
〔コメンテーター〕白澤 政和氏(国際医療福祉大学大学院 教授)
〔アドバイザー〕湯浅 誠氏
〔シンポジスト〕穂坂 光彦氏、大谷 真氏、織田 英嗣氏
<第31回ワークショップ「高齢社会実践的研究助成成果報告」>
○第1部:若手実践的課題研究助成
・僻地に住む独居高齢者に対する社会的交流促進のアウトリーチ支援
高田 大輔氏(文京学院大学保健医療技術学部 准教授)
・高齢者の孤独感を軽減するVirtual Reality(VR)プログラムの開発
今井 鮎氏(京都府立医科大学大学院医学研究科 精神機能病態学博士課程)
・認知症高齢者の就労支援に関する実践的研究
郭 芳氏(同志社大学社会学部 准教授)
・介護職員の危険予知能力評価尺度の開発と安全管理研修への応用
山鹿 隆義氏(名古屋女子大学医療科学部 准教授)
・太極拳を活用した高齢者の健康増進:科学的検証とプログラム開発
陳 岑氏(九州大学大学院 人間環境学府博士課程)
○第2部:実践的課題研究助成
・DXを用いた高齢者を支える家族関係重視型Advance Care Planning(ACP)
プログラムの開発
鈴木 みずえ氏(浜松医科大学臨床看護学講座 教授)
・「地域共生社会」の実現に向けた社会関係資本の実証的研究
塚本 利幸氏(福井県立大学看護福祉学部 教授)
【記録集申込方法】下記URLより申込方法をご確認ください。
https://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/03.html
◆ICTリテラシー向上にかかる教材の積極的な活用について(総務省)
総務省では、これからのデジタル社会において求められるリテラシーを向上するため、公式サイトにおいて各種教材を公開しています。積極的にご活用ください。
1. 5つの分野のICTリテラシーを学ぼう
~つくろう!守ろう!安心できる情報社会~
青少年、保護者、シニアの皆さまを対象に、これからのデジタル社会において必要となるICTリテラシーを身につけるための教材です。本教材では、デジタル空間の特性を理解し、新たな課題にも対処できるよう、最新の事例も用いながら学習することが可能です。
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/Ictliteracy_for_yps/
2. インターネットとの向き合い方
~ニセ・誤情報にだまされないために~第2版
ニセ・誤情報に関する留意点や対策についてまとめた教材です。本教材では、災害時に広まるニセ・誤情報など最新事例や生成AIの影響、民主主義への影響等を踏まえて、ニセ・誤情報について学ぶことが可能です。併せて公表している講師用ガイドラインは、資料に従って講座を進めることで、どなたでも気軽に講座の実施が可能です。
https://www.soumu.go.jp/use_the_internet_wisely/special/nisegojouhou/
3. 官民連携プロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」
総務省では、令和7年1月にプラットフォーム事業者等を含む19の事業者・団体と連携して、意識啓発のためのプロジェクト「DIGITAL POSITIVE ACTION」を立ち上げました。企業・団体のステークホルダーとともに官民で連携した取り組みを進め、さらなるICTリテラシーを向上する取り組みを推進しています。
https://www.soumu.go.jp/dpa/
●「地域福祉・ボランティア情報ネットワーク」トップページ
http://www.zcwvc.net/
●メールニュースのバックナンバーはこちらで見ることができます
https://www.zcwvc.net/member/mailnews/
●メールアドレスの変更、メールニュースの配信停止はこちらへ
https://www.zcwvc.net/member/mailnews/
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
社会福祉法人 全国社会福祉協議会
地域福祉部/全国ボランティア・市民活動振興センター
TEL:03-3581-4655/4656
メールニュース(社協版)専用:c-news@shakyo.or.jp
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
次回は2025(令和7)年4月8日(火)に発行予定です。
2. 東京都地域公益活動推進協議会からのニュースです。
本会事業、東京都地域公益活動推進協議会のホームページが、4月1日をもってリニューアルオープンいたしました!
https://clk.nxlk.jp/m/S9yuap7oF
①地域公益活動の事例検索が簡単になりました!
新たにタグ検索機能を追加!これまで以上に情報を探しやすいウェブサイトになりました!
②デザインを一新しました!
たくさんの方に見ていただけれるサイトを目指し、明るくポップなデザインに仕上げています。マスコットキャラクターつつまるも新しいサイトで皆さんを出迎えます!
③実践事例の寄稿が簡単にできるようになりました!
各社会福祉法人の実践事例がホームページ上で投稿が可能に!メールでのやり取りが不要になり、スムーズにご寄稿ができます!
新しくパワーアップしたウェブサイトへ、ぜひアクセスして下さい!
※一部リニューアル作業中のページがございます。予めご了承ください。
=====================
<東京都地域公益活動推進協議会 事務局>
社会福祉法人 東京都社会福祉協議会
福祉部 経営支援担当(阿部)
3. 全国社会福祉協議会 地域福祉部 全国ボランティア・市民活動振興センターより
3月4日に開催いたしました「市区町村社会福祉協議会ボランティア・市民活動センターの機能強化に係るオンラインサロン~KICK・OFF~」につきましては、ご要望も多かったことから、オンラインサロンのアーカイブ配信を行うことに致しましたので、当日ご覧いただけなかった方や、ご関心のある方が周囲にいらっしゃいましたら、
下記サイトをご案内くださいませ。
投稿日 25年04月05日[土] 11:16 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,学会 ,災害支援 ,社会福祉関連
2011年3月11日に起こった東日本大震災は、多くの問いを私たちに投げかけています。あと3日で、2025年3月11日。私も、2020年3月まで石巻市社協•石巻市の地域福祉アドバイザーをさせて頂き、たくさんの方と出会い、学ばせて頂きました。もう一度、あくまで可能ならば、石巻市の地域に立ち戻り、被災地と協働していく可能性を模索したいと思っています。
映画『生きて、生きて、生きろ』
〜喪失と絶望の中で生きる人々と ともに生きる医療従事者たちの記録〜
震災と原発事故から13年。福島では、時間を経てから発症する遅発性PTSDなど、こころの病が多発していた。若者の自殺率や児童虐待も増加。メンタルクリニックの院長、蟻塚亮二医師は連日多くの患者たちと向き合い、その声に耳を傾ける。連携するNPOこころのケアセンターの米倉一磨さんも、こころの不調を訴える利用者たちの自宅訪問を重ねるなど日々、奔走していた。
ある日、枕元に行方不明の夫が現れたと話す女性。http://ikiro.ndn-news.co.jp/
私は、2025年2月21日、ルネこだいら(小平市民文化会館)で行われた映画上映会に参加し、終了後の映画監督島田陽磨氏と現地で実践する米倉一磨氏(精神科認定看護師)の対談を聞くことができました。想像を絶する被害の深刻さと、その現実の地域の中で働く医師の蟻塚亮二氏、看護師の米倉氏等の働きを知り、そもそも医療、看護、福祉のあり方を考えるきっかけが与えられました。また、以下の本とも出会いました。
本 NPO法人相双に新しい精神科医療保健福祉システムをつくる会『10年間の記録〜なごみのあしあと 特集なごみ支援かるた、なごみを育ててくれた15の物語』
相双とは、いわき市以北に位置し、太平洋に面した南北に長い地域を言い、相馬市、南相馬市、相馬郡及び双葉郡の2市7町3村がある。すなわち、福島県の原発事故により、大きな影響を受けた地域である。そこで、「相双地域の保健、医療、福祉の向上に寄与することを目的として設立しました。具体的な活動としては、地域住民の方々や、公共職員、福祉事業に関わる職員の方々に対するこころのケアが中心となりますが、活動を通して住民の方々と精神科医療、福祉施設とのつながりを円滑にし、地域との絆を深めていきたいと考えています。」(HPに記載された法人概要)
なごみ支援かるたの「本人より焦る支援者の空回り」「変われない人の弱さは支援のカギ」「玄関に入れてもらえば合格点」「専門家できないことは専門外」「憎まれるそれも支援の第一歩」等を読みながら、思わず頷いていました。また15の現実の問題から、活動の一端を知ることができました。お薦めです。
実践『カリタス南相馬』
「カリタス」は、「愛」という意味のラテン語です。感情的な好き嫌いの愛ではなく、相手をそのものとして無条件に大切にする愛を表すのが「カリタス」という言葉です。
カリタス南相馬は
東日本大震災と原発事故により、困難な状況におかれている人々とともに生き、すべての人々の尊厳が尊重される社会を目指します。
福島第一原発から25kmにある場として、福島の現実とそこに生きる人々の思いを世界につなぎます。
地球環境を大切にし、自然との共存を目指します。
地域コミュニティの再創造に向け、地域の人々とともに働きます。
原発事故がもたらした福島の厳しい現状と地域の日常の変化、いのちの尊さを学び、ともに祈り、伝えます。
自然とともに生きる暮らしの実現に向けて、生活を見直します。
◆ カリタス南相馬について
カリタス南相馬は被災者と被災地全体に対して幅広く救援・復興活動を実施するために開設しました 。
◆ カリタス南相馬の活動
カリタス南相馬は、
映画『風に立つ愛子さん』
2011年の東日本大震災で石巻の家を津波に流された村上愛子さん、当時69歳。その出来事は天涯孤独に生きていた愛子さんの人生を大きく変えました。避難所での集団生活は、今まで知り合うこともなかった近隣の方と寝食を共にし、皆と心のつながるかけがえのない時間でした。その後、仮設住宅で7年を過ごし復興住宅へと移っていく―この映画は、震災後の8年間、愛子さんを見つめ続けたその記録です。津波を「津波様」と呼び、震災が幸せを運んでくれたと言う愛子さん。被災者とひとくくりにできない、ひとつの人生がここに映っています。
東日本大震災から14年。能登半島地震から1年。高齢化が進む日本で、今こそ被災について思いを巡らす。
監督は、2012年に公開した『石巻市立湊小学校避難所』を制作した藤川佳三。避難所で出会った愛子さんの明るく奔放な性格に魅了された藤川は、それから断続的に石巻に通い愛子さんが亡くなるまでカメラに収めていきました。 高齢者の独り暮らし、それに伴う孤独死の問題は、「おひとりさま」という言葉で、すでに社会問題化しています。身寄りのない高齢者が、住む家を失い避難所で集団生活を送ったり、仮設住宅や復興住宅で、新しい近隣との付き合いの中で暮らしていくことは、いかに孤独で心身に負担を与えるのか。本作を観ることで、改めて被災とその後の生活について思いを巡らすきっかけになればと願います。(HPより)https://aikosan.brighthorse-film.com
投稿日 25年03月08日[土] 10:58 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連
今から30年前、1995年1月17日午前5時46分52秒、兵庫県淡路島北部、あるいは神戸市垂水区沖の明石海峡を震源として、マグニチュード7.3クラスの自信が発生しました。震源に近い神戸市の市街地の被害は大きく、たくさんの家屋が潰れ、高速道路がなぎ倒され、燃え広がる火災が起こり、6,434人もの方が命を落とされました。私は東京にいて、テレビで報道される深刻な被害を見て、思わず驚きの声を上げていたことが、今さらのように思い出されます。
その後、私は、神戸市長田区の老人ホームに泊まり、デイサービスの利用者の追跡調査に加わりました。焼け落ちた市場を見、また火事が起こった発災当時の混乱を聞くにあたって、大切な人、家、思い出のものを失った方々の痛みと出会い、復興までの道のりが本当に長いのではないかと率直に思いました。しかし、全国から、たくさんのボランティアが集まり、支援に入り、あらたなNPOが広がり、絆を作り上げました。ガバナンス、すなわち統治(government)から協働へという言葉が登場したのもこの時期です。
1995年時より、阪神淡路大震災の被災地の新たな歩みが始まりました。本年は、30年目。阪神淡路大震災1.17のつどい実行委員会は、以下の呼びかけをしました。「1995年1月17日 午前5時46分。阪神淡路大震災が発生し、私たちの大切なものを数多く奪っていきました。あの震災から、まもなく30年を迎えようとしています。震災でお亡くなりになられた方を追悼するとともに、震災で培われた「きずな・支えあう心」「やさしさ・思いやり」の大切さを次世代へ語り継いでいくため、2025年1月17日(金)に「阪神淡路大震災1.17のつどい」を、神戸市中央区の東遊園地で行います。」テーマは『よりそう』でした。
そこで遺族代表の武田眞理さんは、以下のように述べました。「犠牲になった父からのメッセージ あの朝、子どもたちのお弁当を作っていた私は、突然の激しい揺れであっという間に足が冷蔵庫に挟まり動けなくなりました。関東大震災の生き残りだった祖父がいつも口にしていた「揺れたら火を消せ」の声が聞こえました。手を伸ばしガスを切った途端、体はがれきに埋もれました。暗闇の中をもがいて外に出たときに見たのは、跡形もないわが家と、割れた屋根の下でぼうぜんと娘を抱く主人の姿でした。父母と息子の姿はありませんが、名前を呼ぶと母と息子からは返事が。靴もないまま道路へ出て助けを呼んで、主人と駆けつけてくださった人々の手によって息子は生還し、母は土まみれながら助かりました。 昼になり、変わり果てた姿で父が出てきました。前夜、いとこに電話をかけ、100歳まで生きると言っていた父の生涯は、67歳で終わりました。私は涙に枯れる間もなく、母は自責の念にかられ、恐怖に震える6歳と10歳の子どもたちをどう育て生きていくかで頭がいっぱいでした。 子どもの発熱で葬儀にも出席できず、棺に手紙をいれたくてもメモもない私でしたが、父は一人犠牲になって家族を守り、それは私に強く生きろというメッセージに思えました。 でも、悲しいことばかりではありません。いつもと同じ朝を迎えられる喜びを知り、行政や多くの方から支えていただきました。それらが前を向く原動力でした。大切な家族を心の準備もなく失いましたが、心の中で故人はいつまでも生き続けています。 この30年、さまざまな自然災害がおこり、昨年能登を襲った地震は記憶に新しいです。同じような悲しみをもった人たちに心の平安が訪れることを願うとともに、命の大切さを伝えていきたいと思っています。」
なお、以下のNHKの記事の神戸中央区追悼式の画面をご覧ください。私は、感動で心が揺さぶられました。皆さんもどうぞご覧ください。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250116/k10014694881000.html
私は2020年3月末日をもって、石巻市社協、石巻市の地域福祉アドバイザーとしての役割は終えましたが、東日本大震災の被災地支援は、私の教員人生に多くの教訓を与え、学びの時でした。市川一宏研究室に、大切にしていることを掲載しています。時間がありましたら、お読み下さい。これからも、ずっと、石巻の復興をわすれません。
さて、私は、皆さんに、3つのお願いをしたいと思います。
一つは、震災が起きた時に備えて、まだ家族や友人と相談をしていないなら、防災のチェックリストは色々ありますが、首相官邸のホームページが見易いです。
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/index.html
広く防災を学ぶには首相官邸のホームページがわかりやすいですが、それぞれのお住まいの地域ごとに災害リスクは異なります。ぜひ、お住まいの自治体のホームページなどをご覧いただくか、ハザードマップなどで、ご自身のお住まいや職場、学校がどのようなリスクがあり、どこへ避難すればよいか考えてもらうのも良いかと思います。
https://disaportal.gsi.go.jp/
以上、全社協の駒井公さん情報です。
また、後述する加藤明子さんからの情報です。
・「阪神淡路大震災記念 人と防災未来センター」ホームページより
https://www.dri.ne.jp/useful/checklist/
英語 中国語 韓国語もあります
・世帯状況に合ったアレンジを加えたリストを作成してくれるサイト
東京備蓄ナビ
https://www.bichiku.metro.tokyo.lg.jp/tool/
・障害当事者のワークショップでも活用
国立リハビリテーションセンターが作成したキット
https://www.rehab.go.jp/ri/kaihatsu/suzurikawa/res_saigai01.html
・シンプルでわかりやすい首相官邸版 対象別の追加物品がポイント
https://www.kantei.go.jp/jp/content/000111250.pdf
・持ち出し品だけでなく、自宅での備えを幅広く記載した「井の頭一丁目町会
チェックリスト」。https://www.dropbox.com/scl/fi/79crmek83ilpwae8rrwvt/.jpg?rlkey=hwnvthdiibntp1gpdy3xg9cww&dl=0
第二に、能登半島地震被災地の支援に関する情報をお伝えします。能登支援については、つい先日内閣府が被災地支援に入るボランティア団体向けの補助金を創設してます。
https://www.bousai.go.jp/kyoiku/bousai-vol/kotsuhojyojigyo.html
奥能登ではまだボランティアも募集していますので、ご関心のある方はぜひ。
個人で参加される場合は、下記ホームページから応募する形になります。
https://prefvc-ishikawa.jimdofree.com/
被災地である能登半島の現状を追いながら、可能な、必要としている支援を考えていきたいと思っています。
以上、駒井さんからの情報提供でした。
また、吉村誠司さんは、今も、facebook等で発信して下さっています。
第三に、地域で防災ネットワークを広げようとしている加藤明子さん(三鷹市福祉Laboどんぐり山三鷹市介護人材育成センター、東京社会福祉士会災害福祉委員会)を紹介します。「防災士になった経緯」「災害対応に関して考えていること」を中心に書いて頂きました。
<「防災士になった経緯>
・防災士とは、「日本防災士機構」が認証した研修期間で研修を受講し、一定の基準
(事前レポートとテスト)を満たし合格したら取得できる民間資格です。
資格を持つことで得られる職務がある訳ではなく、あくまで民間ボランティアです。
・研修は「災害発生のしくみ」「災害二関する情報」「公的機関や企業の災害対策」
「自助」「共助」そして「防災士制度」の科目があり、丸2日間受講します。
私がこの資格を目指したのは、直接的には地域包括支援センター時代に、地域防災に熱心に取り組む町会さんや住協の方々に関わらせていただいたことが契機です。皆防災について多くの知識を持っており、東京都の講座などでさらに学び続けておられる姿勢に、感銘を受けました。そして、住民の方々が「日頃のつながりが、災害などもしもの時に生きる」という認識で防災のことを捉えていたことに、地域福祉の神髄をみました。「防災」と「みまもり、支え合い」を一連の流れで考え、日頃の共助が
災害時の助け合いにもつながる、という視点です。
学ばないと、彼らと同じ目線で地域防災を考えられないと思い、この頃から防災の
本を読むなどしていました。また、子どもを連れて地区の防災イベントに参加させて
いただいていました。そして、要配慮の人たちが取り残されない地域づくりについて、町会や住協の企画に参加するとともに、名簿を元に杏林のゼミの学生とマッピングをしたり、地域支援連絡会で地域内の取り組みを高齢者に限らず共有して住民と行政と専門職で課題抽出する機会をつくるなどしてきました。
専門職向けには、東日本で被災したケアマネの方の話を聞く企画を行い、意識調査をしました。そして、あまりに三鷹の災害対応の仕組みを知らないことに衝撃を受けました。これではBCPなどと言っても絵に描いた餅だなと思い、その後は医師会付の勉強会「地域ケア会議」(医師、薬剤師、訪問看護師、ケアマネがメンバー)の企画に加わらせてもらっています。
<防災に関する思い>
「正しく知って備えて誰もが生きのびる確率を上げられるように」そして「いつもも、もしもも繋がりで支えあう地域福祉」というところでしょうか。災害に限らず、疾病や障がい、認知症など支え合う意識を持っている人が増えるよう、防災活動を一つのきっかけにできたらいいと考えています。
防災は、まちづくりです。それを被災地支援を通して、それぞれの地域で学んでいくことが大切だと思っています。それは、今行われている孤独孤立予防、認知症対応、生活困窮者対応と、共通しています。いや、すべての住民が当事者である点で、より普遍性があるのではないでしょうか。これからも<震災で培われた「きずな・支えあう心」「やさしさ・思いやり」の大切さを次世代へ語り継いでいくため>できることをしていきたいと私は思っています。
皆さん、お元気で。
2025年1月29日
市川一宏
投稿日 25年01月29日[水] 10:38 AM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連
皆さん、おはようございます/こんにちは/こんばんは。お元気ですか。
さて、2月22日に、ハイブリッドで開催されます21世紀キリスト教社会福祉実践会議大会のご案内をさせて頂きます。
大会では、「誰が隣人になったと思うか?」〜ともに生きる関わりを求めて~をテーマに、以下のプログラムが予定されています。
開会礼拝:上田憲明氏(日本聖公会東京教区司祭)
基調講演1:幸田和生氏(カトリック東京教区名誉補佐司教、一般社団法人カリタス南相馬代表理事、カトリック原町教会司祭)、現在も進行中の原発被害に直面する住民と共に歩む「カリタス南相馬の働き」から学びます。
基調講演2:向谷地生良氏(社会福祉法人浦河べてるの家理事長、北海道医療大学名誉教授)、「他者の苦しみへの責任と連帯」を目指し、精神的障がいをもつ方々と共にある浦河べてるの働きから学びます。
シンポジウム
・稲松義人氏(社会福祉法人小羊学園理事長)「重度の障害をもつ人と歩む」、意思を判断すること自体が難しい重度の知的障がいをもつ方と共に生きていく日々の実践を学びます。
・下条裕章氏(聖公会神田キリスト教会司祭、きぼうのいえ施設長・理事長)「独居の高齢者の生活を支えるために」、高齢化が進む山谷において、「生」を全うするための宿屋を提供する実践から学びます。
・長縄良樹氏(日本児童育成園統括施設長)「一人ひとりの子どもの成長と可能性を支えて」、
子どもの成長を支援して多様なケアを展開する育成園の実践から学びます。
司会者である石川一由紀氏(救世軍本営社会福祉部長)のコメント
「それぞれ切り口は違うが、「歩み寄る」「支える」という実践の中で「隣人」になろうとしてきたことを掘り下げたい」
閉会礼拝 小勝奈保子氏(日本福音ルーテル聖パウロ教会牧師)
閉会の挨拶 大橋愛子氏(さかえ保育園園長)
なお、実践会議は「神は苦しむ人間の姿を見て、見逃さず駆け寄り、寄り添い、その痛みを背負って下さる方であることから、強い共感が生まれる。神と同じように人々の苦しむ姿に共感して駆け寄るならば、神を信じる、信じないにかかわらず、意識するとしないとに関わらず、神と結ばれた共に歩む隣人である」(カトリック司教森一弘先生)という基本的考え方を大切にしてきており、施設職員の研修の場にもなってきました。
是非、ご参加くださいますよう、お願いいたします。
2025年1月21日
21世紀キリスト教社会福祉実践会議代表
ルーテル学院大学 名誉教授 市川一宏
参加の申し込みは、以下のパンフレットをご参照ください。
https://www.dropbox.com/scl/fi/vyhs4knc918qgsirvqcwh/12-202410.10.pdf?rlkey=r2k87ip9600ozn1r8503dxl33&dl=0
投稿日 25年01月23日[木] 12:01 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,大学関連 ,学会 ,教会関連 ,災害支援 ,社会福祉関連
三鷹ろうなん防災委員会は、三鷹市の聴覚障がい者協会と登録手話通訳者会、手話サークル鷹の会の3団体で構成され、災害が起きたときに聞こえない人が安心して避難できるように様々な対策を考える活動をしています。私に直接メールが届いたことを契機に、聴覚障がい者:防災イベント体験に、参加しました。
日時:2024年11月30日(土)16:00~18:00
会場:元気創造プラザ 3階1~4会議室
私は、被災地支援には随分参加しましたが、それぞれの課題について、踏み込んだ議論をしていないことに反省しています。
会場の部屋は2つに分かれ、体験学習をする部屋には、テントが並べられ、まず耳栓と音を遮断するヘッドホンをつけて、テントに一人入ります。そして、一定の時間、電気が消され、条件を渡され、実体験をすることにしました。そこで体験したことは、後でグループに別れ、カード方式でまとめられました。
また別の部屋では、聴覚障害者会の方から講義を受け、掲示した模造紙から、何が課題か学びます。聴覚に障がいがあると言っても、千差万別であり、またコミュニケーションに違いがありますが、災害など緊急事態になると、体力も精神も参る状態に陥ったり補聴器の電源が切れて、普段とれていたはずのコミュニケーションが取りづらくなります。さらに、周りの人に「きこえない」と気づいてもらえないとか、アナウンスや呼び出しがわかりません。実体験をして、不安や戸惑いでストレスが大きいことを感じました。さらに自分で出す音の大きさもわからず、周囲とトラブルになることもあるそうです。
最近、被災地に行くことが多くあります。いや、地震だけでなく、大雨、洪水、台風等で被災を受けているところが多くなっていることでもあります。東日本大震災の関係では、いわき市、多賀城市、宮城県、福島県、石巻・女川・東松島ブロック等を訪問し、現状を知ることができました。まだ、地震の影響が残っています。だからこそ、私たちは、忘れてはいけない。また能登半島地震においても、まだまったく問題が解決できていない。日本のどこでも、自然災害が起こる危険性がある。だから、被災地支援を通して、今までの取り組みと現状を学び、自分たちのい地域の防災力強化に努めていくことが必要だと痛感しています。
今回の三鷹市ろうなん防災協会の研修に参加して、その思いを強くしました。被災地のことを決して忘れません。
なお、同委員会が資料をまとめています。非常に貴重な資料です。
https://www.dropbox.com/scl/fi/9mxf48t675lwa36ahtesk/.pdf?rlkey=gf2bbphkphwnbfz6touvcn4a9&dl=0
投稿日 24年12月08日[日] 4:12 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連
2024年11月26日午後10時47分ごろ、石川県西方沖を震源とする最大震度5弱の地震が発生しました。 富山県内では震度4の揺れが観測されています。 最大震度5弱を観測したのは石川県です。 この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード(M)はM6.4と推定されます。(富山テレビ)
今、能登半島に支援に入っている吉村誠司さんのことが心配です。発災当初より、重機を使って被災者の救出、生活基盤の立て直しを行なっており、現在も続く厳しい現実をフェースブックで伝えてくれています。
https://www.facebook.com/seiji.yoshimura.73
吉村さんが公表している彼の履歴を紹介したいと思います。1965年8月三重県生れ。聖パウロ学園高(全寮制)、1991年3月ルーテル学院大学(社会福祉コース)卒業 。在学中ワークキャンプ・交流国際NGOを発足、18 ヶ国を自転車等で一人旅しインドで荷物を失い人生が変わる。25歳で国分寺市議会議員に当選。国分寺子ども劇場会員、東京YMCA運営委員、多摩ワイズメンズクラブ会長、国分寺青年会議所副理事長、専務理事歴任(転居の為退会)。95年阪神淡路大震災では、神戸市長田区へ入り支援活動、後日「神戸元気村副代表」になり、仮設住宅等の孤独死を防ぐ 24 時間の緊急通報システムや子どもケア、引越し隊、動物保護など様々な活動展開し、市政へも提案。97 年日本海重油流出事故では、情報HPを神戸から発信(NHKプロジェクトXで紹介)。
00 年カンボジア対人地雷撤去支援活動開始、03 年反戦活動でイラク入り、バスラ近郊や病院で湾岸戦争で使用された劣化ウラン弾被害の現状調査し医療支援、NGOヒューマンシールド神戸を設立。中越、中越沖地震、パキスタン、中国雲南や四川省、インドネシア各地震でも活動、アフガニスタン選挙NGO監視団では難民キャンプへ。12 年間(約8年神戸元気村、約4 年ヒューマンシールド神戸)神戸で活動し、災害時は、初動救援から曳き起し手法での修復技術なども紹介、被災者生活再建支援法の活用等伝える。各地や学校で講演会や防災や重機の講師を務める。東日本大震災では、発生直後に出発し、翌早朝には宮城県気仙沼、岩手県陸前高田へ入り 1 週間は初動救援などの活動。石巻災害ボランティアセンターと連携する NPO 連絡協議会の立ち上げ協力。その後、各地の地震や豪雨被災地へ…●(社)OPEN JAPAN 理事、防災士、カヌーガイド、長野県森林整備技術者、元立教大学非常勤講師、消防団員、重機オペレーター (車両系建設機械、小型移動式クレーン、フォークリフト、大型・特殊免許 )、CONE リーダー、(特活)インターバンド理事、災害救援NGOヒューマンシールド神戸代表 、下手な手品師。
吉村さんは、誰よりも早く被災現場に駆けつけ、重機を使って、現地の要望に対応してきています。どうぞ、吉村誠司さんの活動をご支援ください。
Donation Yuucho Bnk 00980−7−264796 ヒューマンシールド神戸
投稿日 24年11月26日[火] 11:49 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連
2024年5月18日(、東京発9時53分ひたち7号に乗り、いわきに向かい、そしてJR常磐線各駅に乗って13時12分に双葉に着きました。東日本大震災・原子力災害伝承館を訪問するためでした。しかし、急遽、いわきに戻ることになりましたが、引き返す電車の時間まで1時間半あり、待つ間、近隣を歩きました
そもそもJR常磐線は、東日本大震災と東京電力福島第1原発事故の影響で不通区間が残っており、2020年3月14日、富岡―浪江間(20.8キロ)で運転を再開し、9年ぶりに全線がつながった線です。双葉駅は無人駅でしたが、きれいな新しい駅で、線路を境に海の反対側には復興住宅が建てられていました。しかし、海側の土地は、雑草が生い茂り、廃屋が残されていました。その写真です。
私は、違和感を感じながら駅の近くを歩きました、私が感じた違和感の理由を後から知ることになりました。翌日頂いた資料を見ますと、双葉町は帰宅困難地域で、私が歩いた場所は、特定復興再生拠点地域で、双葉町の大部分は、帰還困難地域でした。福島原発事故の終息がいつ来るかはまったく見えていないことがわかりました。
2021年2月11日の東京新聞には、双葉駅に関して、以下のことが書かれていました。
「住民のいない町」JR常磐線双葉駅のある一日<あの日から・福島原発事故10年> 東京電力福島第一原発(福島県大熊町、双葉町)から4キロの場所に、JR常磐線双葉駅がある。新しい駅舎に隣接する旧駅舎の時計の針は「2時47分」を指したまま、10年前の地震直後から動かないのだろう。昨年3月に駅周辺や沿岸部の一部で、許可証なしの立ち入りが可能になったものの、インフラ整備の遅れで町民が生活できるのはまだ先。今月5日、「住民のいない町」の一日を玄関口である駅で追った。
5時56分 東の空にわずかな赤みが差す。いわき(福島県いわき市)行きの上り一番電車に乗降客はいない。無人の改札で、空間線量計のデジタル数字が赤く光る。
7時5分 原ノ町(南相馬市)行きの下り普通電車から、沿岸部にできた町産業交流センターに入る企業で働く神田秀一さん(53)=楢葉町=が同僚と降りた。「車の方が便利だけど、双葉町で働く人間としてせっかく復旧した交通機関を使いたいので」。町のシャトルバスに乗り込んだ。運賃は当面無料だ。
8時20分 「電車は風が吹くとすぐ遅れちゃうから、みんな車だよ。駅は立派なんだけどな」。シャトルバス運転手の奥田邦勇さん(72)がぽつり。20分ほど待つも、無人で出発した。 以下省略(HPよりご覧になれます)
そのような背景がある駅とは知らず、原発事故の影響が続いている現状を実体験しました。そして、常磐線の線路の下はコンクリートで固められていますが、それは線量を下げるために行われていることも後から教えて頂きました。東日本大震災が起こった2011年3月11日から13年経ちますが、被害の状況は現存し、かつより深刻化していました。
私は、その後、いわきに戻り、遅い昼食を食べて、再びJRに乗り、双葉駅を通過して、宿泊予定の南相馬市の原ノ町駅に向かいました。その車窓から見えた夕焼けが、水田に映る景色を見て、自然に抱かれている様な温かい気持ちになりました。
5月19日(日曜日)、食事の後すぐに、Youtubeの阿佐ヶ谷教会の礼拝が始まる前の時間、ホテルの自転車を借りて南相馬市原町シーサイドパークに行きました。海岸には、きれいな広い砂浜が広がり、水遊びを楽しむ親子連れや、サーフィンをしてる人、犬を連れて散歩している人たちがたくさんいました。
左には、原町火力発電所がありました。約12年前に、全国の社協職員から寄せられたお見舞金を持参して南相馬市社協を訪問した時に、福島原発事故の前に、火力発電所の爆発があったことをお聞きしていました。
なお、海岸までの道は、登りあり、下りありで、さらに幹線道路から脇道に入ると、蛇行していました。帰りも長い坂を上り、予定通りホテルに戻ってきましたが、それほどの疲労感を感じませんでした。自然の美しさを味わいながら、すがすがしく晴れた空の下で、自転車を漕いでいたからと思います。
午後2時には、カトリック原町教会のミサに出席をしてきました。私の所属教会は、カトリックではありませんが、ロウソクがいたるところに置かれた礼拝堂の中で、幸田先生から語られる愛には、強い説得力を感じました。
df821b0404145d25250214240b0d4e54
原町教会の幸田和生司教様にお会いし、先生が代表をなさっておられた21世紀キリスト教社会福祉実践会議のこれからの運営について、ご助言を戴くことは、今回の訪問の重要な目的でした。同実践会議については、後日ご紹介させて頂きます。
ミサの後、幸田先生に東京から福島の浜通りに教会を移られた理由をお聞きすることができました。幸田先生は、先の原発事故の後の被害の地図に示されているように、まだほとんどが解決できていません。土地を追われた住民、今までの大切な絆を断ち切られた人々、急激な少子高齢化によってコミュニティの機能が失われた場で生活を続ける人々とともにありたいという強い思いに、私は心を揺すぶられました。
隣接するカリタス南相馬にお伺いし、神父様、シスターの方々、担当スタッフと食事を頂きました。なお、驚いたことに、そのスタッフが、20数年近く会っていなかった卒業生でした。心より感謝しました。
最後に、カリタス南相馬の紹介をさせて頂きます。代表の幸田先生は、以下のように語られています。
カリタス南相馬へようこそ インフォメーション
新年のご挨拶
2024年を迎えて 世界的にさまざまな問題・課題を抱えながらも、喜びと希望をもって新年を迎えようとしていたところ、いきなり1月1日に能登半島に大きな地震が起こってしまいました。この文章を書いている時点で地震発生からまだ4日しか経っていませんが、次第に明らかになる被害の大きさに驚くばかりです。亡くなられた方のご冥福をお祈りするとともに、被災されたすべての方がこの困難を乗り超え、一刻も早く生活を取り戻すことができるようお祈り申し上げます。
わたしたちカリタス南相馬は東日本大震災と原発事故以後の歩みの中でさまざまな経験をしてきました。今回の被災地からは遠く離れていますが、これまでの経験を活かしながら、わたしたちにできることを見つけていきたいと思っています。
今年のカリタス南相馬のキャッチフレ「見さ来ぅ南相馬!」としました。そのことを紹介した『東京教区ニュース』第409号(2024年1月1日発行)の「福島の地から〜カリタス南相馬」という文章ですが、肝心の年号を間違えて原稿を提出してしまいました。訂正した文章を以下に載せますので、どうかお読みください。 わたしも含め、スタッフ、シスターも高齢化してきて力の衰えを感じることがあります。いろいろご迷惑をかけるかもしれませんが、今年もよろしくお願い申し上げます。
2024年1月5日 一般社団法人カリタス南相馬代表理事 幸田和生
「見さ来ぅ南相馬!」
「見さ来ぅ南相馬!」というのは、2024年のカリタス南相馬のキャッチフレーズです。「みさこぅ」と読みますが、浜通りの言葉で「見においで」という意味です。カリタス南相馬の前身であるカリタス原町ベースは、全国から東日本大震災被災地に来るボランティアの方々に宿と食事を提供するために始まりました。その後、ボランティアだけでなく、特に原発事故の被災地の現状を知りたいという方々も受け入れて、その方々の案内をするのも、わたしたちの重要なミッションと考えるようになりました。しかしこの3年間、新型コロナウイルス感染症の流行によってカリタス南相馬では宿泊者の受け入れをすることがほとんどできませんでした。2023年の夏は大幅に制限を緩和することができて、多くの人、特に高校生や大学生のグループを受け入れることができました。そこで、2024年は、以前カリタス南相馬に来られた方で、久しぶりに福島に行ってみようかという方、またボランティア活動をしてみようという方、さらにまだ行ったことはないけれど福島県浜通りのことを見たい・知りたいという方を大いに歓迎したいと考えています。
福島の原発事故は過去のことではありません。今も福島第一原発には大量のデブリが残ったままで、その処理や廃炉の目処は立っていません。一方で周辺地域の状況は年とともに変わってきています。ALPS処理水の海洋放出の問題、除染によって出た除去土壌の再利用の問題は決して福島だけの問題ではありません。政府が原発の再稼働や増設・新設に向けて動き始めた今だからこそ、原発事故の影響が今もどのように続いているか、あの震災と事故から学ぶべきことは何なのか、自分の目で見て考えることが大切だと感じています。
来てくださった方々には、震災からの復興状況や原発事故の現在だけでなく、福島県浜通りの四季の風景、この地ならではのイベントや美味しいものなども紹介していきたいと考えています。
「ミサコゥ」という言葉は、カトリック信者にとっては「ミサに来てね」と聞こえるかもしれません。そう受け取ってくださっても良いのです。この地でミサにあずかり、この地で祈ることに大きな意味があると感じています。「巡礼のつもりでここに来ました」と言われる方も少なくありません。福島は自然との関係やわたしたちの生活を見つめ直す回心の地でもあると言えます。
東京駅から南相馬市原ノ町駅まで、常磐線特急で約三時間半。どうぞ皆さま、「見さ来ぅ南相馬」、
975-0006 福島県南相馬市原町区橋本町1-15 0244-26-7718 / FAX 0244-26-8007https://caritasms.com/ https://www.facebook.com/caritas.minamisoma/
これからも、カリタス南相馬の活動から学んでいこうと思っています。皆さんも、カリタス南相馬の活動にご協力ください。
2024年5月24日 市川一宏
投稿日 24年05月24日[金] 3:19 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,教会関連 ,災害支援
1.「買って応援~」
吉村誠司さんより、情報が届きました。
「能登半島地震で壊滅的な被害を受けた輪島市中島酒造と小松市東酒造(杜氏実家は珠洲市で全壊)のコラボ新酒が4月22日から限定販売開始します。宜しくお願いいたします。 https://sake-5.jp/sakenews/50605/ 」
2.葛飾区社協より
葛飾区社協の避難者への対応は、支援の有力な方法として、私は評価しています。添付させて頂きます。
3.全社協より
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
■ 全社協からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆令和6年5月孤独・孤立対策強化月間 「民生委員・児童委員」「老人クラブ」
「社会福祉協議会」による全国キャンペーンについて
(全社協 地域福祉推進委員会)
内閣府では、令和6年4月1日からの孤独・孤立対策推進法施行を契機とし、孤独・孤立対策官民連携プラットフォームを中心に、孤独・孤立についての理解・意識や機運を社会全体で高めていくため、毎年5月を強化月間として集中的な取り組みを実施することとなりました。
こうした状況を踏まえ、全社協地域福祉推進委員会では、民生委員・児童委員、老人クラブ、社会福祉協議会が一体的に孤独・孤立対策への取り組みを一層推進することを目的に、広報・啓発活動や支援活動の展開を呼びかけることといたしました。
【詳 細】下記URLをご覧ください。
◆全国で「福祉の就職総合フェア」を行います(4月、5月分)
(全社協 中央福祉人材センター)
都道府県福祉人材センターおよび福祉人材バンクにおいて、福祉のお仕事に関する就職総合フェアを行います。各都道府県内の求人事業所がブースを出し、福祉の職場や仕事内容の説明をしたり求職者の質問に直接お答えします。その他、福祉の仕事や就職活動の理解を深めるセミナーや事業所職員によるトークセッション、介護ロボット展示、転職時の資金の貸付事業(介護分野就職支援金貸付事業等)の案内等、さまざまなプログラムが行われています(開催都道府県により内容は異なります)。
下記URLより詳細が確認できますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。ご不明な点は、各センター・バンクにお問合せください。
【掲載内容】2024年4月、5月分
【詳 細】下記URLをご覧ください。
https://www.fukushi-work.jp/news/detail_67.html
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
■ 他団体からのお知らせ等
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆『和田敏明 地域福祉実践・研究のライフヒストリー』刊行のお知らせ
―社会福祉協議会の変遷とこれからへの期待及び提言―(香川県社会福祉協議会)
本書はこれまで50年余りにわたり社会福祉協議会や地域福祉の実践を牽引し、理論形成に尽力され大きな功績を残しつつ、今なお後進の指導に精力的に取り組まている和田敏明先生と大橋謙策先生の対談記録です。これまでの取り組みを回想いただくとともに、地域共生社会時代における社協組織のあり方や今後の社会福祉の展開について、3回にわたって対談いただいたものを取りまとめました。また、巻末には対談にともなう社協関係資料(約100頁)も掲載しています。社会福祉協議会の基本要項改正の議論が行なわれている今日、これからの社協のあり方や方向性を考えるうえでの必読書です。
【編 著】和田敏明 著
越智和子、大橋謙策、日下直和 編
【体 裁】B5判 198頁
【価 格】1,500円(税込)
【発 行 日】2024年3月31日
【発 行 元】香川県社会福祉協議会
【購入・詳細】下記URLをご覧ください。
https://www.kagawaken-shakyo.or.jp/news/entry-446.html
【問合せ先】香川県社会福祉協議会 総務企画課
TEL:087-861-0545 FAX:087-861-2664
◆〔4/30応募締切〕第二回「令和6年能登半島地震による災害支援活動助成」のご案内
(公益財団法人風に立つライオン基金)
令和6年能登半島地震発災から3か月以上が経過しました。風に立つライオン基金では、長期化する支援活動を応援するため、2回目の「災害支援活動助成」の募集を開始しましたのでご案内します。
【助成対象団体】災害ボランティアセンターが設置された地域で活動する当該県内の団体(任意団体含む)
※反社会的勢力と関わりがないこと。特定の政治や宗教の普及を目的としないこと。
※県外ボランティアの受け入れをしている地域は対象に含みます。
※令和6年能登半島地震における災害救助法が適用された新潟県、富山県、石川県および福井県の35市11町1村(内閣府防災担当 令和6年1月1日時点)とします。
【助成対象活動】緊急支援・復旧支援・心の支援・ボランティアへの支援活動など
※当該被災地の災害ボランティア・センター等と連携された活動であること。
【助成対象費目】災害支援活動に資する直接経費(交通費、宿泊費、重機・資機材リース費、消耗品費、人件費の一部、等)
※全ての支出に対して領収書等の証憑提出が必要です。
【助成金額】1団体あたり最大30万円
【助成対象期間】2024年4月1日(月)~2024年9月30日(月)まで
【締 切 日】2024年4月30日(火)
【詳細・申込】下記URLをご覧ください。
https://lion.or.jp/news/news/20240408.html
【問合せ先】公益財団法人風に立つライオン基金 助成事務局
E-mail: support@lion.or.jp
4.東社協より
さて、当協議会では、社会福祉法人による地域公益的な取組みを広く共有・発信する場として、先日「新宿アール・ブリュット企業展2023」を取材し、YouTubeチャンネルで公開を開始しました。より多くの方にその実践をご覧いただきたく、関心のある方は、ぜひご覧いただけますと幸いです。
▼「新宿アール・ブリュット企業展2023」動画視聴はこちら!
https://clk.nxlk.jp/m/NjMV9jHwE
また、より一層の活動促進と地域公益活動を始める上での手がかりとなるよう、実践事例からポイントやヒントをまとめたヒント集を発行しました。
どの取組みも法人・施設も地域のニーズを知ることにより、多くの住民と繋がり、世代を超えて新しいコミュニケーションを生みだしています。ぜひご覧ください!
▼ヒント集閲覧はこちらから!
https://clk.nxlk.jp/m/ZZygGlwvE
<東京都地域公益活動推進協議会 事務局>
社会福祉法人東京都社会福祉協議会
福祉部 経営支援担当(阿部)
〒162-8953新宿区神楽河岸1-1
TEL:03-3268-7192 FAX:03-3268-0635
E-mail:tky-koueki@tcsw.tvac.or.jp
投稿日 24年04月21日[日] 10:08 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連
私に届いた最新の情報をお届けします。
1.吉村誠司さんの活動
能登半島被災地、特に輪島市で活動している吉村誠司さんは、FACEBOOKを開設しています。新しい現地の情報をお知りになりたい方は、どうぞコンタクトして下さい。
2.民生委員児童委員活動
3月13日に発信した都道府県・指定都市民児協宛のメールニュースとして公表しているもの全民児連事務局から頂きました。
https://www.dropbox.com/scl/fi/u7vlkb6guy4k0jqed3zeu/5.pdf?rlkey=kagwvvsh4qj9ap5adtaxs22lc&dl=0
3.東社協地域福祉推進委員会(令和6年3月8日)
各種別の部会から委員が参加している地域福祉推進委員会で把握した、能登半島地震をふまえた各部会で取り組んでいること
https://www.dropbox.com/scl/fi/dn4oss56vuled0shx76m6/3.8.pptx?rlkey=ftsd6rghrmnaeetccatpc02tt&dl=0
投稿日 24年03月29日[金] 5:53 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援
2024年1月1日に発生した能登半島地震から2ヶ月を過ぎましたが、依然、先行きが見えない状況にあります。また、どのような支援が可能か、適切なのか、能登半島、特に奥能登の住民の方々の要望にどのように応えていくべきか、気持はあるのですが、戸惑っているのが、私の正直な気持で、今できることをしている現状です。
そして、これからも続く能登半島地震の支援にどのように関わり続けていくか、私たちは、問われています。
他方、能登半島震災の問題は非常に深刻ですが、2月に開催された高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の最後の会議で、私は以下のように申し上げました。「人材確保、養成等に明らかな決定打を示せず、私は閉塞感を感じています。今、必要なことは3点。自らの取り組みを振り返ること、これからの地域、社会の姿を描くこと、協働した取り組みを目指すこと。委員の皆さんもその主体です。この有力な自治体でできなければ、どこの自治体でもできないと思います。」と。
私は、現在、複数の市町村、都府県の自治体や社協と関わりをもっています。能登半島地震の被災地と共通の問題をもっており、被災地支援と各地域の孤立予防、災害対応のまちづくりの取り組みを、互いに学びながら進めていく必要があると考えています。そして今は、どこで災害が起こっても不思議でない状況にあります。できることから始めていきたい。今後とも、いろいろ教えて下さい。
2月末より、神奈川県のブロックで現地に派遣された卒業生からの情報
発災より47日経過していたので、家屋の状況は発災時より厳しかなっている(段々傾いている等)というお話が被災された方々からちらほらと聞かれました。今後、大きい余震で倒壊しないか、心配です。
実は右腕の肘に痛みがあり、片手で10トン爪ジャッキ(25kg)以上が持てなくなったので、輪島ベースを仲間達に託し、鍼灸院通いと家庭内雑務にて戦線離脱~(泣)。帰路、液状化被災地の金沢市近く内灘町を仲間案内で廻り石川県を離れたが、被害は予想以上にかなり深刻だった・・・
とフェースブックに書かれていました。心配して、私は以下のことを書き込みました。
吉村さん、おはようございます。能登半島に真っ先に駆けつけ、以降現地で支援に取り組んでおられたので、体調に心配していました。まずは体調の回復に努め、今まで、そして今後求められるの実践を整理し、私たちに知らせて頂けませんか。私には、様々な情報が入っており、全国の友人に情報を提供しています。吉村さんの活動も伝えてきました。あなたの発言はとても貴重です。ちなみに、宮城県のI 市のAさんが現地に入っていると聞いています。
これからも、応援して下さい。
3.長野県社協からの情報提供
『令和6年能登半島地震に係る支援方針』 長野県災害福祉広域支援ネットワーク協議会(災福ネット) 社会福祉法人長野県社会福祉協議会
https://www.dropbox.com/scl/fi/ci484elurdlwuz4l1fifm/13.docx?rlkey=i9a0tt9isqxgkvwotictp0fuv&dl=0
4. 『災害から地域の人びとを守るために=災害福祉支援活動の強化に向けた検討会報告書』全社協
https://www.shakyo.or.jp/bunya/saigai/teigen/20220331/index.html
5.ぼうさいこくたいポスター
https://www.dropbox.com/scl/fi/u9fub5s8gaggsiollou0r/.pdf?rlkey=tc4ccax3v7rfvxj38chxkglt6&dl=0
投稿日 5:51 PM | カテゴリー: カテゴリ無し ,共助社会づくり ,災害支援 ,社会福祉関連
次のページ »