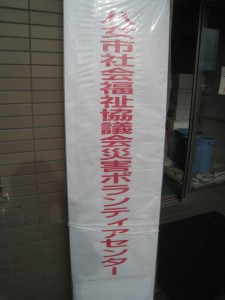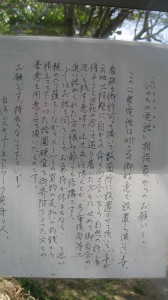社会福祉関連
報告にあたって
地域における孤立や孤独、虐待、そして貧困等の問題を解決するために、民生委員・児童委員、主任児童委員(以下、民生委員と言う)への期待が高まっています。しかし、民生委員は、5つの壁に直面していると思います。
①<先行する期待の壁>地域の問題を民生委員だけで解決することは無理です。それぞれの地域は、民生委員、専門職、ボランティア、住民が協働して課題に取り組むために、それぞれの具体的な役割を確認することが不可欠です。
②<多様な役割の壁>どこまで、どのような活動したら良いか、民生委員自身が戸惑うことがあります。それぞれが、「したいこと」「できること」「求められていること」を確認し、活動のための知識と技術を高めていくことが必要です。
③<地域の理解の壁>多くの住民は、民生委員活動には長い歴史があり、先人の重要な働きが地域を支えてきたという事実、現在も民生委員活動が地域問題を予防解決しているという現実を知りません。民生委員も、自分の活動を説明し、地域の理解を広げることが求められています。
④<日頃の活動の壁>民生委員は、日々、切磋琢磨しながら活動をしています。同時に自分だけで課題を背負い、活動の目標と意味を見失うこともあります。民生委員同士、関係者と共に、活動を振り返る機会があり、活動の意味を再確認できる場が大切です。
⑤<活動を支える体制の壁>活動を支援する体制を確認しなければなりません。民生委員・児童委員協議会において新任民生委員を支える体制、同協議会において民生委員、同協議会担当者、専門職がともに情報交換し支え合う体制を築くことが活動の前提です。
本報告は、研修を通して、以上の課題を解決することを目指しました。
①多様な活動をバックアップする研修:「発見」「相談」「地域連携」「啓発」「民生委員・児童委員協議会の運営、活動の記録」という項目に分けています。
②スキルアップできる研修:講義と受講者の参加型研修を組み合わせ、「学ぶ」→「気づく」→「描く」→「変わる」サイクルを取り入れています。
③啓発を目的とする研修:研修を通して、民生委員が住民の福祉理解を促進し、地域における福祉を考える機会を提供することを目指しています。
④アイデアを大切にする研修:活動は地域の特性等によって異なります。民生委員それぞれが日頃工夫しているアイデアを共有することを大切にしています。
⑤活かす取り組み:民生委員が自分の強みと課題に気づき、強みはより強化し、課題は改善していくことのできるプログラムにしています。
今日の委員活動に関する負担の増大が指摘されるなか、委員同士の「助け合い」、「支え合い」が重要となっており、そうした人間関係づくりの面からも研修の重要性が増しています。本研修体系の実現により、委員の皆さまの活動支援につながることを切に願っています。
平成25年3月 民生委員・児童委員研修のあり方に関する検討委員会
委員長 市川一宏
民生委員研修体系
ワークブック
事例集
投稿日 13年07月15日[月] 11:37 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
このたび、長野県社会福祉協議会『信州系まめってぇ読本』が発行されましたので、お届けします。 本書は、「小地域における地域支え合い体制づくり推進のあり方や普及に関する研究委員会」が、1年間をかけて、長野県内の地域福祉活動を検証し、その実践から学んだことをまとめたものです。私は委員長でしたが、委員の方々、長野県社会福祉協議会職員の熱意とネットワークによって、さらには各地区の社協、NPO、住民、当事者のご協力によって発刊することができました。長野県の地域福祉の成果と地域力をご覧下さい。この一つひとつの取り組みが、明日の社会を切り開いていくと思います。 確かに、それぞれには地域性があり、活動内容、活動までの取り組み等は違いますが、しかし、いくつかの共通点があることを学び、全国各地で参考にして頂ければと思っています。 私も仕事として長野県を訪問してから、20数年になるでしょうか。それ以降、長野県の社会福祉協議会や福祉関係団体、地域福祉を推進して来られた方々に育てられ、私の今があります。心より、感謝しています。 2013年7月1日
長野県支え合い
投稿日 11:26 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
2012年夏、福岡県市区町村社会福祉協議会会長・常務理事・事務局長研修会の講演の機会を頂きました。私にとっては、お世話になった方々で、講演の機会を頂いたことは、本当に感謝でした。 しかし、2日間の予定は、福岡県内の水害の影響もあり1日に縮められました。要項は以下の通りです。 平成24年度市区町村社会福祉協議会会長・常務理事・事務局長研修会
1 趣 旨 昨年3月に発生した東日本大震災では、地域のつながりの重要性が再認識されるとともに、NPOや市民団体などによる活発な災害ボランティア活動が展開される中で、その拠点となる災害ボランティアセンターの運営とコーディネート役を担う社協の存在や役割も改めて見直される機会となりました。 一方で、少子高齢化の進行などにより地域社会や家族形態が変容するなか、社協の強みであるネットワークを活かした地域福祉活動の充実が求められています。 さらに、地方財政が逼迫するなかで、補助金・委託金の削減により社協経営は厳しさを増しており、組織体制の強化や事業の活性化を図ることもままならない状況ですが、地域主権改革等中央情勢を注視しつつ、地域のニーズの変化に柔軟に対応していくことが重要となってきています。 本年度は、社会福祉諸制度の動向を踏まえ、東日本大震災を通して見えてきた社協の役割や今後の展望等について共通認識を図ることを目的に開催します。
2 主 催 社会福祉法人 福岡県社会福祉協議会
3 開催日 平成24年8月1日(水)
4 会 場 ホテルパーレンス小野屋
5 参加対象 市区町村社会福祉協議会会長、常務理事、事務局長
6 内 容
11:00 〔開 会〕
挨拶・オリエンテーション
11:10 〔報 告] 「市区町村社会福祉協議会の現状と課題」 報告者 福岡県社会福祉協議会
11:25 〔事業説明〕 市区町村社協に関する本会事業の説明 説明者 福岡県社会福祉協議会
13:00 〔実践報告〕 テーマ①「災害に備えた関係機関・団体との連携について」 報告者 大刀洗町社会福祉協議会 事務局長 村山 真知子 氏
テーマ②「これからの人材育成、業務改善と効率化」 報告者 宮崎県都城市社会福祉協議会 総務課副参事兼法人係長 櫻田 賢治 氏
14:10 〔講 演〕
「東日本大震災を踏まえ、今後の社協のあり方を考える」 講師 ルーテル学院大学 学長 市川 一宏 氏
事業説明の時に、私は現地に到着しました。研修会は、福岡県の市町村が被災しており、2日も予定を1日に短縮されることになりました。事業報告で、福岡県内の被災地に、福島県内の職員が応援に来ることを知りました。しかもそのメンバーが、よく知っている職員と分かり、私は、講演の終了後に、福島から来た職員の方々に会いたいとお願いし、福岡県八女市社会福祉協議会災害ボランティアセンターを訪問しました。そこで、福島県社協の職員、福島県相馬市ボランティアセンター所長等とお会いしました。皆さんは、九州からの東日本大震災への応援に対して、感謝し、自分たちができることをしたいと、福岡県内のもっとも被害が大きかった八女市に、何時間もかけてやって来ました。私は、福岡県内の地元の焼酎を渡し、健康が守られ、ボランティアとして、精一杯頑張ってほしいと、伝えました。




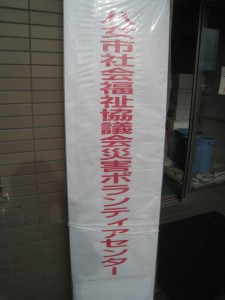
下の写真は、福島県相馬市の被害に遭った海岸、そしてボランティアセンターの建物です。私が訪問した2012年4月には、センターの壁に、絵手紙が飾られていました。それは、少しでも早い復興を願い、送られてきたその一枚一枚に込められた思いに感動しました。そして、支援に対する感謝をもって、福岡県八女市に来た皆さんの思いを忘れることはできません。
10日近いボランティアを終え、福島に帰った彼らから、連絡がありました。「無事に帰りました。活動を終えた後、みんなで飲みました。ありがとうございました。」という電話に、私は、助け合って生きること、恩を返し続ける姿に、日本が失った絆、個々への思いやり、自然な助け合いの姿を見ました。日々、その絆を紡いでいくことが、日本の明日を切り開きます。



当日は、朝倉市のホテルパーレンス小野屋に泊めて頂きました。朝倉市のこの場所は、大雨の影響を受けた土地です。いち早く、被害に対する対応ができた地域です。私が宿泊したようなすばらしいホテルがあるのですが、必ずしも街自体がすべて活気があるわけではありません。
しかし、朝早く、部屋から見ていると、一人の若者が、自転車に乗って、目的地に急ぐ姿を見ました。私は、当たり前の日常生活に感動しました。一人ひとりが、自転車に乗り、それぞれの目的地の向かって、必死に歩んでいる。その心があれば、日本の復興は可能だと思います。今、そのエネルギーが、日本には必要とされていると思っています。


投稿日 13年04月28日[日] 10:10 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
「私は、必ずあなたと共にいる」というメッセージを届け続ける働きを紹介します。 私は、昨年、藤藪庸一牧師にお会いしました。来週、訪問する白浜レスキューネットワークのリーダーです。「自殺しようと苦しむ方々を何とかして助け、人生に希望を失っている方々に、もう一度人生をやり直そうと思ってもらえるように関わっていきたいと願って」、NPO法人白浜レスキューネットワークが立ち上げられました。
和歌山県南部西海岸にある白浜三段壁(さんだんべき)は、断崖絶壁の名勝ですが、自殺者があとを絶ちません。保護した件数は、年間30件を超えるそうです。相談電話は、三段壁以外からもあり、1260件を超えるそうです。また、保護した方々が自立するには、自己破産や就職活動などとともに、もっとも大切な、心身の回復が不可欠です。これらの問題を解決していくために畑を作り共同生活をしていると、藤藪牧師は言われていました。
藤藪牧師は、著書(藤藪庸一『<自殺志願者>でも立ち直れる』講談社)でこう書かれています。「私が何よりもうれしいのは、<略>共同生活を経て、自立していくことです。<略><教会に遊びにおいで><いつでも連絡をちょうだい>自立していく際には、また会えることを祈って送り出します。<略>私との関係を続けて連絡をくれ、そしてなんといってもその人が自立して生き生きと頑張っていることがわかると、私は励まされます。」 今、必要なことは、「共にいる」存在があることを、希望を失いかけている方々に届けることではないでしょうか。「共にいる」働きが、明日の社会を切り開いていくと、私は確信しています。」 この文章は、2012年度卒業式で私が話したメッセージの一部です。機会があって、実際に働かれている場で、藤藪牧師にお会いしてきました。午前に、弁当を調理し、かつ喫茶店として場を提供しているCOMBを訪問しました。先生は、調理に追われておられました。当日は、たくさんの弁当の注文があったそうです。生きていくことに絶望し、当地を訪れた人々が、最後の決断の前に、助けを求めてくることができるように、いつも心を開いている人がいる。絶望の中にあって、救いのみ手を差し伸べようとする働きがある。これから、未来に向かって再び歩もうとする仲間がいる。


白浜三段壁に行きました。本当にすごい絶壁。そして2枚の看板と電話ボックスに張られた紙を見て、驚きました。白浜レスキューネットワークのメッセージが置かれていたのです。




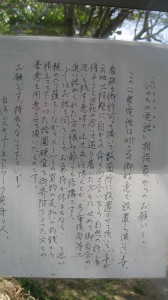
藤藪先生の白浜バプテスト白浜教会


投稿日 1:38 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
以下の要領にて、ボランティア講演会が開催されました。
◆日時 平成25年3月9日(土)
◆場所 甲府市総合市民会館 芸術ホール
◆定員 500名
◆演題 「明日の社会を築く~地域の絆をつくるボランティア活動~」
◆講師 「ルーテル学院大学 学長 市川 一宏 氏」
◇主催 甲府市社会福祉協議会(甲府市ボランティアセンター)
甲府市ボランティア団体連絡協議会
◇後援 甲府市
◇問合せ 甲府市ボランティアセンター
今、ボランティア活動の推進に以前の勢いがなくなっている気がしています。ボランティア活動の必要性はあり、その意味はわかっていても、参加する人が広がってきていません。多くの地域で、狭い個々の生活の中に目が向けられ、「明日を共に築く」姿が見えにくくなっています。
確かに、社会に閉塞感があります。明日への不安が先立ち、それぞれが今を生きることに精一杯です。しかし、そこには、2つの選択肢があると思っています。一つは、先が見えない故に、今を生き続けるという選択肢。もう一つは、先が見えない故に、立ち止まり、あきらめるという選択肢。
今回の主催者の挨拶を聞いて、私が勇気づけられました。紹介します。このような一つひとつの取り組みが、明日を切り開きます。「始めることから始めませんか」
1.主催者挨拶 甲府市ボランティア団体連絡協議会 市川会長
皆さん こんにちは
甲府市ボランティア団体連絡協議会の市川と申します。
本日は、甲府市社会福祉協議会と、私ども甲府市ボランティア団体連絡協議会との共催によりますボランティア講演会に、ようこそおいでくださいました。
ありがとうございます。
この講演会は、主催者の双方とも、平成24年度の年間の事業計画には入っていませんでしたが、このたび、山梨県新しい公共支援基金事業を利用してのボランティア活動をすすめることを目的として企画いたしました。
講師の市川一宏先生には、後程ご紹介させていただきますが、ルーテル学院大学の学長として、大学および大学院で教鞭をとる傍ら、多くの学会の長としてのお仕事をこなし、また本日のような全国各地から招かれてのご講演、ご指導など大変お忙しい時間を割いて、私どものためにお越しくださいました。
ありがとうございます。
先生をお招きするに当たりまして、私どもが研修事業として参加しております、全国ボランティアフェスティバルに、先生は毎年招聘され、ご専門の分野で分科会を担当されています。昨年開催されました全国ボランティアフェスティバル三重での分科会では「平成24年度ふれあい・いきいきサロン全国交流会 広げよう地域の絆・増やそう地域の笑顔」をテーマに、コーディネーターとして、全国から参加者と交流されましたが、私たちの1泊2日の日程では、午前、午後と1日かけた先生の分科会には、残念ながら参加できませんでした。
今日は先生から直接お話をお伺い、学習をしたいという強い思いがありまして、先生にお越しいただくことになりました。
先生の業績につきましては、ルーテル学院大学のホームページに紹介されていますが、先生の研究室のページには、先生が自ら投稿された文章を見ることが出来ます。全国各地で公演をされた内容がたくさん出てまいりますが、その一つ一つが先生にとりましては、強く印象に残ったことばかりだと思います。
今日はボランティア団体のメンバーや地区社協、自治会、民生児童委員、学生の皆さん、そして、これからボランティア活動を始めようという思いの方など多くの方々のご参加をいただいております。
この講演会を聞いて、皆さん一人ひとりが、今後どのような役割を持って地域の絆をつくり、活動につなげていけるか、大いに期待しているところですが、先生にも今日は良い講演会だったと心にとめていただきますよう、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
2.社会福祉協議会会長挨拶
本日は、お忙しい中、多くの皆様にこのボランティア講演会にご参加をいただき、誠にありがとうございます。
皆様もご承知のとおり、高齢化がものすごい勢いで推進しております。さらに、世の中は景気が長い間低迷しており、社会情勢が誠に厳しく、失業者が多く、正規雇用が少ない非常に厳しい状態にあります。
さらには2年前には東日本大震災があり、そのために生活に難儀している人々が大勢おります。こういった中で多くの人達がボランティアに精を出しており、本日会場にいらした方々の中にもいろいろな分野でボランティアに精を出している方々が大勢いらっしゃると思います。非常に尊い存在であります。
さらに、いつ来るかわからないと言われております、東南海地震がもし起きた場合は、更に多くのボランティアの手が必要になると思いますが、日本の福祉はボランティアに頼りすぎているようにも思えます。
最近よく聞く「絆」という言葉がありますが、隣近所でお互いに助け合っていくことの出来る世の中にしなければならないと思います。
さらに、今ここにいらっしゃる方々は年配の方が多く、自分自身の高齢化に伴い、後継者がなかなか出てこないことを心配している方も多いと思います。
自分たちの世代は頑張っていても、後を継いでくれる人がいないことを非常に心配しております。
このような中で、甲府市社協では、いきいきサロンや配食サービスを続けて、地域の活性化やお年寄りの元気を保つために一生懸命手を尽くしております。しかし、ボランティア不足もあり、なかなか思うようにいかないのが現状です。
ボランティアは要求されていますが、まだまだ不足しています。この状況をどうすれば良いのでしょうか。皆さんが温かい手を差し伸べる、温かいまなざしを向けるだけではどうにもなりません。一人ではそれ以上の事はできないと思いますので、やはり隣近所の人と手を取り合っていくしかないと思います。
本日は、ルーテル学院大学の市川学長の講演でございますが、甲府市ボランティア団体連絡協議会の皆様と甲府市社協職員が早朝からこの会場設営を頑張っておりました。そのことにお礼を言いたいと思います。
今日は市川学長のご講演を聞いて、さらにボランティアの輪が広がり、相互が熱くなるように甲府市の事業が進んでいけば良いと思っております。
簡単ではございますが、私からのあいさつとさせていただきます。
本日は、よろしくお願いします。
3.甲府市ボランティア団体連絡協議会の現状とこれからの展望
甲府市ボランティア団体連絡協議会は、平成6年度(平成7年2月)に発足以来、19年が経過し、今年20年目を迎える。
主な事業は、「甲府地区ボランティア交流会ボランティア博」で、平成14年度は、「全国ボランティアフェスティバルやまなし」の中で行われ、それ以前は講演会が中心で平成15年度から(交流会及び活動展示だけでなく)舞台による発表が加わった。当時は、甲府地区ボランティア交流会という名称で、当団体の加入団体による交流会だったが、平成20年度からは、市内大学交流ネットワーク(市内4大学のボランティアサークル)、甲府市社会福祉協議会の2団体が加わり3団体共催事業となり、「甲府地区ボランティア交流会ボランティア博INこうふ」に名称を変更した。
「甲府地区ボランティア交流会ボランティア博」は、5年目を迎え、ボランティア団体だけでなく、一般の市民にも関心を持っていただくイベントとして定着してきている。
次に、研修会の一環としての全国ボランティアフェスティバルは、当団体からの参加者が毎年減少している。
赤い羽根共同募金、歳末助け合い募金街頭募金への協力は、甲府市社協が事務局を担う、山梨県共同募金会甲府市支会からの期待が大きい事業だが、参加者・募金額とも停滞気味である。
県民の日記念事業の中での、やまなし市民活動交流フェスタにも毎年参加しているものの当団体の活動紹介事業としての機能はあまり果たせていない。
当団体の実施事業は、努力の割には報われないという部分もあり、またボランティア自身の高齢化が要因となり、当団体への加入数も減少してきている。
甲府市社協には、ボランティア基金という財源があり、当団体に新規加入するボランティア団体には優先的に活動資金としての助成をしてきた経過があるため、今後慎重に検討した上で有効に活用できれば新規団体加入に有効ではないかと思われる。また、甲府市ボランティアセンターに団体登録しており、当団体に未加入のボランティア団体についても新規加入の勧誘等に努める。
当団体の組織に係る構想として、甲府地区ボランティア交流会ボランティア博にて高齢者・障害者・子供コーナー等のジャンルに分けてコーナーを設けたが、このグループをそのままの活動に繋がる部会として活動したら各団体同士の理解も深まりイベント等がやりやすくなると思われる。
新しい取り組みを予算がないから実行出来ないではなく、目的を見つけて、どのようにすれば実現できるかを考えることが大事だと思われる。
平成25年3月18日 甲府市ボランティア団体連絡協議会
会 長 市 川 孝 次
投稿日 7:03 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
宮崎県社協は、全国で、実力のある都道府県社協の一つです。私は、20年近く前、全社協地域福祉部の紹介で、県社協の経営基盤強化のために、作業委員長として頻繁に宮崎県を訪問しました。その時より、宮崎県社協は、市町村社協と協働して、各地域の地域福祉の推進のために、過疎サミットやさまざまな企画を打ち立て、宮崎県内における重要な役割を担ってきました。私も一緒に各地を訪問しましたが、その経験が、私の地域福祉に関する考え方に影響を与えています。 全国ボランティアフェスティバルを開催した時には、県と協力して、数万人の参加者を記録しました。私は、福祉のまちづくりをテーマに、分科会を担当しましたが、当時、紀宮妃が聞きに来られたことは思い出です。 今回は、地域福祉推進フォーラムです。登場する事例は、活動実績のある、宮崎県内でも有数の地域です。詳細を述べることはしませんが、その実績から学ぶことが多いと思います。
地域福祉推進フォーラム
テーマ「地域のつながりの再構築」
1 趣 旨
少子・高齢化の急速な進行や景気の低迷、人間関係の希薄化や家族機能の低下等により、孤立死や自殺、貧困や低所得、育児不安、介護、子どもや高齢者への虐待、障がい者の地域生活移行、引きこもりなど人々の生活課題が多様化、複雑化、高度化してきています。 これらの生活課題に対して、平成19年に厚生労働省に設置された「これからの地域福祉のあり方に関する研究会」がまとめた報告書「地域における『新たな支え合い』を求めて-住民と行政の協働による新しい福祉-」では、特に身近な「地域社会」の中での「つながり」をどのように再構築していくかが、これからの地域福祉の課題であると指摘しています。 そこで、本フォーラムでは、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる地域社会を目指して、地域のつながりを再構築し、支え合う体制を実現するための方策について、関係者の共通理解と更なる連携の促進を図ることを目的として開催します。
2 主 催 宮崎県 社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会
3 日 時 平成25年3月1日(金) 午前10時から午後3時30分まで
4 会 場 フェニックス・シーガイア・リゾート シーガイア・コンベンションセンター4階(蘭玉の間) 宮崎市山崎町浜山
5 参加対象 自治会等役員、民生委員児童委員、ボランティア・NPO団体、市町村行政職員、市町村社会福祉協議会職員、社会福祉施設職員、その他関心のある方
6 プログラム
・趣旨説明 宮崎県社会福祉協議会 地域・ボランティア課長 坂本 雅樹
・基調講演「これからの地域福祉とまちづくり」ルーテル学院大学学長 市川一宏 氏
住民が直面している福祉ニーズや地域の生活課題とは何か。また、地域づくりに必要な介護予防、自立支援、住民参加の視点をもとに実践事例を交えながら、これからの地域福祉とまちづくりの方策について学びます。
・パネルディスカッション ルーテル学院大学学長 市川一宏 氏
地域のつながりの再構築 ~住民の暮らしを支えるための仕組みづくりと協働」
誰もが安心して暮らせる地域づくりを進めていくためには、同じ地域に暮らす住民同士だからこそできる発見や気づき、見守りや支えあいの取組みとともに、同じ地域の中で住民の地域福祉活動を支援したり、専門的な相談援助に取り組む機関との協働が必要です。このパネルディスカッションでは、日常生活圏域において住民や地域包括支援センター、社会福祉協議会、地区社会福祉協議会がそれぞれの立場で地域福祉の推進をめざし、協働していくための視点や方法について、専門家の助言をいただきながら考えます。
・高鍋町正ヶ井手地区自治公民館 館長 河野 幸雄 氏
「福祉ネット部」を中心に顔の見える活動にこだわり、高齢者の見守り、介護予防や配食サービス等を積極的に展開。平成15年12月に国の介護予防等拠点整備補助事業を利用して木造平屋を増築し完全バリアフリー化。介護講習のほか、ストレッチ体操、ひな人形づくり、レクリエーションなど幅広く利用されており、住民同士の交流をすすめています。
・宮崎市小松台地区社会福祉協議会 会長 川俣 勲 氏
高齢者・障がい者・母子家庭・乳幼児のいる世帯を対象に、地域の中高年で組織した有償ボランティアが、高齢者の日常生活の困りごとについて、簡単な庭木の剪定、草取り、買いものの持ち帰りなどを行う「お助けマン・ウーマン事業」を展開するなど、地域関係の希薄化防止への活動を行っています。
・日向市財光寺地域包括支援センター センター長 梅田大介 氏
地域包括ケアシステムの中核的機関として地区の課題や問題点を区長、民児協、高齢者クラブ、病院、薬局、社会福祉協議会、行政等で構成する地域ケア会議に積極的に取り組み、またアウトリーチによる高齢者の実態把握、介護予防教室、ふれあいいきいきサロンへの関わり等を積極的に行っています。
・日南市社会福祉協議会 事務局長 冨山 生穂 氏
市内9地区に地区社会福祉協議会や地区福祉推進協議会を設置し、また、福祉推進委員総数1,001名を委嘱して、公民館等を拠点とした、見守り活動、ふれあいいきいきサロン、ひとり暮らし高齢者のふれあい昼食会を行うなど住民の地域福祉活動を支援。平成23年には市と協働して「地域福祉推進計画」を策定するなど、日常生活圏域で住民の地域生活を支える仕組みづくりを進めています。



投稿日 13年03月09日[土] 8:02 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2013年2月、花巻で行われた民生児童委員協議会会長・副会長研修会にお招きいただき、「住民参加による地域福祉の推進と民生委員・児童委員が担う役割」というテーマで講演させていただきました。東日本大震災で死亡した民生委員は、25名で、うち、主任児童委員が4名で、内訳は、宮古市2名、山田町4名、釜石市4名、大槌町4名、陸前高田市11名でした。
私は、亡くなられた方々のご冥福をお祈りし、今後の活動に参考にしていただくこと。そして激励したい思いで、岩手県の仕事をお引き受けいたしました。
海岸沿いは、深刻な被災を受け、今も復興が進んでいません。また過疎の問題も深刻で、雪の中で孤立している方々がたくさんいます。その方々を支え、見守る責任を担う400名を超える方々が集まられました。
私の思いが、皆さんにどれだけ伝わったかわかりません。しかし、会場は、熱心に聞いて下さる方々で、燃えていました。講義が終わり、外を見ると、雪が積もり、冷え切っていました。この対照的な環境を御覧下さい。
岩手県の民生委員の方々の底力を見て、励まされたのは、私の方でした。ありがとうございました。


投稿日 13年03月03日[日] 6:11 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
長野県フォーラム
長野県社協『地域でまめに暮らそうフォーラム』
2012年度、長野県社会福祉協議会は、「小地域における地域支え合い体制づくり研究委員会」を発足させ、地域福祉活動の本格的検証に入った。そして、委員会を重ね、今回のフォーラムを開催することができた。
その後、報告書とともに、事例集、DVDを刊行し、長野県全域で、地域福祉活動の実績を共有する予定。
私は、ここに、長野県の底力を感じている。
1.今回の事例を学ぶポイント(5つのき)
① きっかけ 気付いて、始める
② キイパーソン(最初の一歩を歩み、それに連なる人がでてきた)
③ 貴重な地域の宝(ひと、もの・・・)
④ 希望・気持ち(思いやり)
⑤ 協働(広がる助け合いの輪)
「来たくなる長野」
2.目標<コミュニティの再生>
①コミュニティに所属するもの同士の相互の関わり
②関わり対するアイデンティティ、愛着
③それらを実現しやすい地理的な空間
④互いを認め合うコンセンサスと一定の規範
⑤コミュニティを支える宗教や祭り等の文化の形成
⑥人材や活動等の一定の地域資源の存在
3.大桑村「ますや」と山之内町「わくわく商店街」活動の特徴
① 地域が直面する問題に答えた活動「足に靴を合わせる活動」
② 資源(ひと、もの、かね、知らせ等)の活用
③ 地域のみんなの居場所、縁側、ほっとできる場づくり
④ 「みんなが参加者」誰がボランティアで、誰が担い手であるか分からない活動
⑤ それぞれの能力を活用した活動=来たい気持ちになってもらう。
⑥ 人を増やす方法:楽しく、無理なく、見える活動
⑦ 「皆で考え、工夫する」組織の透明性
4.茅野市の活動
① 今までの実績と計画があった。
② 地域拠点が4カ所あり、地域に課題に迅速に取り組める。
③ 専門職と住民が協働(互いの役割に関する協議と合意)
④ 住民主体=住民も解決の当事者、互いに助け合う絆とサービスの連携
⑤ 調整する人の配置
5.社協の役割
① 住民の要望を聞くこと
② 求めている人と求められている人を繋ぐ
③ 活動のイメージを一緒に考える
④ 活動をできるだけ多くの人に伝え、理解者を増やす
⑤ 可能な地域の宝を活動希望者に紹介する。
⑥ いつも一緒に悩む
6.総括
① 「タ」互いの協力
② 「ス」進めてみよう
③ 「ケ」健康づくり、元気づくり
④ 「ア」アイデア
⑤ 「イ」居場所、居心地
投稿日 5:54 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2012年10月、長崎県民生委員大会で講演をさせていただいた。テーマは「つなぐ心 地域の絆づくり〜期待される民生委員・児童委員とは〜」である。たくさん委員の方々が、地域から来られていた。島部から船に乗られて来ておられる方々も少なくない。感謝を込めて、私自身が委員の方々から教えていただいたことを精一杯、お伝えした。大きな会場で会ったが、会場の庭には、小さな石像が置かれていた。このような気持ちが、民生委員の方々の思いであると思っています。


会場から長崎空港に向かう時、太陽が輝いていることに気がついた。車をとめていただき、写真を撮った。明日はきっと希望の太陽が昇るだろう。民生委員・児童委員の方々が、毎日、地域の方々に届けようとしているように。

なお、地域で、深刻な生活問題が顕在化している。その問題に取り組んでおられる民生委員・児童委員の方々の働きに、心から敬意を表したい。そして、その活動を支援する仕組みを作らないと、委員の方々が燃え尽きてしまう危険性がある。
以下、私が月刊福祉に執筆した内容をお伝えしたい。感謝を込めて。
『民生委員・児童委員』
1.はじめに
2011年3月11日、東日本大震災が起こり、亡くなられ、行方不明になられた方々のご冥福をお祈りし、被災地で復興を目指しておられる方々の希望の光を覚え、これからも支援していくことの大切さを強く思う。被災地の復興は、私たちの未来である。と同時に、ほぼ同じ人数の方々が、毎年自死しておられる、いわゆる無縁死という事実を忘れてはならない。今、私たちは、どのような日本社会を創るのか、復興を通して、子どもたちにどのような社会を引き継いでいくのかという問いに答えていく使命があると考えている。
民生委員制度は、大正6年に岡山県に設置された「済世顧問制度」と、大正7年に大阪府で始まった「方面委員制度」が始まりである。今に至る90数年、
民生委員は、「社会奉仕の精神をもつて、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もつて社会福祉の増進に努めるものとする。」(民生委員法第1条)の精神に基づき、様々な課題に取り組んできた事実がある。その歩みに敬意を表しつつ、新たな社会づくり、まちづくりに共に取り組みたいと願うものである。
2.民生委員・児童委員の悩み
1年にわたり、民生委員推薦のあり方を検討した際に、民生委員・児童委員の方々から活動のやりがい、悩み、苦労についての意見をお聞きした。日頃の活動として、「高齢者の好みが様々であり、また、なかなか心を開いてくれないため、支援のきっかけがつかみにくい」「障害者のいる世帯の将来が心配になる」「子育て中の家庭の貧困化や、不登校児童の問題など、児童の問題は複雑多岐にわたっており対応が困難」「様々な相談が寄せられ、予想外の相談や、対応困難なものもある」「セキュリティの整ったマンションの訪問、一人世帯の方への訪問が困難」「新住民との接点の結び方や、自治会のない地域での住民との連携、働く世代との関わりが難しい」と言われた。そこには、今日の地域における課題が明確に示されている。これに対し、「民生児童委員として、何を求められているのか不明確に感じる」「学校や関連機関の事業・会議が多い。本来ボランティアがすべき仕事や募金・調査など、活動以外の仕事が負担となる」「市民の民生児童委員に対する認識度が低く、職務を行う上で支障を感じる」「行政等からの依頼事項が多い。また、個人情報の関係で連携が困難」という、民生委員・児童委員活動を妨げる要因が、本来は連携して課題に取り組むはずの行政、相談機関や施設、社会福祉協議会等により生み出されている事実が散見される。個々のニーズに対応し、それぞれの委員がどのように関わるのかという合意がなされていない。また漠然と役割を期待されても、委員自身どのように連携すれば良いか戸惑うばかりである。また、情報の共有や研修、日常的な相談を通した活動支援が行われなければ、燃え尽きて「眠生委員」となるのは当然である。これらの民生委員・児童委員の悩みに答えていく責任が、専門職および機関・団体にある。
3.今日の地域福祉課題
2007(平成19)年7月、「民生委員制度創設90周年活動強化方策<広げよう 地域に根ざした 思いやり>100周年に向けた民生委員・児童委員行動宣言」(全国民生委員児童委員連合会)が採択された。その内容は、今日の福祉課題を認識し、それに取り組む活動を提起したもので、人と人との絆を再生しようとしたものでもある。
児童や高齢者虐待、死亡後長期間発見されない男性単身者が増加し、自殺者は1998年以降3万人を超え続けている。また、高齢者・障害者の消費者被害が顕在化し、特に、一人暮らしの高齢者が格好の標的になっているが、被害にあった自覚のない人も多い。高齢者、障害者、さらには、日本語のわからない外国人などの災害時要援護者の避難支援等が課題となっているが、これらの根源には、孤立・孤独という共通の課題がある。すなわち、「絆が切れた社会」の姿が見えてくるのである。
第一に、明日への希望が見えない現実がある。ある小児科医が、多くの青年が非行にはしらない4つの理由をあげた。第1は適度な忙しさ、第2は関心事があること、第3は家族や友人との心の繋がり、第4は明日への希望である。お金を失うと生活の危機、名誉を失うと心の危機、希望を失うと存在の危機と言われる。困難な状況にあっても、また乗り越えなければならない多くの課題があっても、一人ではなく、共に考え、悩み、そして明日への歩みを応援する人がいることを伝え続ける絆を大切にする社会でありたい。
第二に、コミュニティとは、生活の場、存在が守られる場、休息の場、安心できる場、自分らしくいられる場、生産と消費の場、ともに学ぶ場、それぞれの人と出会う場、助け合う場、家族が生活する場、保健医療福祉等のサービスを利用する場である。そして、地域に対する愛着、アイデンティティ、相互の関わりがないところに、コミュニティは存在しない。そこには、明らかに、住民関係があり、共に生きていくための一定の合意が必要となる。このコミュニティ、すなわち絆をたえず築いていく社会でありたい。
第三に、経済至上主義は、巨大な消費社会を作り上げた。そして、生産的であることが価値、生産的でないことが非価値となり、その対比がそのまま「善と悪」の考え方に結びつくならば、互いを支え合う共生社会を築くことができない。一人の存在を認め合い、困難に直面する声なき声があるならば、それを代弁して、連帯して解決していく社会でありたい。
第四に、まちづくりの視点が大切である。農業、林業、漁業が衰退してきた結果、山間地域、海岸地域が過疎地域となった。それぞれの地域の強みを最大限活用した、働く場の開拓を含めたまちづくりのできる社会でありたい。
それらの関わりに、民生委員・児童委員は重要な働きをしてきたのである。
4.地域住民の生活を支える民生委員・児童委員の役割
①地域に散らばるアンテナとしての役割
生活苦に直面している人・家庭を発見する受信アンテナと、必要な情報を提供する発信アンテナの役割が必要である。民生児童委員は、たとえば「一人の不幸も見逃さない」ことを目標に掲げ、全国各地で伝統的な見守り活動を実践してきた。そして、孤立し、必要な情報が届かない住民に対し、様々な工夫をしてきた。そもそも情報は、当事者、サービスや施設、専門職等多様である。また直接本人からの相談以外に、同僚、住民、介護者等を通じて入ってくる情報、ボランティア活動の場に行って得る情報もあり、受信アンテナとしての役割は大きい。他方、必要な援助を知らず、また誤解して利用しておらず、困難な状況にある住民に対して、理解しやすい情報を届け、説明を加えて理解をすすめ、さらに一緒に相談機関を訪問する等、発信アンテナとしての役割も担っている。
②専門機関や専門職につなぐ役割
民生児童委員は、得た情報を、つなぐ役割をもっている。特に、経済的な問題だけでなく、家族問題、心の問題等が重なっている場合、民生児童委員だけで対応することが難しく、迅速かつ確実に必要な所に情報をつなぐことが不可欠である。なお、このためには、得られた情報を通し、何が課題なのか把握し、つなぐか所を確認すること、対応の緊急性を判断する知識が求められる。
③住民や関係機関と協働する役割
住民の生活全体を支えるために、住民、自治会、町内会、保健医療福祉機関、ボランティア団体と協働した取り組みが大切である。また、必要な場合には、当事者の情報を共有し、対応を明確にして、それぞれの役割を合意することが必要である。特に児童や高齢者の虐待に対しては、迅速かつ総合的な対応が求められる。児童虐待は、経済的困難と親族・近隣・友人からの孤立が要因となり、高齢者虐待は、本人の認識がない場合もあり、多くは発見が遅れる。過重な負担を一人で抱え込んでしまう養育者や介護者に対し、関係者間の日頃からの情報交換、支援のための協議や研修が欠かせない。
④代弁者としての役割
今までご指導いただいた民生児童委員の働きは、困難な問題を抱えている住民とともに歩み、その心に希望の火をともし続けてきた働きであった。そして地域問題を見過ごすのではなく、実像として把握するために、その情報を必要な機関につなぎ、当事者を代弁していく役割を担ってきた。約30年数前、県福祉総合計画をたてるために1週間現地調査に入り、ホームヘルプサービスについてお聞きしたが、その必要性を主張したのは、民生児童委員だけであった。
⑤新たなサービスを開拓する役割
「繰り出し梯子」とは、公的サービスを必要とする人にサービスが届かない現状を打開するために、狭間を埋め、支援していく柔軟かつ先駆的な活動を意味する伝統的な言葉である。今日においても、公的サービスだけで生活困難な状況を解決することはむずかしい。ふれあいいきいきサロン活動は、高齢者、障害者、子育て中の親等を対象に、地域を拠点にして、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を決め、運営していく仲間づくりの活動である(全国社会福祉協議会『「ふれあい・いきいきサロン」のすすめ』)。2006年の介護保険の改正によって介護予防が強化されたが、その実績はすでにサロン活動で積み重ねられており、同活動に関わっている民生児童委員も多い。
⑥まちづくりの推進者としての役割
前号の絆社会、共生社会、連帯社会、参加社会を目指すことためには、住民の福祉理解を促進する取り組みや、住民自身が自分の問題として地域問題を理解する機会を提供する、日々の活動や継続的取り組みによってはじめて実現するものであり、民生委員活動の意義はそこにある。
5.民生児童委員の活動を支援する仕組み
以下、西東京市において議論した要約をお伝えする。
①役割の明確化
役割が多様化し、またたくさんの会議等に出席することによって、多忙になっている傾向にある。それぞれの地域において、中心的役割を明確にする必要がある。
②日常的活動を支援する仕組み
民生児童委員が、日々の活動の中でさまざまな課題を抱え孤立することのないよう、同協議会や事務局が、相談を受け付け、連携して課題解決に取り組むこと。必要な場合、専門機関の援助を受ける体制を整えること。経験の長い委員が新任委員のフォローを行なうなど、各地区の実情に応じた支援体制の構築が求められる。
③民生児童委員協議会に対するバックアップの体制
同協議会活動の自主的活動を支援するために、行政や社会福祉協議会との連絡会議等による日頃からの緊密な連携が望まれる。
④市民全体に向けた民生児童委員の役割と活動に係る広報の強化
⑤民生児童委員の代表者が計画の段階から加わった研修の実施
以前、全国民生委員児童委員連合会元顧問故光田釥(きよし)氏にインタビューを行った。そこで、光田さんが語られた以下の言葉をもって、私の役割を終えたい。「民生委員制度が90年近くも連綿として続いているのは、この専門性<民生委員法の基に行動する専門的な立場>と生活者の視点という両面性をきちんと調和させながら、先輩の民生委員・児童委員たちが取り組みを進めてこられたからだと思います。この世界に数少ない活動に誇りをもって、私たち一人ひとりの民生委員・児童委員が活動や制度を支えているという気持ちで取り組んでいただきたいと思います。」(「月刊福祉」7・8月号)
投稿日 13年01月12日[土] 10:43 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2011年12月、熊本市にある、熊本ライトハウス(社会福祉法人慈愛園が経営する盲ろうあ児施設)と熊本ライトハウスのぞみホーム(知的障害者更生施設)を訪問することができた。個々の利用者の生活を大切にするハード、ソフト面の配慮を目のあたりにして、私は、北欧の福祉国家で見学したホーム・ハウスを思い出した。揺るがない信念が日常生活に築かれ、また国の政策の基軸となっていた。
日本においては、福祉予算が切り詰められる時代にあって、ハウス・ホームで生活なさっておられる方々が、どのような状態にあっても、一人の人間として守られ、大切にされるという福祉の使命を、何とかして継続していこうとするライトハウスの意気込み、使命感に、私は、感動したのである。
室内は広々としており、天井も高い。それぞれの部屋には、生活する人の個性が見られる。視覚に障害があっても、それぞれの方々は、広い生活空間を体験し、木の温もりと響きを実感し、そこで働く職員の心を通して生きていくことの温もりを味わっておられると、私は感じた。ある利用者のカラフルなデザインの布団カバーは、家族の思いが込められていた。
ライトハウスルーテル教会に関係する社会福祉施設である。これからも、伝統ある社会福祉法人慈愛園の一つの有力なハウスとして、輝き続けていただきたい。ライトハウスには、目指すことができる、立ち戻ることができる、ルーテルのミッションがあるのだから。ご案内して下さった施設長山口初子氏に心より感謝したい。
以下、るうてる法人会連合が出版した『未来を愛する 希望を生きる―共拓型社会の創造をめざして』(人間と歴史社)の文章を紹介する。
熊本ライトハウスミッション
「わたしは、神がそのみ業を演じられる偉大な舞台の袖に立っておられると、
しばしば感じたものです。愛の種が、荒れて耕されていない土にまかれました。
わたしたちはそれに水をそそぎ、神が育ててくださいました。そして何という
収穫を、神はこの小さな園に働く人々にお与えくださったのでしょう。
この41年間、わたしがしたことではなく、わたしの主エスが世の終わりまで、
わたしと共にいるとのお約束をお守りくださったことを誇りたいのであります。」
※昭和37年(1962)モード・パウラス先生の慈愛園辞任の辞
社会福祉事業に従事する私どもは、パウラス先生の神への愛と奉仕の業に倣いまた、慈愛園の定款にも明記されております「イエスキリストによって示された、愛と奉仕の精神に基づき多様化な福祉サービスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより」を目指し、クリスチャンワーカーとしての使命感を常に覚えたいものです。
【 まかれた種 】
大正9年(1920) 熊本で開かれた日本福音ルーテル教会第1回総会において、「社会事業創始の件」について熊本に施設を設立する決議が行なわれ、その委員長にモードパウラス先生が就任されました。就任後パウラス先生をリーダーとした仲間の愛と奉仕の業は、子どもやお年寄りのお世話をする「慈愛園」を創設し社会福祉分野での事業の取り組みは広範にわたりましたが、その中で視力に障害を有する子どもたちへの処遇が課題となっていました。
その課題に取り組むため理事長のパウラス先生を始め潮谷総一郎園長、視力障害の石松量蔵神水教会牧師と九州女学院英語教師のマリアン・パッツ先生が加わり4名の障害児福祉サービス研究会が発足し、昭和24年(1949)日本福音ルーテル教会第26回総会において障害児施設の設立が決議されました。
【 めばえ 】
慈愛園から2キロほど離れた三菱重工所有の家屋を買収し、理事会はライトハウス設立を決議し、「ライトハウス」の命名者潮谷総一郎先生が初代園長に就任。
昭和28年7月1日(1953)県下唯一の盲ろうあ児施設 熊本ライトハウスの設置が定員40名で認可されました。
【 あゆみ 】
昭和31年(1956)7月には潮谷総一郎先生の尽力により、慈愛園は全国に先駆けて熊本目の銀行も発足しました。昭和33年(1958)門脇トミ2代目園長は、慈悲に満ち誠実で祈りの人でありまた、目や耳に障害を持った子どもたちに対して使命感に燃え、施設運営の基盤作りに懸命に取り組まれました。
子どもたちが障害を有しているため社会経験に乏しくなることから、社会性と心身の鍛錬を目的に創立3年目の昭和30年からボーイスカウト活動が開始され、日本最初の盲児・ろう児によるボーイスカウト熊本14団が誕生し、その後ガールスカウトも結成され日本アグーナリーの基礎ともなりました。
これまで子どもたちは与えられた建物で大集団の生活を余儀なくされ、盲学校や聾学校に通っていましたが、昭和40年(1965)7棟の新らしいホームを頂き家庭的な雰囲気の中で生活指導や役割分担と責任など、個別の人間形成に大いに役立ち福祉施設の小舎制の先駆けともなり、クリスマスプレゼントとして児童・職員ともども嬉しい思い出です。
昭和46年(1971) 山口拓爾3代目園長は実践行動の人でありました。入所児童の人格形成はもとより広くボランテイア活動をとおして障害福祉の分野における貢献は、施設内外を問わず全国に及び地域の夜警や清掃奉仕活動も30年を超える活動が続けられました。
その後入所児童数も昭和48年(1973)94名をピークに減少していきました。
【 成人棟の誕生 】
少子化は入所児童も例外ではなく、視力や聴力の単一障害児よりも知的な発達の遅れや自閉的傾向など、いくつかの障害を併せ持ったいわゆる重複障害児の存在が注目されだし、平成3年(1991)年には18歳を超えた入所者19名の中に11名の重複障害者が20歳~25歳という現状でありましたので、その子たちの生活の場を求めざるを得ず成人施設の設置という課題となり、保護者・職員をはじめ関係者の懸命な働きにより平成5年(1993)知的障害者更生施設(盲重複障害者施設)熊本ライトハウスのぞみホームとして定員30名で開設され、悲願でありました児童施設年齢超過児の解消として関係者の大きな喜びとなりました。また、地域への社会貢献のひとつに平成元年(1989)からは市社会福祉協議会からの委託事業として、地域老人の給食サービスふれあいランチとして約100食を月2回提供する事業も現在まで続いております。
障害を有している子も普通の子と同じように、教育や福祉のサービスを受けその子らしく生きていかれる社会を構築することが求められ福祉施設の存在はそのような使命を託されているのです。心身の状況により、自己主張や自己の権利を表現できない社会的に弱い立場の人々に対して、イエス様が誰にでも分け隔てなく、殊に重荷を負っている人々にイエス様自から歩み寄り手を差し伸べ導かれていることは、社会福祉事業従事者のミッションとして忘れてはならないものです。
最後に、80数年前にパウラス先生を日本に送り出されたアメリカのルーテル教会の継続された祈りと献げものに感服し、感謝申し上げますとともにこれから私どももそのスピリットを継承し、日本福音ルーテル教会と近隣教会のたゆまぬお支えによりいま福祉制度の大きな転換期にも各自与えられた場において、クリスチャンワーカーとして愛と奉仕の業に励んで参りたいと願っております。

投稿日 12年02月14日[火] 5:34 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
« 前のページ
次のページ »