私にとって学びの多い練馬パワーアップカレッジ
練馬パワーアップカレッジの入学者は、第10期を迎えました。この間、たくさんの方々が学び、巣立っていかれました。そのお一人おひとりの存在が、働きが、練馬区の宝であると確信しています。
Ichikawa's Office
社会福祉関連
練馬パワーアップカレッジの入学者は、第10期を迎えました。この間、たくさんの方々が学び、巣立っていかれました。そのお一人おひとりの存在が、働きが、練馬区の宝であると確信しています。
2017年10月、秋田市で記念大会が開催されました。県内各地より、バスを連ねて来られた民生委員の方々の熱き思いに、私は心を揺らされました。
秋田県民生委員児童委員の方々が担って来られた・子どもが生まれた家庭に届ける「ハッピーメッセージ」・子育て支援・孤立を防止する様々な取り組み・要援護者の対する緊急時のマップづくり・多様な小地域福祉活動は、大きな実績です。その原点は、以下の歌詞と近いと思いました。
講演の前、千秋公園に向かう道を歩いていましたら、歌が聞こえました。思わずその場所に行くと、千秋公園の近辺で生まれ、秋田を代表する歌手、東海林太郎の歌でした。「母に捧げる歌」の一節に感銘を覚えました。
「胸もさけよと 声かぎり われは歌わん 高らかに 歌うことこそ わがつとめ 我がのぞみなり わが命」
東海林太郎の歌う姿勢と、秋田県内の民生委員児童委員の方々の活動の姿勢に共通点を感じています。
千秋公園の紅葉
投稿日 17年10月26日[木] 10:02 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
縁の会は、高齢者福祉関係で働く方々、高齢者福祉に関心のある方々が中心に企画をたて、実施するのが縁の会です。その意図は、実践報告を聞き、話し合い、情報交換をし、そして励まし合うこと。
報告者紹介
・岩崎智之@おとなりさん。
地域の方々と繋がることを大切にしている「~お散歩&日常デイ~おとなりさん。(http://otonari30.com)」そして、農業と福祉の連携である「ノウマチ(http://www.minhata.com/management)」を運営。どちらも、ホームページは要チェック。掲げられている理念は、心に語りかけられているような強い想いを感じます。「地域の方々と共に、地域のために。」をテーマに、「地域力再生業」を目指し、児童福祉や農業も視野に入れ「地域が本来持つ力」を引き出すべく活動中。「未経験であることが嫌い」な性格。
趣味は路地裏散歩、ラーメン食べ歩き、そして対称的にマクロビオティック。好きなアーティストはエンヤ。介護事業経営研究会(C-MAS)スペシャリスト(特別専門家)みそソムリエ協会認定みそソムリエ。
練馬区 街かどケアカフェ
・オレンジカフェ金のまり
テーマ「自宅を改造!デイサービス・認知症カフェに」
地域のお年寄り、一人ひとりの中にある「つながり」の結び目は、ゆるやかにほどけはじめていると考えます。そこから生まれる「ゆらぎ」に正面から取り組むために、オレンジカフェを始めました。デイサービスや居宅介護支援だけではどうにもならない。私たちは限界を感じ始めていました。
日々の暮らし、近所の人々とのつながり、近所の人の持つ力…。そんな時、私たちは「オレンジリング」そして、「京都式オレンジカフェ」を知りました。それが今の街かどケアカフェにつながっています。人と人とのゆるやかなつながりの中で「老いを生きる」場を作ろうと思いました。顔見知りができた。顔見知りに会えた。頼りたいお医者様に出会えた…。
そんなささやかなできごとを大切に、これからもオレンジカフェを続けていきます。
今回は、ノウマチと金のまりの実践から学びます。どうぞお気軽にご参加下さい。
投稿日 17年09月10日[日] 12:09 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
2017年8月31日、京都市ロームシアターのメインホールにおいて、大会が開催されました。テーマは、「これからの民生委員・児童委員活動に期待されるもの〜民生委員制度のこれまでの歩みを振り返り、これからの展開を考える〜」。表彰式等の公式行事が終わり、私の講演にどれだけの方が残って下さるか、実は心配していましたが、実際に講演を行う時には、たくさんの方々が、熱心に聞いて下さいました。
京都市は、校区の強い地域福祉活動のメッカと言える地域。伝統に裏付けられた地域への愛着と、人々の幸福を願う思いを根底に据えた民生委員児童委員活動が京都市に存在することを実感し、私自身が参加なさった方々に励まされた時でした。
感謝。
投稿日 17年08月31日[木] 6:00 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2017年8月24日、シーガイアコンベンションセンター4階サミットホールにおいて、宮崎県民生委員児童委員大会が開催されました。県内2,400人の民生委員児童委員のうち、約2,300人が参加しておられ、会場はいっぱいになっていました。その熱気に、私は、宮崎県民生委員児童委員を象徴する『3つの木<き>』を思い浮かべました。
1.絆(人と人との絆)
2.郷土愛(生活する地域の文化・宗教に対する誇りと愛着)
3.希望(生活の困難を抱え、明日への希望を失う危機に直面している人に寄り添うことによって、希望の光を届ける)
宮崎県から学ぶ機会を頂いたのが、今から20年前でした。県社協と県内の地域福祉の強化のために検討したいとのご依頼がありました。それをお引き受けする決意をした理由は、孤児の父である石井十次が宮崎県高鍋町茶臼原で行った実践を学びたいというものでした。その後、高鍋町を訪問し、高鍋藩第7代藩主秋月種茂(あきずきたねしげ)による試みがあったことを知りました。貧しさ故に行われていた間引きを禁止し、生まれてくる3人目以上の子どもに対し、一日米二合または麦三合のいずれかを支給し、産婆を大阪から呼び、当時多かった出産による死亡を防ごうと努力したのです。その影響を受けたと言われる石井十次は、今の児童福祉の原点を作った人です。
岡山孤児院20周年となる1907(明治40)年、宮崎県の茶臼原に孤児院を移動しました。たとえば、1905年の東北凶作によって生まれた800名の孤児を受け入れる等、地域、家族が壊れ、捨てられる児童を保護する篤志家です。岡山孤児院12則(1902=明治35年)は、家族主義=小舎制をとり全体の統一を破らない限り各小舎の特殊性を尊重、満腹主義=各自に十分食べさせること、宗教主義=形式的な信仰の強制でなく、人生における信仰の必要性を自覚させること、密室主義=個人的な話し合いによる教育、旅行主義=見聞を広めるように努力、米洗主義=米をとぐようにそれぞれの特質を現させる、小学教育=孤児院小学校で行う、托鉢主義=孤児院の維持を零細な寄付金募金によること。委託主義、実行主義、非体罰主義、実業主義を内容としています。
宮崎県の民生委員・児童委員の方々の絆をつくろうとする働きと、石井十次の生き方に、私は、共通点があると考えています。
また、私は、県社協の方々と、いくつもの市町村を訪問しました。宮崎、都城、日南、日向、日之影、西都、えびの、串間、西米良、須木村(現小林)、山田(現都城)、門川、諸塚、等々を訪問し、地域福祉実践を学び、住民の方々と話し合いました。そこで、それぞれの伝統文化を知りました。また高千穂にも行きました。住民の方々は、伝統文化を尊重し、また今まで活動なさってこられた先輩の民生委員児童委員が築かれた助け合いの文化に敬意を表し、郷土への愛、愛着をもっておられることに気づいています。
今、社会は、混迷の中にあります。家族、地域の絆が弱まってきて、孤立、虐待、自殺が増加しています。だからこそ、互いの違いを尊重する社会、相互理解に基づく社会、協力し合って問題を解決していく社会、明日への希望を実現する社会、お互い様の心が根付いた社会という『共助社会』を築くことが必要になっています。それは、日々の希望の光を灯す働きから生まれます。宮崎県民生委員児童委員の方々の日々の実践から、私はそのことを学んでいます。
今回の訪問は、宮崎県の友人に、今までの感謝を述べる意味もありました。そして、講演は、20年近くご指導頂いた民生委員児童委員の方々へのお礼を申し上げる機会と考え、精一杯努力したつもりです。感謝。


投稿日 17年08月25日[金] 1:50 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
平成 29 年 7 月 9 日(日)、東京ビックサイトに両陛下をお招きし、民生委員児童委員10,000人が参加して、民生委員制度創設 100 周年記念大会が開催されました。
式典第 1 部(14:30~15:00)
開会宣言
民生委員・児童委員物故者黙祷
民生委員児童委員信条朗読
天皇皇后両陛下のご臨席
国歌斉唱
式辞挨拶 厚生労働大臣・全国社会福祉協議会会長・東京都知事
厚生労働大臣特別表彰
全国民生委員児童委員連合会会長表彰
天皇皇后両陛下のご退席
閉会の辞
続く2日目、有楽町のよみうりホールにおいて、以下の100周年記念テーマ別研修Ⅴ「これからの民生委員児童委員協議会活動について」が行われました。
[登壇者] 金井 敏 氏(高崎健康福祉大学教授)
越智 和子 氏(琴平町社協常務理事・事務局長)
藤目 真晧 氏(全民児連 副会長)
[コーディネーター] 市川 一宏 氏(ルーテル学院大学学事顧問)
会場の熱気から、新たな100年に向けて、確かに歩みが始められたと実感した2日でした。式典開催前 img-801154950
投稿日 17年07月25日[火] 11:21 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2017年6月28日、第7期同委員会の一回目の会議が開催されました。

今回は、①地域おける高齢者の孤立等の生活問題が深刻化していること、②高齢者を支える家族、地域の支援機能が弱まり、新たな地域づくりが急がれていること、③区市町村の役割を強化することが求められている一方、介護保険財政は逼迫していること、④障害者福祉計画、地域福祉計画等の計画との整合性が問われていること、⑤総合事業の内容が各区市町村によって異なり、差が見られること等、様々な課題が明らかになっています。委員会としても、住民、当事者、民生委員児童委員、ボランティア、NPO、社会福祉法人、社会福祉協議会、医師会、歯科医師会、薬剤師会等の団体、介護福祉士、社会福祉士等の専門職団体、行政の各担当部署等の役割の合意に基づく協働が必要です。委員各位の積極的な提案を大切に、計画としてまとめていきたいと考えています。
資料は、東京都のHPに掲載されています。どうぞご覧下さい。
投稿日 17年07月24日[月] 7:11 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
上智大学教授であられた松本栄二先生が理事長である麦の家を訪問しました。松本先生は、ソーシャルグループワークの第一人者であり、日本における実習教育の礎を築かれた方です。松本先生よりお電話があり、中川村での講演をお願いしたいとのこと。また、その前日に、近隣のソーシャルワーカーの勉強会があるので、講師をお願いしたいとのご依頼でした。先生からのご依頼をお断りできるわけがなく、すぐに日程の調整に入りました。新宿駅からバスで約4時間そして、先生が建設から関わられていた『麦の家』を訪問する機会が与えられました。グループホームの案内書を掲載します。そのいたるところで、聖書の「一粒の麦、地に落ちて死なずば、唯一つにてあらん、もし死なば多くの実を結ぶべし」の理念に基づく社会福祉実践共同体を目指す」という考え方がちりばめられています。
私は、援助の原点を学びました。
個室
以下は、2007年の記事です。
「一粒の麦、地に落ちて死なずば、唯一にて在らん」-を基本精神に、長野県で初めて「単独型痴ほう性高齢者向けグループホーム「麦の家」を開所、今年10年目を迎える。
「痴ほう(認知症)というと、嫁が親切に世話をしないからなどと誤解されていたが、認知症は病気、咳のようなもの、やっと正しく理解されるようになった。グループホームは利用者を介護するだけが仕事ではない。利用者が変われば、家族が変わる。家族が変われば、地域も変わっていく。地域福祉の意識を変えていく拠点である。地域福祉の意識変革こそ、21世紀のグループホームの方向」。
93年、中川村の健康福祉大会に講師として招かれたことをきっかけに、95年夏、上智大学のゼミの学生と村に訪れ、農家を借り、単身高齢者世帯と超高齢者夫婦世帯の支援ネットワークについて社会福祉調査を実施した。その中で、村の古老や痴ほう化した高齢者と出会い、人としての温もりや人間愛を見出し、「彼らとともに住むことが幸せ」と確信し、4人の仲間とグループホーム建設を目指した。
98年、「麦の家」は利用者5人という最小規模の単独型グループホームとしてスタート。1年後「麦の家の利用者こそ、家族内関係の再生を促し、共生を目指す家族福祉の原点。利用者の変化が地域の福祉化を促す力となっている」ことを確信したという。
「麦の家」は「住みなれた地域で、自分の家庭生活のリズムを変えることなく、または、可能な限り、それに近い時間と空間を持つ場でありたい」と言う考えから、木と紙と土でできた山小屋風の家が並ぶ。現在、定員12人で、2人用が3棟、夫婦棟、5人用1棟。1棟ごとに玄関、キッチン、風呂、居室があり、靴を脱ぎ、履くことで、個人と共同生活の場をはっきりと分けている。だから、利用者は個室のことを「私の家」と言う。
「麦の家」は入居時に、週1回以上面会に来る、来た時は「文句をいう」という契約をする。預けぱなしではケアはできない。来ると、お礼ばかり言う人がいるが、苦情を聞くことで、介護が改善される。
「認知症はすばらしい病気。建前と本音を使い分けることもなく、幼子のように、人間性がもろに出る。認知症のお年寄りこそ、社会を照らす光だ」とも。
「麦の家」は地方の福祉実践活動の一環として、月1回、周辺福祉関係諸施設のスタッフや指導者が実践事例を持ち寄り、研究、討議をしている。
また、10月28日午前9時20分?午後4時30分まで、中川村文化センターで、「第2回麦の家・地方の福祉実践研究集会」を開く。上智大学名誉教授のアルファンス・デーケン博士(生と死を考える会全国協議会名誉会長)が「生と死、そしてユーモアを考える」。松本理事長が「生と死を選ぶことの出来る場を創る-認知症高齢者向けグループホームから考える-」と題してそれぞれ講演する。「死を看取るということについて」をテーマにパネルディスカッションもある。詳細は麦の家(TEL88・4069)
投稿日 17年07月23日[日] 10:35 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
2017年5月27日、日本社会福祉教育学校連盟、日本社会福祉士養成校協会、日本精神保健福祉士養成校協会が合併した日本ソーシャルワーク教育学校連盟が創設されました。これは、長年、多くの方が願っていた教育の統合であり、「ソーシャルワーク教育学校に課せられた社会的使命に鑑み、ソーシャルワーク教育の内容充実及び振興を図るとともに、ソーシャルワーク及び社会福祉に関する研究開発と知識の普及も努め、もって福祉の増進に寄与することを目的としています。」
ソーシャルワーク教育は、現代社会にあって、その重要性がますます高まっています。この大同団結を契機に、多くの方々の理解を得て、困難にある方々を支援し、また顕在化しているさまざまな生活問題を予防するためにも、求められるソーシャルワーカーを一人でも多く育成し、社会に輩出していくことを決意した時でした。
新会長の白澤政和氏の挨拶
2017年5月20日、第10回学園祭が開催されました。
第10回カレッジ祭1
学園祭は、私たちの思いを形にする場です。1年半にわたり、知識と実践の学びを積み重ねてきた第9期生、また知識と実践とのたくさんの出会いを経験して、学びを始めている第10期生が企画を担当し、今回はココネリという新たな会場で実施できました。
それぞれの期生には、それぞれの持ち味があり、今回も、学園祭の会場のすみずみに活かされていました。
私は、本年で学長を務めて10年になります。第1回から学園祭を見ていて、いずれも心のこもった内容であり、感動を覚えます。そして、たくさんの卒業生が、学園祭に来られます。いろいろな地域福祉実践をしている方もおられます。また、ご自分で、ご家族の介護等を担っておられる方もおられます。その方々が戻って来られる場を、今の学生がつくって下さった。それぞれの思いを形にして、学園祭のプラットホームに置いておかれました。
私にとって、たくさんの方に出会い、再会し、本当幸せな一日でした。
感謝。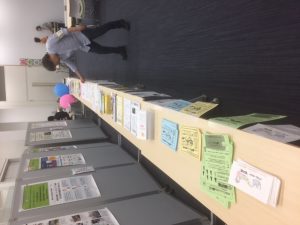
パワーアップカレッジの卒業生の実践を示したたくさんのパンフレット。これが、パワーアップカレッジの強みです。
投稿日 17年05月23日[火] 7:57 AM | カテゴリー: 社会福祉関連