2013年の夏、福岡県内の市区町村社会福祉協議会会長・常務理事・事務局長研修会が行われた。九州北部は、7月に長期間豪雨が続き、大きな被害を受けた地域もあり、「地域の絆」の大切さを共に確認した時となった。
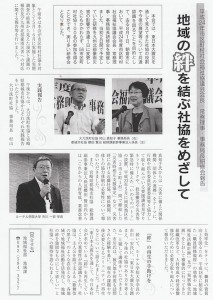
私は、県社会福祉協議会の方にお連れ頂いて、社会福祉協議会災害ボランティアセンターが継続して開設されていた八女市を訪問した。八女市を流れる川が氾濫し、たくさんの住宅が被害にあって、まだ片づいてはいなかった。

私たちは、災害ボランティアセンターを訪問し、関係者の方々を慰労し、そして奥に集まっていたグループに声をかけた。彼らは、福島県から支援に来たメンバーで、東日本大震災の時に支援を受けた御礼に、福島から駆けつけて来たのであった。よく知っているメンバーもおられ、私は、「絆」の意味を学ぶことができた。東日本大震災の被災地のことを忘れてはならないし、それぞれの地域で共に歩むことの大切さを実感した。
「被災地を訪問し、まだ瓦礫が片付かず、生活の拠点を失った方々の生活の場が、未だ築かれていない現実、支援が遅れている現状を見続けてきました。
しかし、自分たちで、コミュニティを再建しようとする動きが確実に生まれており、この地道な歩みと足を揃えることが、今、本当に求められていると思います。明日を目指して、被災地で生まれた「希望の光」と共に歩みたい。
そして、日本全国で、今回の死亡者、行方不明者の数を超える人たちが、自殺、孤立死している現状に、少しでも挑戦したいと思っています。
すなわち、被災地支援を通して、今、日本社会が求めている「希望」と「絆」を再生していくこと。今は、それぞれの場で、互いに支えあい、生きていくことが大切な時期になっています。
私は、その基盤を築き、若者たちが、希望を持って生きていくことができる社会づくりに努力したいと再度思いました。」
投稿日 13年10月19日[土] 3:00 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
宮城県内では、復興に向けてさまざまな取り組みが行われている。その中で、社会福祉協議会の役割への期待が大きい。そのため、今、各社協が地域課題に対してどのような取り組みを決意し実践しているか、また実践していくかを検証し、それぞれの社協に活かすことができるか考えていく必要がある。さらに、今回の研修においては、住民や関係者と協働で創り上げる地域福祉活動計画の意義を参加者で検討し、明日の地域社会を描こうとした。


投稿日 13年10月18日[金] 4:17 PM | カテゴリー: 社会福祉関連
第10集会(特別集会) 企画および進行予定について(案) 全民児連事務局
1.日 時 平成25年10月11日(金) 9時30分~12時30分
2.会 場 幕張メッセ「幕張イベントホール」
3.テーマ 東日本大震災被災地における民生委員・児童委員活動 ~被災地と全国との絆による被災地支援の強化に向けて~
4.本集会がめざすもの(主旨) 東日本大震災の発生から当日で2年7か月を迎えることとなるが、被災地はなお厳しい状況が続いているだけでなく、復興にはなお多くの時間を要することが見込まれている。 そうしたなかにあって、被災住民の支援にあたっている民生委員・児童委員の心身の負担が高まっており、委員支援も大きな課題となっている。また、本年12月には震災後初の一斉改選を迎えようとしている。 本集会は、震災被災地の復興状況や住民生活、そのなかで顕在化している課題、および被災地における委員活動の状況等について、被災地の委員からの紹介を通じて全国から参加する関係者が理解を深めるとともに、地元に戻り、広く関係者に報告いただくことを通じて全国的な理解や支援の継続につなげることをめざす。 さらに、被災地の経験を広く全国の関係者が共有することにより、今後に向け、災害時要援護者支援活動やそのための態勢整備に役立てていただく。
5.コーディネーターおよび報告者(敬称略)
【コーディネーター】 ルーテル学院大学 学長 市川 一宏
【発表者】 岩手県大船渡市民児協 副会長田代研三
・宮城県東松島市民児協 主任児童委員内野牧子
・ 福島県大熊町民児協会長秋正夫
・仙台市民児協 副会長森孝義
・千葉県浦安市西地区民児協 副会長渡邊武

投稿日 13年10月11日[金] 10:40 PM | カテゴリー: カテゴリ無し,社会福祉関連
2009年9月25日午後5時19分日没

2009年9月25日午後5時26分日没

2010年9月21日5時49分日の出

2011年9月13日4時53分 満月
![2011-9-13 ① 赤富士と満月 撮影3時53分[1]](http://kichikawa06-08.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/09/766f39fbffd2bfe9a307a87d0c82ba01-300x194.jpg)
2011年9月13日5時25分 赤富士と残りの満月
![2011-9-13 ② 赤富士と残月 撮影5時23分[1]](http://kichikawa06-08.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/09/6182011a9d4e9774b00a71da934755ab1-300x224.jpg)
2013年9月18日5時48分 日の出 朝霧の逆さ富士

投稿日 13年09月26日[木] 9:49 PM | カテゴリー: 富士山(佐藤弘氏)
山中湖での撮影ですが、あえて撮影時期の表示はやめました。
雲の状況で 涼しさがながれだしてくるようですね(特に③は)。
③は白鳥が飛んでいる ともみえそうな雲でした。
①

②

③

投稿日 13年08月02日[金] 7:43 AM | カテゴリー: 富士山(佐藤弘氏)
夏の富士山と云えば 「冬場の紅富士に対し 赤富士」があげられます。
富士山の表層にある玄武岩が朝日を受けて 赤く焼けます。
やや毒々しい感じもしますが見れば見るほど特徴のある風景です。

2007-7-17
 2008-10-28 初冠雪の赤富士
2008-10-28 初冠雪の赤富士

2010-8-5 帯雲の逆さ赤富士

2011-9-13 赤富士と残月
投稿日 13年07月20日[土] 9:57 PM | カテゴリー: 富士山(佐藤弘氏)
報告にあたって
地域における孤立や孤独、虐待、そして貧困等の問題を解決するために、民生委員・児童委員、主任児童委員(以下、民生委員と言う)への期待が高まっています。しかし、民生委員は、5つの壁に直面していると思います。
①<先行する期待の壁>地域の問題を民生委員だけで解決することは無理です。それぞれの地域は、民生委員、専門職、ボランティア、住民が協働して課題に取り組むために、それぞれの具体的な役割を確認することが不可欠です。
②<多様な役割の壁>どこまで、どのような活動したら良いか、民生委員自身が戸惑うことがあります。それぞれが、「したいこと」「できること」「求められていること」を確認し、活動のための知識と技術を高めていくことが必要です。
③<地域の理解の壁>多くの住民は、民生委員活動には長い歴史があり、先人の重要な働きが地域を支えてきたという事実、現在も民生委員活動が地域問題を予防解決しているという現実を知りません。民生委員も、自分の活動を説明し、地域の理解を広げることが求められています。
④<日頃の活動の壁>民生委員は、日々、切磋琢磨しながら活動をしています。同時に自分だけで課題を背負い、活動の目標と意味を見失うこともあります。民生委員同士、関係者と共に、活動を振り返る機会があり、活動の意味を再確認できる場が大切です。
⑤<活動を支える体制の壁>活動を支援する体制を確認しなければなりません。民生委員・児童委員協議会において新任民生委員を支える体制、同協議会において民生委員、同協議会担当者、専門職がともに情報交換し支え合う体制を築くことが活動の前提です。
本報告は、研修を通して、以上の課題を解決することを目指しました。
①多様な活動をバックアップする研修:「発見」「相談」「地域連携」「啓発」「民生委員・児童委員協議会の運営、活動の記録」という項目に分けています。
②スキルアップできる研修:講義と受講者の参加型研修を組み合わせ、「学ぶ」→「気づく」→「描く」→「変わる」サイクルを取り入れています。
③啓発を目的とする研修:研修を通して、民生委員が住民の福祉理解を促進し、地域における福祉を考える機会を提供することを目指しています。
④アイデアを大切にする研修:活動は地域の特性等によって異なります。民生委員それぞれが日頃工夫しているアイデアを共有することを大切にしています。
⑤活かす取り組み:民生委員が自分の強みと課題に気づき、強みはより強化し、課題は改善していくことのできるプログラムにしています。
今日の委員活動に関する負担の増大が指摘されるなか、委員同士の「助け合い」、「支え合い」が重要となっており、そうした人間関係づくりの面からも研修の重要性が増しています。本研修体系の実現により、委員の皆さまの活動支援につながることを切に願っています。
平成25年3月 民生委員・児童委員研修のあり方に関する検討委員会
委員長 市川一宏
民生委員研修体系
ワークブック
事例集
投稿日 13年07月15日[月] 11:37 AM | カテゴリー: 社会福祉関連
« 前のページ
次のページ »
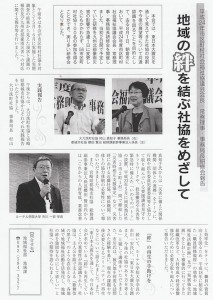







![2011-9-13 ① 赤富士と満月 撮影3時53分[1]](http://kichikawa06-08.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/09/766f39fbffd2bfe9a307a87d0c82ba01-300x194.jpg)
![2011-9-13 ② 赤富士と残月 撮影5時23分[1]](http://kichikawa06-08.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2013/09/6182011a9d4e9774b00a71da934755ab1-300x224.jpg)


























